相撲の化粧まわしのルーツは“大名の見栄”だった
土俵入りのたびに力士が身につける、金糸が輝く「化粧まわし」。一見すると単なる衣装のようですが、その刺繍には家紋や縁起物、地域の象徴など、力士やスポンサーの誇りが込められています。
今回のNHK総合『チコちゃんに叱られる!』(2025年10月17日放送)では、この日本相撲界の伝統美に隠された“意外なルーツ”を深掘り。ゲストの花村想太(Da-iCE)さんが「戦う前の男らしさを見せるもの」と答えると、チコちゃんが「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と一喝。その正解は――「大名の見栄」でした。
この“見栄”という言葉の裏には、武士の誇り、芸術の進化、そして日本人の美意識が重なっています。この記事では、化粧まわしがどのようにして生まれ、どんな変化を遂げてきたのかを、歴史と文化の両面から詳しくたどります。
宮中儀式から始まった「力と美の儀礼」
化粧まわしの起源は、千年以上前の平安時代。相撲博物館の土屋喜敬学芸員によると、当時の宮廷では「相撲節会(すまいのせちえ)」という行事が行われていました。これは五穀豊穣を祈るための神事で、力士たちは天皇や貴族の前で力を披露。相撲は神聖な儀式の一部だったのです。
そのとき、力士たちが身につけていたのが「とうさぎ(たふさぎ)」と呼ばれる布。これは腰に巻く下着のようなもので、現在の化粧まわしの原型とされています。当時はまだ装飾的な意味はなく、“神に力を見せるための清らかな装い”でした。
戦国の世、相撲は「大名の威信」をかけた競技へ
時代が進み戦国時代に入ると、相撲は庶民の娯楽を超えて、武士の間で人気の“勝負事”として定着していきます。各地の大名たちは「相撲に強い者」を家臣として抱え、「うちの家来は最強だ」と誇示するため、相撲大会を開くようになりました。
ここから、力士の装いにも変化が生まれます。強い力士を持つことは大名の名誉であり、その力士を飾る衣装こそが「見栄の象徴」となったのです。特に、豪華な織物や金糸で装飾されたまわしは、「主君の財力と文化水準」を示すものとして重んじられました。
この頃から、相撲は単なる格闘技ではなく、“美と力を競う舞台”としての性格を帯び始めたのです。
江戸時代、化粧まわしが「芸術」へと進化
江戸時代になると相撲は庶民の娯楽として大流行。町人文化の中心となり、芝居や歌舞伎と並ぶ大衆エンタメのひとつに成長しました。観客が増えれば、当然「見た目の華やかさ」も重視されます。
ここで登場するのが、紀州藩が贈った伝説の「紀州まわし」。金糸で虎や竹を描き、見事な刺繍が施されたその豪華さは圧巻で、「まるで屏風絵のよう」と称えられたほどです。これをきっかけに他の藩も競うように派手なまわしを作り、化粧まわしは一気に豪華絢爛な文化へと発展しました。
江戸中期の元禄文化の華やかさも拍車をかけます。尾形光琳や菱川師宣らの絵画に見られる「装飾美の精神」が相撲にも反映され、化粧まわしは“土俵の芸術品”としての地位を確立しました。刺繍には家紋や縁起の良い図柄、そして地域の特産物や風景までが描かれるようになり、見る人の心を惹きつける美の競演となったのです。
「見栄」を超えて、職人技と文化が息づく現代へ
しかし、華やかな化粧まわしも実際の取組には向かず、力士たちは試合専用の「取組まわし」を使用します。化粧まわしは土俵入りの儀式専用として残り、力士の“顔”を象徴する存在に。
そして現代では、その伝統に新しい風が吹き込まれています。スポンサー企業や自治体、さらには人気キャラクターとコラボした化粧まわしが登場し、令和の相撲界を彩っています。
たとえば、熊本県のくまモン、ハローキティ、さらには『北斗の拳』のラオウを描いたまわしなど、まさに“ポップカルチャーと伝統の融合”。これらのまわしは、ベースボール・マガジン社などの協力を得て制作され、時代を超えて「日本の美」を発信し続けています。
化粧まわしが語る日本人の「見栄」と「美」
相撲の化粧まわしには、“力士の誇り”だけでなく、“主君の誇り”、“職人の誇り”が重ねられています。そこにあるのは単なる飾りではなく、日本人が大切にしてきた「美しくあれ」「誇りを見せよ」という精神。
刺繍一針一針には、贈る人の想いと、贈られる力士の気迫が宿っています。まわしを贈る側は「力士よ、堂々と勝て」、受け取る側は「この誇りを土俵で見せる」と心に誓う。そんな絆こそが、化粧まわしの真の価値なのです。
まとめ
この記事のポイントを整理します。
・化粧まわしの起源は平安時代の宮中儀式「相撲節会」。
・戦国時代、大名が強い力士を抱えることで“見栄の象徴”に。
・江戸時代の紀州まわしが豪華化のきっかけとなり、元禄文化と共に芸術品の域へ。
・現代ではキャラクターコラボやスポンサー企業デザインなど新しい進化を遂げている。
・化粧まわしは「力士・主君・職人」の誇りをつなぐ、日本の伝統美の象徴。
次に相撲を観るときは、力士が身につける化粧まわしに注目してみてください。その刺繍の中には、千年を超えて受け継がれてきた“日本人の美意識”が、今も静かに息づいています。
出典:NHK総合『チコちゃんに叱られる!』2025年10月17日放送
https://www.nhk.jp/p/chicochan/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


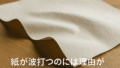
コメント