フクロウの首が驚くほど回る本当の理由は?
今回の『チコちゃんに叱られる!』では、フクロウの首がどうしてあれほど広い範囲を回せるのか、体の構造に迫る内容でした。何気なく見ているフクロウの動きに、実は進化が積み重ねてきた高度なメカニズムがあるとわかり、思わず番組に引き込まれました。この記事では、首の骨の数、目や耳の配置、危険を察知する行動まで、放送で語られたポイントをしっかりまとめます。
【ダーウィンが来た!】絶滅危惧種シマフクロウの野生復帰へ密着3年!人とフクロウの感動ドキュメント|2025年4月13日放送
首の骨が人間の2倍あるからこそ実現する“驚異の可動域”
フクロウの首が大きく回る理由として最も大きいのが、首の骨の数です。
人間を含む哺乳類は、首の骨(頸椎)が7つですが、フクロウはその2倍の14個を持っています。関節が多いほど動かせる角度が増えるため、フクロウは左右後方まで大きく振り返るような動きが可能になります。
番組では、実際の骨格模型を用いて、骨がどのように連動し、どのくらいの角度まで動かしても血管がつぶれないようになっているかを丁寧に紹介していました。
首の動脈には特殊な“余裕”があり、急な回転で血流が止まらないよう、体の中で巧妙に守られているという説明も印象的でした。見た目以上に複雑な体の内部構造が、あの滑らかな動きを作り出しているのです。
正面にある大きな2つの目が“首の可動域”を必要としている
フクロウの顔の特徴といえば、正面に並んだ大きな目。この目は、ただ可愛いだけの特徴ではありません。フクロウは肉食で、小さな獲物を狙うため、距離感を正確に測る必要があります。そのため両目で同じ対象を見つめる『両眼視』を行い、立体的に距離を把握しています。
しかし、正面に向いている分、視野が狭くなります。横を見ることがほぼできず、後ろに注意を向けることも難しいため、その弱点を補うべく首を自由自在に動かす必要が生まれました。
つまり、フクロウは大きく回る首を“視野の代わり”として使っているのです。
耳の穴の位置が左右でずれている理由
番組で特に興味深かったのが、耳の構造です。
フクロウの耳の穴は左右で高さが異なり、片方は少し上、もう片方は少し下に位置しています。このずれが、音が届く時間のわずかな差を感じ取らせ、音の方向だけでなく距離まで正確に判断することを可能にしています。
暗闇でも獲物を迷わず仕留められるのは、視覚だけでなく、この“音の立体的な捉え方”によって位置を特定しているためです。
この耳の構造は、夜行性の捕食者として生き抜くための大きな武器だと感じさせられました。
種類によって異なる“危険回避”の姿──細く変形して木に擬態
放送では、フクロウが危険を感じたときに体を細くして木の幹に擬態する行動も紹介されていました。
アナホリフクロウ や コノハズク、ユーラシアワシミミズク など、それぞれの種類によって姿の変え方は異なりますが、共通するのは「自分を大きく見せるのではなく、細くして目立たなくする」という点です。
体をスッと伸ばし、細長い柱のように変形する姿は、鳥とは思えないほどの変化です。これは敵に見つからないよう、木の幹や枝の一部に見せるための高度な生存戦略です。
番組では、実際に細くなった メンフクロウ の姿も映され、観察している人たちが驚くシーンが印象的でした。
各地の施設で観察できるフクロウの多彩な行動
放送では、実際にフクロウたちを観察できる施設として 我孫子市鳥の博物館 や 掛川花鳥園 が紹介されました。
我孫子市鳥の博物館では骨格標本や生態展示が豊富で、首の構造を学ぶには最適な場所として紹介され、掛川花鳥園では自然に近い形でフクロウたちの動きや表情を観察できる様子が映し出されていました。
観察するだけで、首の動き、耳の構造、擬態行動など、放送の内容がそのまま実体験として理解できる場所として魅力的です。
フクロウが“首を回す動物”であることには明確な理由がある
フクロウの首の可動域は、単なる特徴ではなく 「狩るため」、「生き残るため」、「周囲を把握するため」 といった生活のすべてに直結しています。
首の骨の数、目の位置と構造、耳の位置のズレ、危険時の変形などが重なり合い、夜の世界で生き抜く力を支えています。
鳥というより、まるで“静かに進化を積み重ねてきたハンター”としての姿を感じる内容でした。
まとめ
フクロウの首がよく回るのは、骨の数が多いだけでなく、目・耳・姿勢・狩りの方法など、多くの仕組みが連動しているためです。
今回の『チコちゃんに叱られる!』は、姿の可愛らしさの裏側にある圧倒的な生存能力を見せてくれました。
普段は静かに木に止まっているだけのフクロウですが、その一つひとつの動きに驚くほどの理由が隠れている──その奥深さを感じられる回でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


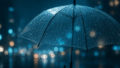
コメント