なぜ人は手をつなぐ?痛みと不安をやわらげる理由
「なぜ人は手をつなぐの?」。親や恋人、友人と自然にしている行為ですが、深く考えたことがある人は少ないかもしれません。実はこの行為には、単なる愛情表現以上の科学的な理由が隠されています。2025年8月22日に放送されたNHK総合『チコちゃんに叱られる!』では、この身近な疑問が取り上げられ、専門家の解説や実験を通じて驚きの答えが紹介されました。この記事では、その放送内容をもとに「手をつなぐとどうして安心できるのか」「なぜ痛みが減るのか」を、わかりやすくまとめます。読むことで、普段の生活で自然に行っている「手をつなぐ」という行為に新しい意味を見つけられるはずです。
手をつなぐと安心できるのはなぜ?
まず最初に思い出してほしいのは、幼い頃に親と手をつないだ経験です。信号待ちや人混みの中で親の手をぎゅっと握ると、それだけで怖さが薄れ、安心できた記憶があるでしょう。大人になってからも、緊張する場面や人混みの中で恋人や家族と手をつなぐと、自然と気持ちが落ち着くことがあります。
この安心感は単なる気分の問題ではなく、人間の脳が持つ仕組みに基づいた反応です。触れることで得られる安心感は、進化の過程で育まれた大切な能力であり、人が社会的なつながりを維持してきた理由の一つともいえます。
スタンフォード大学の研究が示した効果
番組で紹介された解説を行ったのは、明治大学の堀田秀吾教授です。堀田教授は、スタンフォード大学などが2020年に行った研究を取り上げました。実験の内容は、仲の良いカップルや夫婦51組を対象に、脚に熱の刺激を与えたときの痛みを測定するというものでした。
その結果、手をつないでいる場合には痛みや不快感が軽くなるという明確な違いが出ました。手をつながないときに比べて、痛みの感じ方が和らぐのです。しかも驚くべきことに、痛みが弱まった人の脳を調べたところ、前頭前野という部分が活発に働いていることが分かりました。
脳の仕組みと「触れる」という刺激
脳は同時に複数の刺激を受けたとき、「痛み」「冷たさ」「かゆみ」などの感覚よりも「触れる」という情報を優先的に処理します。そのため、手をつなぐという行為は、脳が痛みよりも先に処理する大事な刺激となり、結果的に痛みが軽減されるのです。
この仕組みは「ゲートコントロール理論」とも関連しています。これは1960年代に提唱された考え方で、「触れるなどの心地よい刺激が痛みの信号を遮断する」というものです。スタンフォード大学の実験は、この理論を現代の脳科学の方法で裏付けたといえるでしょう。
絆の深さが効果を強める
研究ではさらに興味深い結果が示されました。痛みの減少具合は、2人の絆の深さや親密さと大きく関連していたのです。信頼関係が深い相手と手をつなぐほど、痛みや不安を和らげる効果は大きくなります。
特に、共感力の高い女性が相手の場合にその効果が顕著であることもわかっています。これは相手の気持ちを理解しようとする力が安心感を増幅させるためと考えられます。単なる身体的な接触ではなく、「心のつながり」が脳に影響を与えているといえるのです。
芸能人夫婦での実験
番組内では、芸能人夫婦である濱口優さんと南明奈さんが登場し、この実験を体験しました。結果はまさに論文通りで、二人が手をつないでいると痛みが弱まり、安心感が増すことが確認されました。視聴者にとっては「日常で自然にしている行為が、実は科学的に根拠のあるものだ」と知る貴重な瞬間になったはずです。
手をつなぐことの心理的効果
手をつなぐ効果は痛みの軽減だけではありません。心理的にも大きな意味があります。例えば、緊張しているときに誰かと手をつなぐと心拍数が安定し、不安感が減ります。これはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられるためです。実際、手をつなぐことは「安全で安心な状態」を脳に伝えるサインになっています。
子どもと親の関係にみる効果
子どもが夜道で怖いときや、病院で注射をするときに親の手を強く握ると安心するのも、この仕組みの一例です。親子の手つなぎは、安全を確保するためだけではなく、子どもに「守られている」という感覚を与える役割を持っています。これは成長しても続き、大人になっても大切な人との手つなぎが安心につながるのです。
よくある質問(FAQ)
Q:手をつなぐだけで痛みはなくなりますか?
A:完全に痛みが消えるわけではありませんが、スタンフォード大学の研究で「不快感や痛みが減る」ことが実証されています。
Q:知らない人とでも効果はあるの?
A:効果はありますが、信頼関係が深い相手との手つなぎの方がより強い効果を発揮します。
Q:男女で違いはあるの?
A:研究では共感力の高い女性が相手のときに効果が強まりやすいことが示されています。
Q:子どもにも同じ効果があるの?
A:はい。子どもは親の手を握ることで安心し、不安や痛みをやわらげることができます。
まとめ
今回の『チコちゃんに叱られる!』で取り上げられた「なぜ人は手をつなぐのか?」という問いの答えは、「痛みと不安を弱めるから」でした。脳は「触れる」という刺激を優先的に処理するため、手をつなぐと自然に安心できるのです。そしてその効果は、相手との絆や信頼関係の深さによって強まります。
普段の生活で無意識に行っている「手をつなぐ」という行為が、心や体を守る重要な役割を果たしていると知ると、身近な人とのつながりを大切にしたくなります。大切な人と手をつなぐことは、言葉以上に気持ちを伝え、心の健康を支えるシンプルで強力な方法なのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


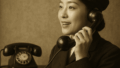
コメント