ChatGPT:
絵文字の謎:なぜ生まれたのか?

まず番組で最初に取り上げられたのは「なぜ絵文字ができたの?」というテーマでした。ゲストの槙野智章さんが「気持ちを伝えたいから」と答えましたが、チコちゃんに叱られてしまいました。正解は「ハートマークをどうしても送りたかったから」という意外な理由です。
解説に登場したのは、大手IT企業で絵文字の開発を手掛けた栗田穣崇(くりたやすたか)さんです。当時の主要な通信手段はポケットベル(ポケベル)で、最初は数字だけでメッセージをやり取りしていました。その後、カタカナやひらがなが使えるようになり、表現の幅は少しずつ広がっていきました。そうした中で新しく生まれたのが「ハートマーク」の絵文字でした。
しかしその後に発売された漢字が表示できる新型ポケベルでは、ハートマークを外してしまったのです。その結果、利用者からの支持を得られず売れ行きは大失敗。この出来事は業界で「ハートマーク事件」と呼ばれるようになりました。それほどまでに人々にとって「気持ちを表す記号」が大切だったことを物語っています。
その後、栗田さんはNTTドコモのiモードプロジェクトに参加。ここで再び絵文字の重要性に注目し、なんと176種類もの絵文字を考案しました。笑顔や食べ物、乗り物など、多彩なアイコンが生まれ、携帯電話でのコミュニケーションを一気に楽しく、そして便利にしたのです。
今ではこの日本発の絵文字文化は世界中に広がり、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にも展示されるほど高い評価を受けています。つまり、最初は「ハートマークをどうしても送りたい」というシンプルな願いから生まれたものが、いまや世界共通のコミュニケーションツールにまで成長したのです。
横浜に中華街がある理由

続いてのテーマは「なぜ横浜に中華街があるの?」でした。ゲストの柳原可奈子さんは「中華が大好きな人が店を始めて、行列ができて広がったから」と答えましたが、チコちゃんに叱られてしまいました。正解は「欧米人との通訳で中国人が活躍したから」という歴史的な背景です。
1853年、マシュー・ペリー率いる黒船が浦賀に来航し、日本は200年以上続いた鎖国を終えて開国しました。その後、1859年に横浜で欧米諸国との貿易が本格的に始まります。しかし当時の日本人は英語に不慣れで、貿易の現場は大混乱。そこで頼りにされたのが、欧米商社に雇われていた買弁(ばいべん)*と呼ばれる中国人商人たちでした。
中国人は欧米人と英語で交渉でき、さらに日本人とは漢字を使った筆談が可能でした。このため、日本と欧米の橋渡し役として非常に重要な存在となったのです。結果として、多くの中国人が横浜に移り住み、生活の基盤を築くようになりました。
その積み重ねがやがて街をつくり上げ、現在の横浜中華街へと発展していきます。今では世界最大級の規模を誇り、フカヒレの姿煮や北京ダック、そして行列のできる焼き小籠包など、本格的な中国料理を味わえる観光スポットとして知られています。横浜中華街は、単なるグルメの街ではなく、幕末から続く歴史と文化の交流が形になった場所だと言えるのです。
アスファルトの謎:正体はなに?

最後に取り上げられたテーマは「アスファルトってなに?」でした。ゲストの岡村隆史さんが「ゴミのかたまり」と答えると、チコちゃんからおなじみの「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と一喝。正解は「はるか昔に生きていた微生物の死がい」という驚きの答えでした。
解説を担当したのは東京理科大学の加藤佳孝教授。教授によると、アスファルトの原料である原油は、古代の海や湖にいた微生物が死んで海底に沈み、その死がいが長い年月をかけて堆積し、地中で熱と圧力を受けながら化学変化を繰り返してできたものです。その時間はなんと数百万年から数億年。つまり、私たちが毎日歩いたり車で走ったりしている道路は、まさに地球の歴史そのものを固めた舞台なのです。
さらに、世界には自然のままのアスファルトが大量に存在する場所もあります。その代表がトリニダード・トバゴにある「ピッチ湖」。湖一面が黒いアスファルトで覆われており、世界的にも珍しい光景として知られています。
この話を聞くと、普段はただの舗装材と思っていたアスファルトが、実は地球の悠久の時間と微生物の営みがつくり出した「微生物の化石の結晶」であることに気づかされます。身近な道路一つとっても、自然の神秘が隠されていると考えると、足元の風景がぐっと特別なものに感じられます。
槙野智章さんのちょっとした悩みと番組告知
休憩中のコーナーでは、引退後にメディア出演が増えた槙野さんが「サッカーボールを使った挨拶で何をすればいいかわからない」と告白。チコちゃんから「炒めたらいい」などユーモラスなアドバイスが送られ、スタジオは笑いに包まれました。
さらに番組では10月10日生放送「国民的早口言葉コンテスト」の募集告知もあり、今後の展開にも期待が高まります。
まとめ
今回の「チコちゃんに叱られる!」から学んだポイントは次の3つです。
-
絵文字誕生のきっかけは「ハートマーク」——日本発の文化は世界を変えた。
-
横浜中華街の起源は通訳として活躍した中国人——歴史的背景がグルメタウンを育んだ。
-
アスファルトは太古の微生物の死がい——足元には地球の悠久の歴史が眠っている。
普段の生活で何気なく使っているものや街の風景にも、こんな深いストーリーが隠されていると知ると、ちょっと世界の見え方が変わってきます。次回の放送も、また新しい「なぜ?」が解けるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

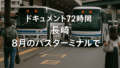
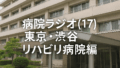
コメント