ペンライトの秘密・かき氷のふわふわ・海のニオイとは?
8月1日(金)放送の「チコちゃんに叱られる!」では、夏らしい話題が盛りだくさんでした。コンサートで使われるペン型ライトのルーツや、家庭ではなかなか再現できない“ふわふわかき氷”の作り方、そして海辺で感じるあの独特なにおいの正体など、日常のなかにある「なぜ?」に迫ります。ゲストは俳優の高橋文哉さんとタレントの野呂佳代さん。放送後には、番組で紹介された内容を追記予定です。
コンサートでペン型ライトを振るようになった理由

ペン型ライトをコンサートで振る文化は、1974年8月に大阪球場で開催された西城秀樹さんのソロコンサートがはじまりとされています。もともとのきっかけは、ヒデキが「ファンの顔を見たい」と願ったことでした。会場がとても広く、しかも夜だったため、ステージから客席が見えにくいことを気にした西城さんは、ラジオ番組で「懐中電灯を持ってきて」とファンに呼びかけました。この提案が放送された翌日、実際に大阪球場に集まった多くのファンが懐中電灯を持参し、それを振って応援したのが最初だとされています。
西城秀樹さんの思いとファンの行動
この出来事の背景には、当時の関係者やファンの証言が残っています。コンサート制作に携わっていた増田武司さんは、ヒデキの指示で球場近くのデパートに懐中電灯を買いに行ったファンが続出し、売り切れ状態になった店舗もあったと語っています。さらに、懐中電灯が買えなかった人々を電気街まで案内したというエピソードも伝えられています。
また、2016年の「東京新聞」のコラムには、西城さん本人が「初めて見る客席の光はとても幻想的だった」と記しており、その光景がどれほど印象的だったかが分かります。この一体感のある光の演出が、のちに“ペンライト文化”として定着する原点となったのです。
変化していくライトと応援スタイル
1975年以降になると、懐中電灯の代わりにより軽くて手軽な簡易型の白いライトが使われるようになり、そこに色付きのセロハンを貼って色を変える工夫が生まれました。1980年代に入ると、化学反応で光るケミカルライト(サイリウム)が登場し、より華やかで安全な応援スタイルが広まっていきます。
このケミカルライトを最初に開発したのはアメリカのアポロ計画の研究から生まれた技術で、本来は火や電気を使わない安全な照明用でした。それが日本では釣り具やパーティーグッズとしても売られ、いつの間にか誰かが会場に持ち込んだことをきっかけに応援アイテムとなったとされています。
やがて2010年代に入ると、アイドルグループのライブ文化が急速に広がり、ペンライトはより洗練され、色の切り替えや連動機能を備えた“公式ペンライト”として登場。ライブごとに振り方や動きが決まっているケースも多く、客席の中心にいるファンの動きを見て、他のファンが真似するという応援の一体感がさらに強まっていきました。
西城秀樹の演出とライブ文化への影響
また、西城秀樹さんはステージ演出にも工夫を凝らしていました。声援が大きすぎて歌が聞こえなくなる場面では、あえてマイクスタンドを振り回すパフォーマンス(マイクスタンドアクション)を取り入れることで、視覚的なインパクトを生み出しました。このマイクスタンドは、ミュージシャンのムッシュかまやつさんが見つけた軽量アルミ製スタンドを使い、特注で作られたものだと言われています。
こうした演出とファンとの関係性が、後のライブ文化全体に影響を与えました。つまり、今のペンライト文化は、西城秀樹さんの「ファンの顔を見たい」という優しさから生まれた発想と、それに応えたファンの熱意が形を変えて受け継がれてきたものだといえます。
家のかき氷がシャリシャリで、お店のかき氷がふわふわな理由

「チコちゃんに叱られる!」では、なぜ家庭で作るかき氷はシャリシャリしていて、お店で食べるかき氷はふわふわになるのかという疑問が紹介されました。答えは、氷をゆっくり凍らせて、とけ始めを削っているからというものでした。詳しく解説してくれたのは、東京海洋大学の鈴木徹名誉教授です。
氷の作り方の違いが食感を分ける
家庭でつくる氷は、水道水を冷凍庫で凍らせるというシンプルな方法ですが、短時間で凍るため空気やミネラルなどの不純物が内部に閉じ込められます。これが氷の中に細かなヒビや気泡を生み、削ったときに砕けやすく、シャリシャリした食感になります。
一方、お店で使われる氷は、千葉県芝山町などにある製氷メーカーがゆっくり時間をかけて凍らせた純氷です。製造では、ろ過された地下水を使用し、-10℃の不凍液の中にアイス缶を沈めて、外側からじっくりと凍らせていきます。さらに、エアレーションと呼ばれる空気の泡を送り込む工程で、内部にある不要な成分や空気を集め、吸い出しては新しい水を補充するという手間がかけられます。この繰り返しによって透明で硬く、密度の高い氷が完成します。
削るときの温度も大事なポイント
鈴木教授によれば、ふわふわのかき氷に仕上げるには、削る直前に氷の表面温度を少しだけ上げることが重要です。冷凍庫から出したばかりの氷は硬すぎて刃が入りにくく、砕けやすくなります。しかし、削る前に常温で数分おくことで表面が少しとけ始め、水分子の結合が弱まります。この状態で刃が入ると、氷がちぎれず、滑らかに削られてふんわりとした食感になるのです。
自宅でふわふわかき氷をつくる裏技
番組では、自宅でもふわふわに近づける方法も紹介されました。以下がその手順です。
-
水道水を10分ほど沸騰させ、空気を抜く
-
常温に冷ましてから耐熱容器に移す
-
ラップで密封し、上からキッチンペーパーでふたをする
-
急激に凍るのを防ぎながら冷凍庫で約10時間ゆっくり凍らせる
-
完成後、氷の中心部分をくり抜いて取り除く
この方法で作った氷は、家庭用かき氷機でも削りやすく、シャリシャリ感が軽減されたやわらかめの仕上がりになります。
沖縄ぜんざいなど多彩なかき氷文化
スタジオトークでは、チコちゃんが「食べたいかき氷」として、沖縄のぜんざい風かき氷を挙げていました。これは、小豆とミルク、きな粉がかかり、白玉のようなお餅が入った和風スイーツで、沖縄県ならではの味わいが楽しめるご当地かき氷です。ゲストの野呂佳代さんも、かき氷好きのお母さんに教えてあげたいと語っていました。
海のニオイの正体は「プランクトンのオナラ」だった?

番組「チコちゃんに叱られる!」で取り上げられた「海のニオイってなに?」という素朴な疑問。その答えはなんと、「プランクトンのオナラ」でした。解説を担当したのは、筑波大学の大森裕子助教。聞き慣れた「潮の香り」や「磯の香り」は、実は植物プランクトンが出すある物質によって発生しているのです。
海のニオイを生むのは「DMS」という物質
海水には目に見えないほど小さな植物プランクトンが、1リットルあたり数万〜数百万匹も存在していると言われています。これらのプランクトンは、光合成を行う際に「ジメチルスルフィド(DMS)」という成分を排出します。これが風に乗って陸に届き、私たちが海辺で感じるにおいの正体になります。
このDMSはもともと強いにおいを持っていますが、海辺に届くまでに薄まっているため、潮風のような爽やかな香りとして感じられるようになっているのです。大森助教はこれを“プランクトンのオナラ”と表現して説明していました。
季節や場所によってニオイが違う理由
海のにおいは、季節や場所によって変化します。国立環境研究所でプランクトンを人工的に培養し、においを比較したところ、春から夏にかけてのプランクトンのにおいが最も強いという結果が出ています。これは、春から夏にかけて植物プランクトンが大量に発生するためです。
また、海の色や透明度も関係しています。たとえば、沖縄やハワイのように透明な海では植物プランクトンが少ないため、DMSの発生も少なく、においはほとんど感じられません。反対に、東京湾などの濁った海では植物プランクトンが多く繁殖し、においも強くなる傾向にあります。
海のニオイと魚の豊かさの関係
植物プランクトンが多い海では、それを餌とする小さな動物や魚が集まりやすくなります。つまり、プランクトンが多い=魚がたくさんいる=おいしい魚がたくさん獲れるという好循環が生まれます。海のにおいが強い場所は、それだけ生き物が豊かな海である証拠でもあるのです。
東京都の葛西海浜公園などでも、潮の香りが強く感じられるのは、こうしたDMSが大気中に多く含まれているからだと考えられています。においは単なる感覚ではなく、海の状態や生態系の豊かさを表すサインとしても捉えられるのです。
【放送情報】
番組名:チコちゃんに叱られる!
放送日:2025年8月1日(金)19:57〜20:42(NHK総合)
出演者:岡村隆史、高橋文哉、野呂佳代
【参考ソース一覧】
・The Japanese Food Lab(かき氷の氷の性質)
・Eater DC(かき氷の温度管理)
・Science Portal(DMSの発生メカニズム)
・Fanlore(ペンライト文化の由来)
・ももいろクローバーZ WIKI(ペンライト応援文化)
・Wikipedia:ジメチルスルフィド (DMS)
家庭で“ふわふわ”を目指すために便利な道具たち

ここからは、私からの提案です。かき氷がふわふわになるには、氷の質や削り方だけでなく、使う道具もとても大事です。家庭でもプロのような仕上がりを目指すためには、氷を均一に削れるかき氷機と、透明で割れにくい氷をつくるトレーがあると便利です。ここでは、家庭でも手軽に使えるアイテムを紹介します。
電動かき氷機と手動タイプのちがい
かき氷機には大きく分けて「電動タイプ」と「手動タイプ」があります。電動タイプはボタンひとつで氷を削ってくれるので、力がいらずに均一な仕上がりになりやすいのが特徴です。特にドウシシャの電動機種「DCSP‑20」は、刃の角度を調整することで氷の細かさを変えることができるため、好みのふわふわ感に近づけやすくなっています。
一方、手動タイプは価格が手ごろで、コンパクトなため収納にも便利です。ドウシシャの「IS‑FY‑20」は、回す力加減で削り具合が変わるため、自分の好みに合わせて調整できるのが魅力です。少し手間はかかりますが、手動でも十分ふんわりとした氷を作ることができます。
| 製品名 | 特徴 | 価格帯 | 電動・手動 |
|---|---|---|---|
| ドウシシャ DCSP‑20 | 刃の調整で細かさ自在 | 約5,000〜6,000円 | 電動 |
| ドウシシャ IS‑FY‑20 | 手軽で省スペース | 約3,000〜4,000円 | 手動 |
氷の質を変える専用トレーもおすすめ
ふわふわのかき氷を目指すうえで、氷そのものの質も重要です。家庭の冷凍庫で作った氷は白く濁りがちで、空気や不純物を多く含んでいます。これにより、削ったときに砕けやすくなり、ガリガリした仕上がりになってしまいます。
そこでおすすめなのが、「透明まる氷トレー」です。ドウシシャの「DCI‑19」は、氷を上からゆっくり凍らせる構造になっており、空気を逃がしながら透明で硬い氷を作ることができます。これにより、プロ仕様の純氷に近い氷を家庭でも再現できるのです。氷がしっかりしていると、削ったときに薄く、やわらかく仕上がりやすくなります。
| 製品名 | 特徴 | 使用目的 |
|---|---|---|
| ドウシシャ DCI‑19 | 空気の混入を抑えた透明氷が作れる | ふわふわ氷の素材づくりに最適 |
購入時のポイントと使い方のコツ
電動タイプを選ぶ場合は、氷の種類に対応しているかどうかを事前にチェックすることが大切です。市販のロックアイスが使えるモデルもありますが、多くの家庭用かき氷機は「専用サイズの製氷カップ」で作った氷しか使えない場合があります。
また、氷を削る前に冷蔵庫で10〜15分ほど常温に近づける「温度戻し」を行うと、よりスムーズに削ることができて、ふわふわ感がアップします。こうしたちょっとした工夫が、家庭でもお店のような食感に近づけるポイントです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


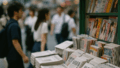
コメント