特別編「ヨーロッパ2077日の地獄 第2部 独ソ戦 悲劇のウクライナ」
2025年7月28日に放送されたNHKの「映像の世紀」特別編では、第二次世界大戦中のウクライナに焦点を当て、独ソ戦の中で起きた悲劇の歴史を映像とともに紹介しました。今回の第2部では、1941年から1943年までのウクライナの過酷な戦争の実態と、その時代を生きた人々の運命、そして今なお続く記憶の語り継ぎについて描かれました。
ドイツ軍の侵攻とウクライナ占領
1941年6月22日、ドイツ軍はソ連に対して宣戦布告をせずに、突然攻撃を開始しました。これは「バルバロッサ作戦」と呼ばれるもので、前触れのない電撃的な侵攻でした。ウクライナの首都キーウもその標的のひとつとなり、街全体が爆撃を受け、市民の暮らしは一瞬で崩れ去りました。住宅や公共施設、教会なども次々と破壊され、多くの市民が命を落とすか避難を余儀なくされました。
電撃戦の威力とドイツ軍の慢心
ドイツ軍は機械化された部隊と空軍の支援による「電撃戦(ブリッツクリーク)」で、ソ連軍を各地で圧倒しました。キーウだけでなく、ハルキウやドニプロといった都市にも次々と侵攻し、当初の作戦は順調に見えました。戦場の映像には、ドイツ兵が次々と前進し、ソ連軍が混乱して撤退する様子が記録されています。
しかし、映像を検証した専門家によれば、これらの勝利の影にはすでにドイツ軍の油断や過信が表れていたといいます。補給線の伸びすぎや兵士の疲弊など、表には出ない綻びが見え始めていたのです。
ソ連軍の焦土作戦と市街地の破壊
ソ連軍はドイツ軍の侵攻に対し、「焦土作戦」と呼ばれる戦術を採用しました。これは、撤退する際に道路・橋・工場・倉庫などを自ら破壊し、敵の利用を不可能にする戦術です。電気や水道などのインフラも対象となり、市街地に設置された時限爆弾や罠によって、後から侵入してきたドイツ軍の被害も大きくなりました。
また、鉄道の線路が意図的に曲げられたり、駅舎が爆破されたりと、戦場は都市全体が破壊の連鎖に巻き込まれる状況でした。特にキーウでは、ドイツ軍が街の中心部に足を踏み入れた数日後、仕掛けられていた巨大爆薬による大規模な爆発が発生し、多数の兵士と建物が巻き込まれました。
このように、ウクライナは戦争の初期から「軍事的目標」だけでなく「生活の場」としての都市機能までもが破壊されていき、住民にとっても兵士にとっても過酷な環境となっていったのです。
ウクライナ市民の地獄の日々
ドイツ軍がウクライナを占領していた期間、現地の人々は極度の不安と恐怖の中で生活していました。都市や村では、ドイツ軍による厳しい支配が敷かれ、食料や医療が不足し、住民の多くが飢えや病に苦しみました。とくに厳しいのは、ナチスの政策によってユダヤ人を中心とする住民が迫害され、大量虐殺が進められていたことです。この事実は徐々に国際社会にも伝わり、同じ頃、日本では対外政策の転換が行われ、真珠湾攻撃へと向かっていくきっかけのひとつになったといわれています。
泥濘期と戦局の変化
1941年の秋、ドイツ軍はウクライナからさらに東へ進もうとしましたが、10月に入ると「泥濘期(でいねいき)」と呼ばれる季節に入りました。これは地面が泥でぬかるみ、戦車や車両の移動が困難になる季節です。これによってドイツ軍の進軍速度は大きく低下し、物資の輸送も滞りました。兵士たちは深い泥にはまり、行軍すらままならない状況に陥ります。
この自然のブレーキにより、ソ連軍は態勢を立て直す時間を得て、各地で反撃を開始しました。結果的にドイツ軍のモスクワ攻略作戦は失敗に終わり、戦争の流れが少しずつ変わりはじめます。
戦火の中にいた人々の現実
その最中、ヒトラーはウクライナを訪れます。彼の訪問はプロパガンダとして大々的に報じられましたが、実際のウクライナの人々の生活は、そうした演出とはまったく異なるものでした。占領された町では、自由は奪われ、監視と暴力が日常となり、働かされる住民や収容所へ送られる人々が後を絶ちませんでした。
市場や通りは静まり返り、食べる物にも事欠く生活。爆撃で崩れた家屋や、道端で亡くなった人々の姿が当たり前のように存在していたといいます。家族と引き離され、避難する術もないまま、子どもたちも大人と同じように過酷な現実に直面していました。
ウクライナ全土が戦場となったその日々は、まさに人間が経験しうる極限の生活だったといえるでしょう。ドイツ軍の占領下で、何もかもを奪われた日常は、深い傷跡として今も記憶されています。
スターリングラードと戦局の転換
1942年、ドイツ軍の進撃は南部へと向かい、次なる戦略目標としてスターリングラードが選ばれました。この都市はソ連にとって政治的にも象徴的にも重要な場所であり、ドイツ軍はその名前からしてスターリンへの挑発としても意味を持たせていたとされています。ドイツ軍は激しい空爆を行い、街の建物は次々と崩れ、瓦礫の山となっていきました。市民の避難も間に合わず、多くの命が犠牲となりました。
包囲された街とソ連軍の粘り
スターリングラードはドイツ軍によって完全に包囲され、あらゆる補給路が断たれる状況になりました。けれども、ソ連軍はこの都市を決して手放すことなく、わずかな物資と兵力で持ちこたえました。市街戦は、建物ひとつ、通路ひとつを巡っての激しい攻防が続き、数ヶ月にわたる壮絶な戦いとなりました。
ソ連軍は冬の訪れとともに反撃に出ます。1942年11月にはドイツ軍の側面を突く大規模な包囲作戦「ウラヌス作戦」を実行。その結果、スターリングラードに展開していたドイツ第6軍は完全に包囲されました。
ドイツ軍の降伏とヒトラーの変化
包囲されたドイツ軍は極寒の中で食料も尽き、補給も絶たれ、ついには1943年2月に降伏します。この敗北は、ヒトラー政権にとって大きな打撃となり、以後ヒトラー自身が人前に姿を見せることが減っていきます。スターリングラードの敗北は、ドイツ軍の「無敵神話」が崩れた瞬間でもあり、世界中にその衝撃が伝わりました。
この戦いを境に、戦局は明らかにソ連側へと傾いていきます。スターリングラードは単なる軍事作戦ではなく、第二次世界大戦の転換点として、歴史に大きく刻まれた戦場となったのです。その後のドイツ軍は、守勢に回りながら徐々に勢力を失っていくことになります。
ソ連軍による反攻とキーウ奪還
1943年8月、スターリングラードの戦いでの勝利をきっかけに、ソ連軍は大規模な反攻を開始しました。南部や東部の前線では各地でソ連軍が勢いを取り戻し、ドイツ軍を次々と後退させていきます。そうした中で、ヒトラーは敗走する自軍に対して「焦土化命令」を出しました。これは、退却の際にウクライナ各地の街や村、工場、鉄道、橋などを意図的に破壊するよう指示するものでした。
フルシチョフの指揮によるキーウ奪還
このウクライナ奪還作戦を統括したのが、ソ連の政治家であり軍事指導者でもあったニキータ・フルシチョフです。彼は地元ウクライナ出身でもあり、祖国を奪還することに強い意欲を燃やしていたとされています。数カ月におよぶ戦いの末、1943年11月、ついにソ連軍は首都キーウの奪還に成功しました。
奪還当日の街は、瓦礫と煙で覆われていました。市内に入ったソ連兵たちは、爆破されつくした建物、放棄された戦車、破壊された橋を目の当たりにしました。市民の多くは避難していたものの、残された人々はその日を涙で迎えたと記録されています。
破壊と再建の繰り返し
しかし、ソ連軍によって解放されたからといって、すぐに平和が戻るわけではありませんでした。ドイツ軍の退却時に行われた破壊行為によって都市のインフラは壊滅状態で、電気・水道・交通すべてが停止し、再建には膨大な時間と労力を要しました。
さらにその後の戦闘で、せっかく復旧させた街が再び戦場となり、また破壊されるという状況が繰り返されました。学校、病院、駅など、生活の中心となる建物も例外ではなく、ウクライナ全体が再建しては壊されるという悲劇の連鎖に苦しみ続けたのです。
この時期のウクライナは、単なる戦場ではなく、人々の暮らしや文化そのものが壊されていく場所となっていました。破壊された町並みと、そこに根を張って生きようとした市民たちの姿は、今も戦争の記憶として語り継がれています。
現代ウクライナと戦争の記憶
番組の最後では、2025年現在のキーウの様子が紹介されました。第二次世界大戦の記憶を伝える「ウクライナ第二次世界大戦史国立博物館」には、ソ連時代の影響が色濃く残されています。今、ウクライナは再び戦火の中にあり、この歴史をどう語り直していくか、模索が続いていると伝えられました。
【出典】
NHK『映像の世紀 特別編「ヨーロッパ2077日の地獄 第2部 独ソ戦 悲劇のウクライナ」』2025年7月28日放送
https://www.nhk.jp/p/ts/X83KVR6573/episode/te/8Z39MV1K6Z/
現代ウクライナから見た歴史の意味とは
現在ウクライナで続いている戦争は、過去に起きた独ソ戦と重なる部分が多くあります。第二次世界大戦でウクライナは、ヒトラーとスターリンという二人の独裁者の間で争われ、二度も焦土となった土地でした。そして今、ロシアの侵攻によって再び同じような破壊と犠牲が繰り返されています。この歴史を見つめ直すことは、単に過去を振り返るだけでなく、今起きている現実をどう受け止めるかという意味でもとても大切になっています。
歴史の連続としての現在
ウクライナでは、過去の戦争の記憶が日々の生活の中で語り継がれています。たとえばバビ・ヤーの虐殺や、Ostarbeiterとしてドイツに送られた人たちの話は、多くの家庭で共有されてきました。こうした過去の記憶は、今の戦争の中でも繰り返されているという認識が広がっています。「また歴史が繰り返されている」という感覚は、今のウクライナの人々の中に深く根づいているのです。
歴史記憶を守る取り組み
ウクライナでは、ロシアや旧ソ連時代の名前がついた通りや建物を改名するなどの脱植民地化(decolonization)政策が進んでいます。また、5月9日の「勝利の日」に代えて、5月8日を「ナチズム勝利記憶の日」として公式に位置づけ、これまでの記念の形も見直されつつあります。これは、過去の支配からの精神的な自立を示す動きでもあります。
現代の戦いと過去の記憶のつながり
情報発信の方法も変わってきました。SNSでは、独ソ戦時代の写真と、今の破壊された町や避難する子どもの写真が並べられ、「違う時代、同じ苦しみ」というメッセージとして広がっています。映像の記録と人々の語りが組み合わさることで、記憶は単なる過去のものではなく、「今、私たちが生きている歴史」として共有されているのです。
| 時代 | 内容 | 被害 |
|---|---|---|
| 1941〜1943年 | ヒトラーとスターリンによる焦土化 | 約800万人の命、都市の85%焼失 |
| 2022年以降 | ロシア軍の侵攻と都市破壊 | 数千人の民間人犠牲、インフラ被害多数 |
| 共通点 | 民間人が最も犠牲になっている | 現地の子ども・高齢者・避難民 |
このように、過去の映像を見つめ直すことは、今の出来事を理解する手がかりにもなります。映像の世紀が届ける映像記録は、過去を知るだけでなく、未来をどう生きるかを考える材料にもなっているのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


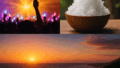
コメント