写楽と蔦重が描いた“歌舞伎の魂”とは?江戸のアート革命を読み解く
「写楽って誰?」「蔦重って何をした人?」そんなふうに思う人も多いかもしれません。でも、彼らの名前は、日本の“アートビジネス”の原点とも言える存在です。今回放送されるNHK Eテレの『木村多江の いまさらですが… 蔦重と写楽が描いた歌舞伎の魂』では、江戸時代に起きた文化の革命にスポットを当てます。この記事では、番組をより深く楽しむために、写楽のデビューの裏側や蔦重のプロデュース術、そして歌舞伎とのつながりまでを詳しく紹介します。
江戸の出版王・蔦屋重三郎とは? “時代を動かした仕掛け人”
まず注目したいのが、江戸の出版界を代表する男、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)。彼は、天明から寛政にかけて江戸・日本橋で活躍した天才的な版元でした。当時の蔦重は、ただの出版業者ではなく、“文化のプロデューサー”と呼ぶにふさわしい人物。黄表紙(風刺漫画のような小説)や洒落本(大人のユーモア本)を世に送り出し、町人文化の中心を作り出しました。
さらに蔦重は、時代の空気を読む力に長けていました。庶民が何に笑い、何に夢中になるのかを敏感に察知し、流行を形にすることが得意でした。そんな彼が目をつけたのが“浮世絵”というメディア。絵を通じてスターや美人、話題を売るという発想をいち早く実践し、現代のエンタメ産業にも通じる「プロデュースの原型」を築いたのです。
蔦重は、すでに喜多川歌麿の『美人画・大首絵』で大成功を収めていました。そこで次に狙ったのが、当時の江戸で爆発的な人気を誇っていた歌舞伎の世界でした。舞台の熱狂をそのまま紙に閉じ込める――そんな挑戦が、のちに“写楽プロジェクト”として動き出します。
謎の絵師・東洲斎写楽の登場 そのデビューはまさに衝撃だった
蔦重が見出したのは、当時ほとんど無名だった東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)。その正体はいまだに謎に包まれています。能役者だったとも、外国帰りの絵師だったとも言われますが、確かなことは、彼がわずか10か月間の活動で日本美術史に鮮烈な爪痕を残したという事実です。
1794年(寛政6年)5月、蔦重の手によって写楽は華々しいデビューを果たします。しかも、その方法が前代未聞でした。歌舞伎役者の大首絵(おおくびえ)28作を、なんと“同時出版”という大胆なやり方で世に出したのです。当時の出版業界では、1点ずつ少しずつ発売するのが一般的でした。28点を一挙に発売するというのは、まさに江戸の「文化的事件」でした。
その絵は、ただの役者肖像ではありません。背景には雲母摺(きらずり)という高級技法が使われ、光を当てると表面がキラキラと輝く仕様になっていました。舞台のスポットライトのような効果で、紙の上の役者が生き生きと見える――そんな工夫が凝らされていたのです。蔦重はこの豪華さを武器に、「写楽という新星が登場した」と世間に強烈な印象を残しました。
絵の中に息づく“歌舞伎の魂”
写楽の絵は、それまでの浮世絵とはまったく違いました。線は太く、表情は誇張され、役者の“演技の瞬間”を鋭く切り取っています。たとえば有名な『大谷鬼次の奴江戸兵衛』では、鬼次の緊迫した目つきや口元の張りつめた表情が見る者に迫ってきます。これは写楽独自の視点――役者が“役を演じる瞬間”そのものを描いた絵でした。
当時の歌舞伎は江戸のエンターテインメントの中心であり、芝居のチケットは高価でも完売が続いていました。蔦重は、その熱気を版画という形で庶民に届けたのです。実際、写楽の大首絵が発売された頃、江戸では歌舞伎の人気役者によるパレードが行われ、街はお祭りのような賑わいに包まれたと伝わっています。まさにアートと大衆文化が一体となった瞬間でした。
それでも、写楽は10か月で消えた
しかし、この成功劇は長く続きませんでした。写楽の活動期間はわずか10か月。1794年5月にデビューし、翌年初頭にはぱたりと作品が途絶えます。現在確認されている作品はおよそ140点に及びますが、その後の足取りはまったく不明です。なぜ彼は消えたのか?
その理由にはさまざまな説があります。ひとつは、写楽の絵があまりに写実的すぎて、当時の人々には“怖い”と感じられたというもの。もうひとつは、幕府の風紀取締りが厳しくなり、役者を描くこと自体が危険だったという説。そしてもうひとつは、蔦重の経営難によって出版事業が縮小したという可能性です。どの説も決定的な証拠はなく、写楽は今も「江戸の幻の絵師」として語られています。
現代に受け継がれる写楽の眼と歌舞伎の血脈
今回の番組では、写楽が描いた四代目松本幸四郎の絵をめぐって、現代の十代目松本幸四郎が登場します。祖先を描いた浮世絵を前に、幸四郎が語る「写楽の筆に宿る役者の魂」は見どころのひとつ。舞台で表情をつくる役者と、筆一本で表情を描く絵師――ふたりの“芸”の共通点を探ることで、江戸と現代がつながります。
また、木村多江や池田鉄洋、加藤小夏らが、作品を前に感じた素直な驚きや感動も紹介される予定です。写楽の絵が200年以上経っても人の心を動かすのは、そこに“生きる人間の息づかい”があるからかもしれません。
まとめ:江戸のプロデュース力が、今を映す鏡になる
この記事のポイントは3つです。
-
蔦屋重三郎は、江戸の出版業界に「流行を作る」という概念をもたらした人物。
-
東洲斎写楽の『28作同時出版』は、今で言う“デビュー戦マーケティング”の原点。
-
歌舞伎と浮世絵が交わることで、江戸の人々は「生きる芸術」を楽しんでいた。
蔦重が写楽をプロデュースした1794年5月――それは、単なる芸術史の一場面ではなく、“日本の表現文化”が動き出した瞬間でした。写楽の消失とともに幕を閉じたその物語は、今の時代にこそ問いかけてきます。
「人を魅了する作品とは、何か?」
その答えを探す鍵が、10月27日の放送にあるかもしれません。
――『木村多江の いまさらですが… 蔦重と写楽が描いた歌舞伎の魂』
放送:2025年10月27日(月)19:30〜20:00
チャンネル:NHK Eテレ(教育)
出演:木村多江、池田鉄洋、加藤小夏、松本幸四郎
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


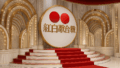
コメント