驚きの共同生活!トッケイヤモリの“家族で暮らす”秘密とは?
タイの夜、静まり返った住宅街で「トッケイ、トッケイ!」という独特の鳴き声が響きます。まるで誰かが名前を呼んでいるようなその声の主こそ、全長30センチを超える巨大ヤモリ――トッケイヤモリです。灰色の体にオレンジの斑点を散らした派手な姿は、どこか神秘的な雰囲気を漂わせています。
東南アジアではこのトッケイヤモリが“家の守り神”として親しまれています。その理由は、家の中に入り込むサソリやムカデ、ゴキブリなどの危険な生き物を食べてくれるから。見た目こそ少し怖いかもしれませんが、実は人間にとってとても頼もしい同居者なのです。
そんなトッケイヤモリの生態は、これまで意外と知られてきませんでした。今回の『ダーウィンが来た!』では、タイの民家で24時間の密着取材を実施。家主たちの協力のもと、彼らの“おうちライフ”を徹底観察し、これまで誰も見たことのない驚きの行動をカメラがとらえました。
巨大ヤモリ・トッケイヤモリの基本プロフィール
トッケイヤモリ(学名:Gekko gecko)は、アジア最大級のヤモリとして知られています。インド北東部からタイ、ベトナム、インドネシア、フィリピンにかけて広く分布し、熱帯雨林から都市部の住宅まで、非常に幅広い環境に適応して暮らしています。
体長は平均30センチ前後、最大で40センチに達する個体も報告されています。鮮やかなオレンジ色の斑点を散らした青灰色の体はとても目立ち、強靭な足の吸盤で垂直な壁やガラスも軽々と登ることができます。
夜行性で、日中は天井裏や壁の隙間、家具の裏などで休み、夜になると活動開始。光に集まる虫を狙って、家の明かりの周囲をじっと見つめる姿は、タイではすっかりおなじみの光景です。
家の中が“ハンティング・ゾーン”!夜の狩人の素顔
トッケイヤモリは、見た目の通り肉食性。主に蛾やバッタ、甲虫などの昆虫を食べますが、小さなネズミや他のヤモリ、さらには毒のあるムカデやサソリを捕食することも確認されています。
行動パターンは“待ち伏せ型(sit and wait)”。壁や天井に張りついたままじっと獲物を待ち、近づいた瞬間に一気に飛びかかります。その瞬発力は見事で、ムカデやサソリのような素早い相手でも逃れられないほどです。
タイの民家では、夜の灯りに集まる虫を狙って外壁や窓際に現れることが多く、「電気をつけておくとヤモリがやってくる」と言われています。こうして人間の生活空間と自然に共存している点が、他の野生動物にはないトッケイヤモリの大きな特徴です。
家族で暮らす!?“単独生活”の常識をくつがえす発見
爬虫類といえば、基本的には単独行動。縄張り意識が強く、同種同士で争うこともしばしば見られます。しかし今回の取材では、その常識を覆す驚きの映像が撮影されました。
民家の壁の裏や天井の隙間で、複数のトッケイヤモリが肩を寄せ合って暮らしていたのです。大人の個体のほか、まだ小さい子どもの姿もあり、まるで家族のように寄り添う様子。親が卵を守るように体を広げ、他の個体が見守るように周囲を警戒する――そんなシーンも記録されました。
この行動は、これまでのトッケイヤモリの研究でもあまり知られていないものでしたが、最近では「共同巣(communal nesting)」と呼ばれる現象が報告されています。複数のメスが同じ場所に卵を産み、共同で守るケースがあるのです。
さらに、一部の研究では「親が子を一定期間世話する」「若い個体が親と同じ巣にとどまる」などの社会的な行動が確認されており、トッケイヤモリは他のヤモリとは異なる“家族的なつながり”を持つ可能性が高まっています。
トッケイヤモリが“守り神”と呼ばれる理由
東南アジアでは古くから、トッケイヤモリは“福を呼ぶ存在”として特別な位置づけを持っています。家に棲みつくと「その家が繁栄する」「金運が上がる」といわれ、鳴き声の「トッケイ!」は“富”や“幸運”を呼ぶ音として縁起が良いとされています。
また、彼らが家の害虫や危険生物を食べてくれることから、「トッケイがいれば安全」「家を清めてくれる」と信じられ、住民はむしろ共存を望むことが多いのです。中には、トッケイヤモリがいることを“神の加護”と考える地域もあります。
一方で、近年ではペット市場や伝統薬としての乱獲も問題になっており、保護活動の対象にもなりつつあります。生態系のバランスを守る存在としても、その役割は見直され始めています。
トッケイヤモリの“おうちライフ”が示す進化のヒント
ダーウィン番組チームが記録したトッケイヤモリの群れ行動は、爬虫類の社会性進化を考える上でも重要な発見です。通常、こうした行動は哺乳類や鳥類で見られますが、トッケイヤモリのような冷血動物が家族単位で暮らすというのは珍しい例です。
これは、生息環境の変化や人間との共存の中で進化した“新しい生き方”なのかもしれません。タイの都市化や気候の影響で住処を変える中、トッケイヤモリが「安全な民家」という場所を選び、家族で協力して生き延びるようになった――そんな背景があるとも考えられています。
放送後の注目ポイントと今後の展開
今回の放送では、家族と思われる複数個体の暮らしぶりがどのように映されるのかが最大の見どころです。卵や子どもを守る様子、獲物を分け合う場面、そして夜の狩りの瞬間――トッケイヤモリの知られざる日常が明らかになるかもしれません。
放送後には、観察された“家族構成”や“共同生活の期間”など、新しい生態の可能性が公表される予定です。この記事も、放送後に番組の発表内容を追記して更新します。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・トッケイヤモリは東南アジアに広く生息する大型ヤモリで、タイでは“家の守り神”として親しまれている。
・夜行性で、ムカデやサソリなどの危険生物を食べ、人と共に暮らす“共生型の爬虫類”。
・ダーウィン番組取材では、複数個体が家族のように暮らす姿が確認され、爬虫類の社会性を考える上で大きな発見となる可能性がある。
まだまだ謎の多いトッケイヤモリ。放送では、その“おうちライフ”の全貌と、彼らがどのように人の暮らしに寄り添っているのかが明かされます。ヤモリの常識を覆す“家族の物語”に、注目です。
(出典:NHK『ダーウィンが来た! 新発見!巨大ヤモリのマル秘おうちライフ』/ウィキペディア/Thailand National Parks/ResearchGate/Behavioural Ecology/Bangkok Herps)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

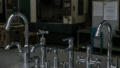

コメント