蛇口づくりの“裏側”を知ると、毎日の水道がもっと面白くなる
水を出すたびに何気なくひねっている蛇口。けれど、その中には多くの工夫や技術、そして職人たちの手作業がつまっています。今回の『探検ファクトリー』では、岐阜県関市で2000種類もの蛇口をつくる工場に潜入し、絶対に漏らさない仕組みや温度調節の秘密に迫りました。
この記事を読むと、普段の生活で当たり前のように使っている蛇口の“すごさ”が分かり、毎日の水との向き合い方がほんの少し変わります。技術の細やかさや手間を知ることで、蛇口を見る目がまったく違ってくるはずです。
2000種類以上の蛇口を生む町・関市の工場へ
番組の舞台は、刃物の産地として知られる岐阜県美濃地方の関市。この地域では、古くから金物産業が盛んで、1933年に蛇口の製造が本格的にスタートしました。長い時間をかけて技術が受け継がれ、現在では2000種類以上の蛇口を製造する大規模工場へと発展しています。
工場内では170人の従業員が働き、それぞれの担当工程に分かれて、手際よく蛇口づくりを進めています。番組の冒頭では、すっちーさんと中川家の礼二さん・剛さんが、作業現場のスピード感や職人の技に驚く姿が印象的でした。
工場には蛇口の形や用途に合わせた数え切れないほどの型があり、日々多品種をつくり続けるためには、スピードと正確さの両立が欠かせません。
6つの工程でつくられる蛇口 最初は“砂型づくり”から
蛇口づくりは全部で6工程。その最初に行われるのが“型づくり”です。ここで使われているのが、金属製の型ではなく砂型という特殊な型。
砂型は耐久性こそ高くありませんが、低コストでたくさんの種類がつくれるため、2000種類もの蛇口に対応するための大切な技術として活躍しています。
砂を押し固めて形をつくり、その中に後で金属を流し込むのですが、砂型は細かい部分にまで形が転写されるため、複雑な蛇口の形に向いています。工場での多品種生産を支えているのは、まさにこの“砂型の柔軟さ”です。
1200℃の青銅を一気に流し込む迫力の鋳造工程
型ができあがったら、次は蛇口の本体部分を形づくるための鋳造です。
工場では1200℃で溶けた青銅を、なんと“2〜3秒”という一瞬のうちに砂型へ流し込みます。高温の金属を素早く流し入れ、隅々まで行き渡らせるため、スピード・温度・角度のどれもが重要。少しでも遅れると金属が途中で固まってしまうため、まさに秒単位の勝負です。
鋳造が終わると、常温で2時間冷却。しっかり固まったタイミングで砂型から取り出し、振動を加えながら崩していきます。砂型はここで役目を終えるため、1つの蛇口ごとに新しい型が必要になるのも特徴です。
その後、鉄の細かい粒を全方向から吹き付けて、表面についた砂や汚れを落とす“ショットブラスト”と呼ばれる工程へ。これにより、表面がきれいになり、次の加工がしやすい状態になります。
見えない工夫が詰まった表面加工 美しさと使いやすさの両立
蛇口は一見するとつるりとした金属ですが、実は細かな溝や凹凸が刻まれています。
この加工は、単に見映えを良くするための装飾ではなく、汚れがつきにくくキレイが続くようにするための実用的な工夫。光の反射を整えたり、素材の質感を柔らかく見せたり、耐久性を高める目的もあります。
また、もし傷が内側まで入ってしまっている場合は、そのまま使わずに再び溶かしてリサイクル。無理に使わず、品質を第一に考えた判断が徹底しています。
コーティングで美しく強く 蛇口の光沢はここで生まれる
検査を通過した本体は、表面に合金の膜をコーティングする工程へ。これこそが、家庭でよく見る“ピカッとした蛇口”を生み出す秘密です。
このコーティングによって、耐食性・耐久性が大幅にアップし、長年使ってもサビや腐食が起きにくくなります。美しさを保つためにも欠かせない大事な工程です。
全長120mの組み立てライン 50以上の部品を手作業で組み上げる
蛇口はシンプルに見えて、実は非常に複雑。
内部には50を超える部品が組み込まれていて、それぞれが役割を持っています。
工場の組み立てスペースは、なんと120mにも及ぶ長いライン。作業員が部品を1つずつ手で組み込みながら進んでいく姿が映し出され、番組を見ているこちらも思わず息をのむほどの細かい作業でした。
手作業だからこそ、機械では気づけない微妙なズレや締まり具合を調整でき、蛇口ごとの個体差を抑えることが可能になります。見た目は小さな製品ですが、内部はまるで精密機械のような構造です。
“絶対に漏らさない”を保証する最終チェック
最後の工程は、蛇口に空気を注入して漏れがないかを確認する検査。
もしどこかに小さな隙間があれば、空気が漏れて気泡となって現れます。工場では、この検査を徹底することで“水漏れゼロ”を目指しており、家庭で安心して使える蛇口が生まれるのは、この細かいチェックあってこそです。
水が逆流しない理由も番組で紹介
蛇口を閉めたときに水が逆流しない仕組みも、番組で分かりやすく説明されていました。
蛇口内部には、水圧に負けないように設計された構造があり、閉めるときの力の方向と水の圧力がちょうど良くぶつかることで、逆流を防いでいます。普段当たり前にしている“ひねる”という動作の裏に、こうした力学のバランスがあることが改めて分かります。
関市の金物技術が支える、日本の“水まわりの安心”
今回の探検で強く感じたのは、蛇口1つが完成するまでにどれだけの人の技術と作業が必要なのかということ。
関市の長い金物の歴史、砂型の柔軟さ、1200℃の鋳造、細やかな表面加工、手作業での組み立て、徹底したチェック。
これら全てが組み合わさって、家庭の水まわりを支える“当たり前の安心”が生まれています。
番組の最後、エンディングでは出演者の3人が工場の技術力に驚きながら、「蛇口を見る目が変わる」と語っていましたが、それはまさに視聴者も同じ気持ちになれる内容でした。
まとめ
『探検ファクトリー』2025年11月15日放送回では、岐阜県関市の蛇口工場をとても丁寧に紹介していました。
砂型づくり、1200℃の青銅流し込み、2時間冷却、鉄粒による洗浄、細かな溝加工、コーティング、120mの組み立てライン、50以上の部品、空気による漏れチェック、水が逆流しない理由──。
当たり前のように使っている蛇口が、これだけの技術の積み重ねで成り立っていることを知ると、毎日の水の時間が少し豊かに感じられます。生活の中の“普通”を支えるものには、必ず職人たちの知恵と努力があります。
家の蛇口をひねる瞬間に、今日のこの工場の姿を少し思い出してみると、いつもの水がほんの少し特別に感じられるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


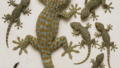
コメント