子どもの楽しみ・給食ジャムの秘密を探る!
探検ファクトリーの今回のテーマは「給食用ジャム」。子どもたちが毎日楽しみにしているあの小さなパックの中に、どれほどの工夫と気配りが詰まっているのか。すっちーさんと中川家の礼二さん・剛さんが、福岡県みやま市のジャム工場を訪ねてその秘密に迫りました。
ジャムの種類はなんと26種類も!
このジャム工場では、子どもたちの給食に使われるフルーツジャムを中心に、全部で26種類ものジャムを作っています。中でもフルーツジャムは19種類と種類が豊富で、他にもチョコレートジャムなどのお楽しみ系も加わっています。それぞれの味には、長年の研究と改良が込められているのが特徴です。
イチゴミックスジャムにはリンゴが入っている
中でも印象的なのは、イチゴミックスジャムにリンゴが使われているという事実です。一見、イチゴだけの甘い味と思われがちですが、実は裏側にはしっかりとした理由があります。1950年代、イチゴはまだ高級品で、学校給食でたっぷり使うには難しい時代でした。そこで登場したのがリンゴです。リンゴは安くて手に入りやすく、色や香りも控えめなのでイチゴと混ぜても味のバランスが崩れにくいのです。
現在では、味の安定性やコスト面、食感の良さを保つためにもこの組み合わせは引き継がれていて、イチゴの風味を生かしながらも、リンゴのやさしい甘さととろみが全体を引き立てる形になっています。こうした工夫のおかげで、子どもたちは毎回おいしいジャムを楽しむことができるのです。
また、イチゴミックスのほかにも、季節ごとにフルーツの出来に応じて配合や糖度を調整しているため、同じ種類でも時期によって微妙に風味が異なります。工場では一つひとつの味に対して細かいこだわりを持ち、手間をかけて作られていることがわかります。ジャムはただの甘いソースではなく、食材の選び方や背景にもたくさんのストーリーが詰まっています。
安心・安全な工夫がいっぱいの製造現場
ジャム工場では、見た目も味もおいしいジャムを作るために、安全と品質の両方に気を配った作業が行われています。使用されているイチゴは、色味の美しさを重視してエジプト産のものが選ばれています。国産のイチゴよりも赤みが強く、見た目の鮮やかさが求められる給食ジャムにぴったりなのだそうです。
保存料を使わずに守る品質
イチゴは仕入れた段階から砂糖に漬けた状態で保管されています。これは雑菌の繁殖をおさえるための工夫で、保存料を使わずに長持ちさせることができます。砂糖には水分を引き寄せる性質があり、菌が増えるのを自然に防ぐ効果があります。そうすることで、子どもたちにも安心して食べてもらえる品質を保つことができるのです。
煮込みと糖度測定のこまやかな工程
イチゴは細かく砕かれ、ペースト状になるまで加工されてから約90℃の高温で1時間じっくりと煮込まれます。この加熱工程で雑菌をしっかりと減らし、なめらかな仕上がりになるようにしています。果物は季節によって甘さにばらつきがあるため、その都度糖度を測定し、味のバランスを丁寧に調整しています。こうした細やかなチェックがあるからこそ、いつ食べても安定した味になるのです。
密閉パイプと最終チェックで異物対策
製造中に異物が混ざることのないように、ジャムは密封されたパイプを通って次の工程へ運ばれます。空気に触れない設計になっているので、衛生面でも非常に優れています。さらに、最後の仕上げでは、ジャムを薄くゆっくりと流しながら、人の目で焦げや不純物を一つひとつ確認しています。機械だけに頼らず、目視によるチェックを欠かさないことで、安心して食べられるジャムが完成します。
こうして、見た目も味もばっちりな給食ジャムは、たくさんの人の手と工夫で作られているのです。何気なく食べているその一口の奥には、細やかな安全対策と長年の知恵が詰まっています。
ジャムづくりのこだわりを表にまとめると
ジャム工場では、毎日子どもたちが安心しておいしく食べられるように、さまざまな工夫がされています。その主なポイントを、わかりやすく表にまとめました。
| 工夫のポイント | 内容 |
|---|---|
| フルーツの種類 | フルーツ系だけで19種あり、チョコレートなども含めると全部で26種 |
| 甘さの調整 | 収穫時期によって変わる果物の糖度を毎回測定し、状態に合わせて調整 |
| 異物混入対策 | 密封されたパイプでジャムを運び、人の目で丁寧に不純物や焦げを確認 |
| 保存方法 | イチゴを砂糖に漬けて、保存料なしでも長く保てるよう工夫 |
| 使用しているイチゴ | エジプト産を使用。色が鮮やかで見た目もおいしそうな仕上がりになるため |
こうした一つ一つのこだわりが、ジャムの品質を支えています。目には見えにくい部分にも丁寧な配慮が詰まっているからこそ、毎日の給食で変わらぬおいしさが楽しめるのです。
とろみの秘密とサイズ変更の理由
ジャム工場では、できたてのジャムを急速冷却する工程があります。熱々の状態からすばやく冷やすことで、ジャムに自然なとろみが生まれます。このとろみは、パンに塗ったときにちょうどよく広がるなめらかさに関係しており、食感や口あたりを決める大切なポイントになっています。
サイズが15gに小さくなった理由
今の給食ジャムは1個15gほどの個包装になっていますが、昔はもっと量が多かったそうです。その理由は、当時のコッペパンが今よりも大きかったためです。しかし、時代とともにパンのサイズが少しずつ小さくなったことで、ジャムの量も見直されました。パンとのバランスを考えて、ちょうどよい量に調整されているのです。
個包装のはじまりとその背景
1950年代までは、バケツのような大きな容器に入ったジャムを、給食当番や先生がスプーンで配っていた時代でした。そのため、どうしても量のばらつきや衛生面での心配がありました。この様子を見た創業者が「誰にでも同じように、きれいに配れる方法」を考え、個包装タイプのジャムを開発しました。これが現在のスタイルにつながっており、今では公平性と衛生面の両立をかなえた重要な工夫として受け継がれています。
こうした変化の裏には、食べる人の立場を考えた小さな工夫と改善の積み重ねがあるのです。どの工程も、子どもたちが安心しておいしく食べられることを一番に考えて作られています。
工場のある地域と今後の取り組み
福岡県みやま市にあるこのジャム工場では、今も次々に新しい商品が生み出されています。また、埼玉県幸手市に本社を構える大塚栄幸(えいこう)さんが創業者として紹介されました。
今回の探検で明らかになったのは、子どもたちのための小さなジャム1個に、たくさんの気づかいや工夫が込められていること。給食で何気なく食べていたあの味が、きっと特別に感じられるようになりますね。
出典:NHK総合「探検ファクトリー」2025年7月19日放送回
https://www.nhk.jp/p/tanken-factory/
昔の給食ジャム事情 年代別比較

ここからは、私からの提案です。今では当たり前となっている個包装の給食ジャムも、時代とともに形を変えてきました。ここでは1950年代からの変化を、年代ごとに分けて詳しく紹介します。
1950年代頃:大鍋からの手分けジャム
この時代の学校給食は、コッペパンと脱脂粉乳が主流でした。ジャムは大きな缶や鍋に入った業務用サイズが使われ、先生や給食当番がスプーンで取り分けて配るスタイルでした。個包装という概念はなく、みんなで分けるのが当たり前。衛生面での工夫はまだ少なく、容器も繰り返し使われるものが多かったです。
1960〜70年代:洋風化とパン食の広がり
給食が少しずつ洋風に変わり始めたこの頃、パンに加えてソフトめんや揚げパンなどが登場します。ジャムは引き続き業務用サイズで、まだ個包装は一般的ではありませんでした。食のバリエーションが増えた分、ジャムの役割もパンのおともから「お楽しみ」に近い位置づけへと変化していきました。
1980〜90年代:米飯導入と衛生重視の時代
この時期から学校給食に米飯が加わるようになり、和洋のバランスが取られるようになります。それと同時に衛生意識も高まり、個包装ジャムが一部の地域で導入され始めました。容器も進化し、衛生面や公平さを考慮した小分けのパッケージが増えていきます。また、牛乳も国産に切り替わるなど、安心・安全への配慮が見られるようになりました。
2000年代以降:個包装ジャムの標準化と技術の進歩
現在の給食では、個包装のジャムがほぼ標準になりました。製造工程も大きく進化し、ジャムは急速冷却によってとろみを生み出し、糖度の測定によって味が安定しています。また、パンのサイズが小さくなったことに合わせてジャムの量も調整されるなど、食べる側に合わせた工夫がされています。味・安全性・使いやすさのバランスが取れた今のスタイルは、長年の試行錯誤の結果といえるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


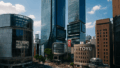
コメント