顔の見分け方が変わる『平均顔』の世界へようこそ
このページでは『実証科学バラエティー 百聞はジッケンに如(し)かず(4)顔を見分ける“平均顔”の秘密(2025年11月26日放送)』の内容を分かりやすくまとめています。
人はなぜ一瞬で相手の顔が分かるのか。子どもと大人で何が違うのか。写真加工が当たり前になった今、顔の見え方はどう変わっているのか。番組で行われたすべての実験と専門家の解説をもとに、顔認識のしくみを深く掘り下げていきます。
NHK【百聞はジッケンにしかず】無意識の決断のワナ!あなたの“選択”は誰のもの?|2025年6月7日放送
人はなぜ顔を見分けられるのか 平均顔という脳の仕組み
番組の軸となったのが 『平均顔』 という考え方です。
人は顔を見るたびに、その顔を写真のように一つひとつ保存しているわけではありません。
私たちは日々出会う 多くの顔の情報 を、知らないうちに頭の中で重ね合わせています。
目の位置、鼻の形、輪郭のバランス、表情のくせなどを少しずつ蓄積し、
「この人たちらしい顔」という 基準となる顔のイメージ を作り上げています。
それが 平均顔 です。
新しい顔を見たとき、脳はまずこの 平均顔 を物差しとして使います。
そして
「目が少し大きい」
「輪郭が細い」
「口元に特徴がある」
といった 平均からのズレ を一瞬で見つけ出します。
この ズレの組み合わせ こそが、その人らしさになります。
平均顔との差が分かるからこそ、
私たちは短い時間でも 大勢の顔を見分ける ことができるのです。
スタジオに登場した平均顔研究の専門家 山口真美教授 は、
平均顔についてさらに踏み込んだ説明をしました。
平均顔は 人それぞれ違う ものですが、
日本人同士を比べると かなり似通う傾向 があるといいます。
これは、生まれ育った環境や、日常で目にする顔が似ているためです。
つまり、
同じ社会
同じ文化
同じ生活圏
で暮らしているほど、頭の中に作られる 平均顔も近づいていく のです。
平均顔は生まれつき完成しているものではありません。
人と出会い、顔を見て、関わり続ける中で、
少しずつ更新され、育っていく 生きた基準 だといえます。
この見えない仕組みがあるからこそ、
私たちは日常の中で自然に人を見分け、
安心して社会の中で関係を築くことができているのです。
子どもの成長で変わる顔認識 小学生と中学生の実験
番組では、顔認識が成長とともにどう変わるのか を確かめるため、
子どもたちによる実験 が行われました。
まず挑戦したのは、小学3年生10人 です。
テーマは 70代男性の顔を見分けられるか というものでした。
実験の流れはとてもシンプルです。
最初に 1人の70代男性の顔写真の映像 を見ます。
その後、30人分の顔写真 が並び、その中から
「さっき映っていた人」を選びます。
結果は、
平均で9.3人を選択
そのうち 正解は6.8人 でした。
実験が行われたのは 東京都板橋区 にある 淑徳小学校 です。
子どもたちは真剣な表情で写真を見比べていましたが、
自信を持って絞り込む様子はあまり見られませんでした。
この結果について、平均顔研究の専門家である
山口真美教授 は、
次のように説明しました。
子どもにとって 高齢者の顔は日常で接する機会が少ない ため、
頭の中にある 平均顔がまだ十分に作られていない というのです。
つまり、
自分の周りにいる
家族
先生
友だち
といった顔は区別できても、
あまり見慣れていない年代の顔 になると、
平均顔がうまく機能せず、見分けにくくなります。
次に行われたのが、中学2年生10人 による同じ実験です。
条件は小学生とまったく同じでした。
その結果、
平均で10人を選択
正解は8人 となりました。
小学生よりも 正確さが高く、
選ぶ人数にも 大きな迷いが少ない のが特徴でした。
この違いについて 山口真美教授 は、
小学生と中学生では 顔の見方そのものが変わってくる と話しました。
小学生は
「目」
「鼻」
「口」
といった 部分ごとの特徴 に注目しがちですが、
中学生になると
顔全体のバランス
配置や雰囲気
をひとつのまとまりとして捉えられるようになります。
その結果、
頭の中の 平均顔がより安定し、
見慣れない顔でも 判断の精度が上がっていく のです。
この実験は、
顔を見分ける力は生まれつき完成しているものではなく、
成長と経験の積み重ねによって
少しずつ育っていく力であることを、
はっきりと示していました。
見慣れない顔でも区別できる理由 国や特徴の違い
次に行われたのが、南米出身のサンバダンサー を使った実験です。
スタジオには実際のダンサーが登場し、途中で VTRに映っていた人物と入れ替わった一人 を見抜けるかが試されました。
一見すると、
文化も
国籍も
雰囲気も
大きく違う顔ばかりです。
しかし結果は、
スタジオメンバー全員が正解 という意外な展開になりました。
では、なぜ 見慣れないはずの顔 を正確に区別できたのでしょうか。
この点について、平均顔研究の専門家である
山口真美教授 は、
とても重要な仕組みを説明しました。
人の頭の中には 平均顔 があり、
そこから 大きく外れた特徴 は、
自然と 強調されて見える というのです。
たとえば
肌の色
表情の動き
体全体の雰囲気
顔立ちのメリハリ
といった要素は、
平均からのズレが大きいほど印象に残りやすくなります。
そのため、短い時間しか見ていなくても、
「あの人はここが違う」という情報が
記憶にしっかり刻まれる のです。
番組ではこの説明を分かりやすくするために、
『スター・ウォーズ』のキャラクターが例として紹介されました。
登場人物たちは、
目
鼻
輪郭
全体のバランス
が極端にデザインされています。
だからこそ、
一度見ただけでも
「このキャラクターだ」と
すぐに思い出すことができます。
この例から分かるのは、
平均顔は固定された一つの顔ではない ということです。
見る相手
場面
文化
経験
によって、
頭の中で使われる 平均顔は柔軟に切り替わっています。
見慣れない顔であっても、
平均からのズレを手がかりにすることで、
人はしっかりと 個人を見分けることができる。
このサンバダンサーの実験は、
平均顔が 状況に応じて働く、とても柔らかな仕組み であることを、
はっきりと示していました。
写真加工が平均顔に与える影響 現代の顔認識の変化
番組後半では、写真加工が当たり前になった現代 ならではの
顔の見え方の変化 が取り上げられました。
顔認知心理を研究している 杉森絵里子准教授 によると、
加工された顔を日常的に見ている人 と
ほとんど見ていない人 では、
魅力的だと感じる顔の基準そのものが変わる可能性 があるといいます。
つまり、
「どんな顔が自然に見えるか」
「どんな顔がその人らしいと感じるか」
は、
育ってきた視覚環境 によって左右されるということです。
この考えを確かめるために行われたのが、
小学3年生の2人組 による実験でした。
2人には、友だちの顔写真が提示されます。
用意されたのは
無加工の写真 1枚
特徴を強調した写真
特徴を薄くした写真
を加工の度合いを変えて並べた 計6枚 です。
その中から
「本当の写真」
つまり 無加工写真 を選んでもらいます。
参考として紹介されたのが、シカゴ大学 の先行研究です。
この研究では、多くの人が
平均顔に近づけた写真
つまり、特徴をやや薄めた写真を
「本物らしい」と選ぶ傾向が示されていました。
ところが、今回の実験結果は
はっきり二つに分かれました。
1人は
平均顔に近い写真 を選び、
もう1人は
特徴を最も強調した写真 を選んだのです。
この意外な結果について、
平均顔研究の専門家である
山口真美教授 は、
とても現代的な見方を示しました。
写真加工に 日常的に慣れているからこそ、
平均に近い顔よりも
特徴がはっきりした顔の方が「その人らしい」
と感じた可能性がある、というのです。
つまり、
これまで
「平均顔=自然」
とされてきた基準が、
写真加工の普及によって
少しずつ書き換えられている可能性 が見えてきた、
ということになります。
写真加工は、
単に見た目を変えるだけではなく、
私たちの頭の中にある 平均顔そのもの に
静かに影響を与え始めているのかもしれません。
この実験は、
顔の見え方は時代とともに変わる という事実を、
とても分かりやすく示していました。
平均顔が示す 人と社会をつなぐ見えない力
番組の最後に語られたのは、平均顔が持つ社会的な意味 でした。
顔を見分ける力は、単に
「記憶力がいい」
「目がいい」
といった 視覚の能力だけの話ではありません。
人は顔を覚えることで
相手を認識し
安心し
関係を築き
社会の中で つながり続ける ことができます。
つまり、顔を見分ける力は
人と人が共に生きるための土台 でもあるのです。
番組の中で 濱田岳 は、
「平均顔を高めることは、社会とのつながりを持つきっかけになるかもしれない」
とコメントしました。
この言葉が示しているのは、
平均顔は
机の上で作られる理論ではない
ということです。
平均顔は、
日々人と出会い
顔を見て
言葉を交わし
同じ時間を過ごす中で
少しずつ育っていきます。
家族
友だち
学校
職場
街ですれ違う人
そうした 一つひとつの経験 が積み重なり、
頭の中の平均顔は更新されていきます。
その積み重ねがあるからこそ、
私たちは
相手の表情の変化に気づき
「いつもと違う」と感じ
相手の気持ちを想像することができます。
平均顔は
他者を理解するための基準 であり、
社会に溶け込むための感覚 でもあるのです。
今回の放送は、
顔を見るという
一見すると何気ない行為の裏に、
脳の学習 と
社会経験の積み重ね が
深く関わっていることを教えてくれました。
私たちが
「この人だと分かる」
「見覚えがあると感じる」
その一瞬の中には、
これまでの人生で出会った
無数の顔の記憶 が、
静かに
しかし確かに
支えとして存在しています。
平均顔とは、
人が社会の中で生きてきた
時間そのものが作り出した記憶
なのかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


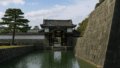
コメント