【実証科学バラエティー 百聞はジッケンに如かず】外見の変化で人はどこまで変わる?
2025年2月5日に放送されたNHK総合【実証科学バラエティー 百聞はジッケンに如かず】では、「人は外見によってどれほど変わるのか?」というテーマのもと、科学的な実験を通じて人間の行動や心理がどのように変化するのかが検証されました。
この番組は、日常の何気ない疑問を科学の視点から解き明かす実験バラエティで、今回が2回目の放送。出演者は濱田岳さん、ホラン千秋さんで、東京大学大学院の鳴海拓志准教授が監修を担当しました。
実験では、「体力」「内面」「知力」に対する外見の影響が検証され、それぞれの場面で興味深い結果が得られました。普段何気なく感じている「見た目の印象」が、実際の行動や能力にどのような影響を与えるのか、科学的な視点から詳しく探りました。
外見によって体力は変化する?消防士の姿で筋力アップ
小学3年生28名を対象に、「外見の変化が体力にどのような影響を与えるのか?」を検証する実験が行われました。人は外見の変化によって、実際の筋力や運動能力が変わるのか、科学的な検証を通じて明らかになりました。
【実験の概要】
児童を握力や背筋力が均等になるように2つのチーム(Aチーム・Bチーム)に分け、綱引き対決を実施。その後、Aチームに消防士の制服を着せ、再び綱引きを行うことで、外見の変化が運動能力に及ぼす影響を測定しました。
【実験の流れ】
- Aチーム vs Bチームで綱引きを3本勝負
→ 体力は均等なはずなのに、Bチームが3連勝し、Aチームは完敗 - Aチームに消防士の制服を着せ、消防士の活躍映像を見せる
→ 自分が消防士になったという気分に浸る - Aチーム vs Bチームで再び綱引きを3本勝負
→ これまで勝てなかったAチームが1回勝利
【実験結果のポイント】
- 消防士の制服を着たことで「自分が強くなった」と錯覚し、積極的に挑戦できた
- 綱引きの結果だけでなく、実際の筋力測定でも握力・背筋力が向上
- 「外見の変化」が自己認識を変え、体力やパフォーマンス向上につながることが科学的に示された
【なぜ制服を着るだけで筋力が上がるのか?】
- イメージの力が自己暗示につながる
→ 制服を着ることで「消防士のように強くなれる」という気持ちになり、自然と力を発揮 - 自信が高まることで、実際のパフォーマンスが向上
→ 「自分は強い」と思うことで、筋力をより効果的に使える - 「役になりきる」ことで、身体能力が引き出される
→ スポーツ選手が試合前にユニフォームを着ると集中力が上がるのと同じ効果
【外見の影響はスポーツや仕事にも応用可能?】
この実験から分かるのは、「外見の変化によって自信が高まり、実際のパフォーマンスが向上する」ということ。これはスポーツや仕事の場面でも応用できる可能性があります。
- スポーツ選手が試合前に「勝負ユニフォーム」を着ると気持ちが引き締まる
- 面接やプレゼンでスーツを着ると自信が増す
- 制服を着ることで役割意識が芽生え、仕事の集中力が高まる
この実験は、見た目の変化が自己認識を左右し、体力や行動にまで影響を与えることを明らかにしました。つまり、「なりたい自分」を演じることで、実際の能力が向上する可能性があるのです。
外見によって内面も変化する?助け合い精神が高まる
続いて行われたのは、「外見が人の内面や行動にどのような影響を与えるのか?」を検証する実験です。単に外見が変わるだけで、人の心や行動が変わるのかを科学的に検証しました。
この実験では、小学3年生28名を対象に、消防士の制服を着たグループ(14人)と、通常の体操着を着たグループ(14人)に分け、それぞれの「利他的な行動の変化」を観察しました。
【実験の流れ】
- 児童を消防士の格好をしたグループ(14人)と、体操着のグループ(14人)に分ける
- 事前にどちらのグループに入るかはランダムに決定
- 児童たちは、実験の目的を知らずに参加
- 個別に部屋へ案内し、スタッフがペン立てをわざと落とす
- ペン立てが床に転がり、明らかに「拾うべき状況」を作る
- 児童はスタッフの指示なしで行動する
- どの児童がペンを拾うかを観察する
- 児童の行動を記録し、どちらのグループがより助け合い精神を発揮するかを検証
【実験結果】
- 体操着のグループでは、14人中1人だけがペンを拾う
→ ほとんどの児童は、ペンが落ちたことに気づいても無反応だった - 消防士の制服を着たグループでは、14人中5人がペンを拾う
→ 消防士の格好をしていることで、「助けるべきだ」という意識が自然と高まった
【なぜ外見が行動に影響を与えるのか?】
この結果から、「制服を着ることで、助け合い精神や責任感が高まる」ことが示唆されました。なぜ外見の変化だけで行動が変わるのか、いくつかの心理的要因が考えられます。
- 役割意識が芽生える
- 制服を着ることで、「消防士になった」という感覚が生まれる
- 自然と「困っている人を助けるべきだ」と考えるようになる
- 周囲の期待を意識する
- 消防士の格好をしていると、「助けるのが当たり前」という意識が生まれやすい
- 「周りから見られている」という意識が行動に影響を与える
- 助け合いの行動が促進される
- 「制服を着た=ヒーローになった」と思うことで、積極的に行動を起こす
- 特に子どもは「なりきる」ことで、普段よりも前向きな行動を取りやすい
【この研究が示す重要なポイント】
- 制服や服装の変化が、行動や意識に大きな影響を与える
- 消防士のような「助ける職業」の格好をするだけで、実際に助け合いの行動が増える
- 子どもだけでなく、大人にも「制服が行動に与える影響」がある可能性が高い
この研究結果は、学校や企業の制服の意味を考え直すきっかけにもなります。例えば、医療従事者が白衣を着ることで「患者を救う責任感」を持つ、警察官が制服を着ることで「市民を守る意識」が高まるなど、職業ごとの制服が果たす心理的効果が改めて示されたと言えます。
また、日常生活でも「仕事着」「勝負服」「フォーマルな場でのスーツ」など、服装によって気持ちが変わる経験をしたことがある人も多いはずです。この実験結果は、そうした「服装の心理的な影響」を科学的に裏付けるものと言えるでしょう。
外見によって知力も変化する?棋士になりきると将棋の実力アップ
将棋教室に通う男性3人を対象に、「外見の変化が知力にどれほど影響を与えるのか?」を検証する実験が行われました。将棋のように高い集中力と戦略的思考が求められる場面で、「外見の変化」がどのような影響を及ぼすのかを調査しました。
【実験の流れ】
- 普段の状態でAIと対局し、実力を測定
- 3人の現在の実力を把握するため、AIと対戦
- AIの強さは、それぞれの段位よりも2ランク上に設定
- 棋士の着物を着用し、実際の対局会場に近い環境で再挑戦
- 参加者それぞれが憧れる棋士の着物を着用
- 対局場の雰囲気を再現した部屋で、よりリアルな環境を構築
- 棋士が実際に食べる「勝負めし」を食べる
- 将棋会館特製チキンカレーや骨付き鶏もも肉のガーリックローストなど、棋士が対局時に食べる食事を提供
- これにより「プロ棋士になった気分」をさらに高める
- 再びAIと対局し、思考力や判断力の変化を測定
- 環境の変化が実際のパフォーマンスにどのように影響するかを比較
【結果のポイント】
- 1人はAIに対する「最善手の割合」が向上
- 通常の対局ではミスが多かったが、着物を着て対局すると精度が向上
- 「棋士になった」という意識が集中力を高めた可能性が高い
- もう1人は、格上のAIに勝利する快挙を達成
- 事前の解析では勝率が低いと予想されていたが、実験後の対局ではAIを撃破
- 棋士の振る舞いや環境が、直感や思考力の向上につながったと考えられる
【なぜ「なりきる」ことで知的パフォーマンスが向上するのか?】
この結果から、「外見の変化が自己認識を変え、知的パフォーマンスを向上させる」ことが明らかになりました。
考えられる要因は以下の通りです。
- 「プロ棋士になった気分」が集中力を高める
- 着物を着ることで、「自分はプロ棋士だ」という心理的なスイッチが入る
- これにより、普段よりも集中力や思考力が高まる
- 「憧れの棋士に近づく」という意識が自己効力感を向上させる
- 憧れの棋士と同じ服装をすることで、「自分も強くなれる」という感覚が生まれる
- これが「自己効力感(自分ならできるという感覚)」を高め、パフォーマンスを向上させる
- 「環境の再現」が本番の臨場感を生む
- 実際の対局場に近い空間で戦うことで、気分が高まり、冷静な判断がしやすくなる
- これにより、普段以上の力を発揮できた可能性がある
- 「勝負めし」がメンタルを整える
- 棋士が実際に食べる食事を摂ることで、対局への意識がさらに高まる
- 「この食事を食べたから勝てる」という心理的効果が、冷静な思考につながる
【この実験が示す重要なポイント】
- 外見を変えることで、知的なパフォーマンスも向上する可能性がある
- 「なりきる」ことで、普段よりも集中力や判断力が高まる
- 環境や食事など、細かい要素を整えることで、さらに能力を引き出せる
この研究は、勉強や仕事などのシーンでも応用できる可能性があります。例えば、試験勉強の際に「スーツを着て取り組む」「本番の会場と似た環境で学習する」ことで、より良い結果を出せるかもしれません。
「なりきる」ことで人のパフォーマンスは向上する。この実験は、そうした心理的効果を科学的に証明した貴重な結果と言えるでしょう。
外見の変化が影響を与えやすい人とは?
監修を担当した東京大学大学院の鳴海拓志准教授によると、「自尊心の低い人ほど、外見の変化による影響を受けやすい」とされています。これは、外見が変わることで「なりきる」効果が生まれ、行動やパフォーマンスに大きな影響を与えるためです。
【外見の変化が大きく影響する理由】
- 「なりきること」が自己暗示を強める
- 外見が変わることで、普段の自分とは違う意識が芽生える
- 例えば、消防士の服を着ると「強くなった気がする」、棋士の着物を着ると「冷静に考えられそう」といった感覚が生まれる
- 実験でも、消防士の制服を着た小学生が体力測定で高い数値を出す、棋士の格好をした人が将棋AIに勝つといった結果が得られた
- 「自分の能力を信じるきっかけ」になる
- 「自分はこんなことができるのかもしれない」という自己認識の変化が生まれる
- 例えば、棋士の着物を着た参加者が実際に対局スキルを向上させたのは、「棋士のように考えられる」と思い込めたから
- 仕事や勉強でも、「できる人の服装を真似する」ことで集中力が上がることがある
- 「新しい自分を発見する」ことができる
- 普段の自分では気づかなかった可能性に目を向けることができる
- 「いつもの自分」という固定観念を崩し、「なりたい自分」に近づくチャンスになる
- 例えば、「普段は消極的な性格だけど、スーツを着ると自信が持てる」という感覚も、外見の影響の一例
【実験が示す重要なポイント】
- 外見の変化は、体力や知力だけでなく「内面」も変える
- 「なりきる」ことで、自信がつき、実力以上のパフォーマンスを発揮できる
- 特に自己肯定感が低い人ほど、「外見の変化」がポジティブな影響を与えやすい
この研究は、日常生活にも応用できます。「やる気が出ないときに服装を変える」「なりたい自分を意識したスタイルを取り入れる」ことで、より良いパフォーマンスを発揮できる可能性があるのです。
「見た目が変わると、行動も変わる」。この実験は、その心理的メカニズムを科学的に証明する貴重な結果となりました。
まとめ
今回の【百聞はジッケンに如かず】では、「人は外見によってどれほど変わるのか?」について、科学的な実験を通じて明らかになりました。
- 体力向上:消防士の格好をすることで、筋力がアップした
- 助け合い精神の向上:消防士の制服を着た児童は、実際に優しい行動を取る確率が高まった
- 知力向上:棋士になりきることで、将棋の実力が向上した
- 影響を受けやすい人の特徴:自尊心の低い人ほど、ポジティブな変化を受け入れやすい
この結果から、「なりきることで能力が向上する」ことが科学的に証明されました。もし自信をつけたいなら、まずは見た目から変えてみるのも良い方法かもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

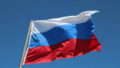

コメント