「ゲーム音楽スペシャル」
ゲーム音楽は「ただのBGM」ではなく、プレイヤーの体験を左右する大切な要素です。この記事では、2025年8月22日放送のNHK「ゲームゲノム」ゲーム音楽スペシャルの内容をわかりやすく整理しました。ファミコン時代から最新のインタラクティブ音楽まで、番組で紹介されたエピソードをすべて反映しています。ゲーム音楽の進化や名曲誕生の裏側を知りたい方におすすめです。
ファミコン時代の制約と試行錯誤
最初に取り上げられたのは、ファミリーコンピュータ(ファミコン)の時代です。当時のゲーム音楽は「同時に電子音3つまで」という厳しい制約の中で作られていました。作曲家の植松伸夫は、ファイナルファンタジーシリーズを手がける以前から、限られた音をどう活かすか頭を悩ませていたと語ります。例えば「ロックマン2 Dr.ワイリーの謎」のAIRMAN STAGEや、「ファイナルファンタジーIII」の名曲悠久の風などは、シンプルな電子音でありながら、今も強い印象を残しています。制約の中だからこそ、メロディに工夫を凝らし、短いフレーズでも耳に残る曲作りが行われたのです。これは多くのプレイヤーが「ゲーム音楽は口ずさめるメロディ」という記憶を持つ理由でもあります。
スーパーファミコンで広がった表現の幅
次に紹介されたのはスーパーファミコン時代。ここでは同時発音数が3つから8つに増え、音色もぐっと豊かになりました。これにより、楽曲は単調さから解放され、より厚みのあるサウンドが作れるようになります。植松伸夫が手がけた「ファイナルファンタジーV」のビッグブリッヂの死闘はその代表例です。壮大なスケール感とリズムの激しさで、多くのファンに「戦闘曲の名曲」として語り継がれています。また「ゼルダの伝説 神々のトライフォース」でも、冒険心をかき立てる音楽が加わり、ゲーム体験が一層豊かになったことが紹介されました。スーパーファミコンは、ゲーム音楽が単なるBGMから「物語を盛り上げる劇伴」へ進化した大きな転換点だったのです。
プレイステーションと「片翼の天使」の衝撃
ハードがさらに進化し、プレイステーションでは同時に24音まで使えるようになりました。この環境で生まれたのが「ファイナルファンタジーVII」の片翼の天使です。オーケストラとロックを融合させた楽曲で、ゲーム史に残る名曲として知られています。植松伸夫はイーゴリ・ストラヴィンスキーやジミ・ヘンドリックスなど音楽界の巨匠から影響を受けたと語り、クラシックと現代音楽の要素を大胆に組み合わせました。ボス戦で流れるこの曲は、プレイヤーに圧倒的な緊張感を与え、まるで映画のクライマックスにいるような体験を実現しました。ここからゲーム音楽は「映画や舞台に匹敵する芸術表現」として世界中に注目されるようになります。
インタラクティブミュージックの革新
番組では「プレイヤーに寄り添う音楽」も紹介されました。ファイナルファンタジーXVのロデオ de チョコボでは、プレイヤーの操作に合わせて音が変化する仕組みが組み込まれています。この技術はインタラクティブミュージックと呼ばれ、音楽が固定されたBGMではなく、プレイヤーと一緒に演奏されるような体験を提供します。解説を担当したのはサウンドプログラマーの岩本翔で、音楽とシステムの融合がいかに難しく、同時に魅力的な挑戦であるかが語られました。この技術は「パラッパラッパー」や「太鼓の達人」など音楽ゲームにも通じるもので、今後さらに発展が期待されています。
ゲームと音楽の極限融合「テトリス エフェクト」
そして番組は水口哲也が手がけたテトリス エフェクトを取り上げました。ここでは、パズルゲームでありながら、すべての操作が効果音やBGMとつながっており、プレイヤーはまるで即興演奏をしているかのような体験ができます。水口は「シナスタジア」という感覚に注目しています。これは視覚・聴覚・触覚が互いに刺激し合って生まれる感覚で、まるで音が見えるような体験を目指しているのです。番組では「Rez Infinite」や「スペースチャンネル5」など、水口の過去作も紹介され、音と映像が一体化する新しいゲームの形が提示されました。
クリエイターたちが語る「ゲーム音楽とは?」
番組の最後に、植松伸夫は「自分にとってゲーム音楽は、遊び足りないし学び足りない学生生活が続いているようなもの」と語りました。常に挑戦と発見を楽しみ、作り続ける姿勢が印象的でした。さらに岩本翔は「プレイヤーに寄り添う音楽の可能性」を、水口哲也は「音楽とゲームがアートとして融合する未来」をそれぞれ語り、ゲーム音楽が持つ力を改めて強調しました。番組ではファンタジーライフiやグルグルの竜と時をぬすむ少女など、多様な楽曲例も紹介され、音楽がどのようにプレイヤーの感情を支えているのかが示されました。
よくある質問
Q. ゲーム音楽がなぜ特別なの?
A. 制約や技術進化に合わせて作曲家が工夫を重ねた結果、ほかのメディアにはない独自の表現が生まれたからです。
Q. 番組で一番印象的だったエピソードは?
A. 「片翼の天使」誕生秘話です。従来の電子音楽を超え、世界中に衝撃を与えた楽曲の背景が紹介されました。
Q. 今後のゲーム音楽はどう進化する?
A. インタラクティブ性がさらに進み、プレイヤーの動きや感情に合わせて音楽がリアルタイムに変化する方向に発展すると考えられます。
まとめ
今回の「ゲームゲノム」ゲーム音楽スペシャルでは、ファミコン時代の3音制約から最新のシナスタジア的体験まで、ゲーム音楽がいかに進化してきたかが紹介されました。植松伸夫をはじめとする作曲家やプログラマーたちの試行錯誤と挑戦が、プレイヤーの心を動かす数々の名曲を生み出しました。ゲーム音楽は単なるBGMではなく、物語を深め、感情を揺さぶり、時には人生の一部となるほどの存在です。この記事を読んだ方はぜひお気に入りのゲーム音楽を改めて聴き直し、その進化の歴史を体感してみてください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

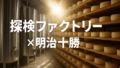

コメント