都市に息づく「恐れ」と「希望」|3か月でマスターする古代文明(2)メソポタミア
「都市の誕生」と聞くと、多くの人は豊かで洗練された暮らしを思い浮かべるでしょう。立派な神殿や市場、整然と並ぶ家々——まさに文明の象徴です。けれど、その始まりは決して夢や繁栄からではありませんでした。
今回の『3か月でマスターする古代文明』が注目するのは、人類が初めて「都市」という仕組みを作り出したメソポタミア文明。そしてその裏に隠された“都市は最終手段だった”という驚きの仮説です。
干ばつ、気候変動、争い。人々は脅威にさらされながらも、生き残るために一つの場所へと集まっていきました。都市は「進歩の証」ではなく、「生きるための避難所」だったかもしれません。この記事では、放送前の段階で見えてきた研究成果をもとに、北メソポタミアの新しい都市観を丁寧にひもときます。
【3か月でマスターする古代文明】[新]1衝撃!最古の巨大遺跡見直される文明の始まり──1万年前に祈りは生まれていた|2025年10月7日
「都市=進歩」ではなかった?北メソポタミアの新発見

従来、世界最古の都市は南メソポタミアのウルク(現在のイラク南部)だとされてきました。紀元前3500年ごろに神殿や行政施設をもつ都市国家が形成され、そこから文明が広がったと考えられていたのです。
しかし近年、北メソポタミア(シリア北部)での発掘が、この定説を揺るがせています。発見の中心は、テル・ブラク(Tell Brak)と呼ばれる遺跡。ここでは紀元前4200年ごろ、すでに“都市的な”集まりが存在していたことが分かってきました。
しかもその形成過程は南部とはまったく異なっていたのです。南では、ひとつの集落が内部から拡大して都市へと変化しましたが、北では複数の小集落が互いに寄り添うように集合し、安全を求めて合体する形で都市が生まれたと考えられています。
つまり、都市は繁栄を目指した結果ではなく、不安と危険に対する“防衛の知恵”から生まれた可能性があるのです。
テル・ブラクが語る「集合の都市」

テル・ブラク遺跡は、北シリアの肥沃なハブール盆地に位置しています。発掘調査では、中心の丘(テル)だけでなく、その周囲にも多くの住居跡が確認されました。これらは同時期に存在し、それぞれの集落が時間をかけて一つのまとまりを作っていったことがわかります。
興味深いのは、その空間構造です。「中心から広がる」ではなく、「外側から寄せ集まる」ように都市が形成されていった点。研究者のジェイソン・アー(Jason Ur)氏は、「テル・ブラクの都市化は権力による統合ではなく、共同防衛と共存の結果として起こった」と指摘しています。
さらに、遺跡内で見つかった「目の像(Eye idols)」と呼ばれる小さな石の偶像群は、人々が共通の信仰をもって集まっていたことを示すもの。宗教的儀礼が、恐怖を抑える“心の防御”として働いたとも考えられています。
ハモウカルが示す“自立した文明の形”
北メソポタミアにはもう一つ、ハモウカル(Hamoukar)という重要な遺跡があります。紀元前4500年ごろから人が住み、やがて黒曜石の加工工房や交易の痕跡が広がりました。
注目すべきは、この都市が南のウルク文化と接触する前からすでに発展していた点です。つまり、北部の都市は南部の影響で“都市化”したわけではなく、自らの環境と状況の中で独立して進化した可能性があるのです。
気候変動による乾燥化や資源不足、他集団との緊張関係といった背景が、人々を“安全な集合”へと導いた。そこに交易や工業生産の仕組みが生まれ、やがて都市へと変わっていったのです。
「安全のための集合」こそが都市の原型
では、人々はなぜあえて集まったのか。孤立して暮らせば、自由ではあるものの、外敵や飢餓、環境変動のリスクは大きくなります。
複数の集落が集まることで、食料を分け合い、防衛を強化し、子どもや高齢者を守る仕組みを作ることができました。こうして、都市は単なる居住地ではなく、**「安全保障のための共同体」**として機能するようになったのです。
防壁や見張り塔といった構造物がのちに登場するのも、この流れの延長線上にあります。最初の都市は城塞ではなく、“人が人を守るための距離感”から始まったと言えるでしょう。
都市が育む「希望」の始まり
恐れから始まった都市には、やがて希望が芽生えます。集まることで人と人のつながりが生まれ、文化や芸術、技術が発展していったのです。
テル・ブラクのような都市では、陶器や織物、金属製品の工房も確認されています。交易ネットワークを通じて南のウルク文化とも交流し、互いに影響を与え合う関係が形成されていきました。
集まることが生存のためだったとしても、そこで得られた知恵や技術が“希望”へと変わっていく。これこそが都市が持つ二面性の魅力です。
「恐れ」と「希望」が共に息づく都市の本質
都市は、人間の感情の鏡です。外敵への恐れ、飢えへの不安、孤立への恐怖。それらが人を集め、都市を作らせた。
けれど、同じ都市で人は笑い、祈り、祭りを楽しみ、芸術を生み出す。恐れと希望が混ざり合う場所こそ、都市の本当の姿です。
現代の大都市も、渋滞や格差といった不安を抱えながらも、文化と創造の中心として輝き続けています。都市の原点にある「恐れ」と「希望」は、いまも私たちの生活の中で息づいているのです。
まとめ:都市とは、恐れの果てに生まれた“希望のかたち”
この記事のポイントは次の3つです。
・北メソポタミアのテル・ブラクやハモウカルでは、紀元前4500年ごろから「安全のための集合」による都市化が進んでいた。
・都市は支配や進歩の結果ではなく、人類が脅威に立ち向かうための“選択”として誕生した。
・恐れを希望に変える人間の力こそが、文明の始まりであり、現代都市にも通じる。
放送では、関雄二氏(国立民族学博物館館長)と常木晃氏(筑波大学名誉教授)が、これらの発掘成果をもとに「都市の意味」を読み解きます。
都市は単なる建物の集まりではありません。そこには、人類が何を恐れ、何を望んできたのかという“心の歴史”が刻まれているのです。
出典・参考:
・国立民族学博物館
・筑波大学古代文明研究センター
・『Cambridge University Press』/『ScienceDirect』/『ArchaeOrient』研究論文
・Harvard Magazine「Jason Ur: The Archaeology of Urban Beginnings」
・Wikipedia「Tell Brak」「Hamoukar」
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

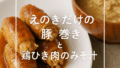
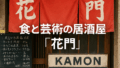
コメント