増える廃校、企業が目をつけた理由とは?
全国で増え続ける「廃校」。かつて子どもたちの笑い声が響いていた場所が、いま新たな役割を与えられています。「学校が企業の拠点になるなんて…」と驚く人も多いのではないでしょうか。この記事では、実際に全国で進む廃校の再利用の現状と、企業や地域が得ているメリットを紹介します。
NHK【新プロジェクトX】若狭のサバ缶が宇宙へ!廃校寸前の高校が世界初の快挙|2025年5月31日放送
教室がAIの頭脳に変わる!佐賀・玄海町のデータセンター化
佐賀県玄海町にある旧小学校では、まるで未来都市のような変化が起きています。かつて子どもたちが黒板に向かって学んでいた教室に、今は約120台のサーバーがずらりと並び、AI向けのデータセンターとして稼働中です。教室の広さはサーバー設置にちょうどよく、通信設備の設置も容易。校舎は鉄筋コンクリート造で安定しており、電力供給や空調システムの導入もしやすいという利点があります。
企業側の最大のメリットは「スピード」と「コスト」。土地の取得や新築の必要がなく、自治体から無償または格安で借りられるため、すぐに事業を始められます。しかも、空き教室が多いほどサーバーの拡張がしやすく、AI研究やクラウド運用にも柔軟に対応できます。玄海町では地元雇用の創出にもつながり、地域住民の期待も高まっています。かつての学び舎が、いまや最先端の情報処理拠点として再び地域を支えているのです。
岐阜・瑞浪市では「技術の展示場」として再生
岐阜県瑞浪市の旧中学校も、見事に生まれ変わった廃校のひとつです。校舎は電気自動車(EV)の部品展示場として再利用され、産業と教育をつなぐ新たな役割を担っています。広々とした理科室には精密機器やEVモーターが並び、体育館には試作車の展示ブースが設置されています。
展示場を訪れた企業関係者は「学校という懐かしい空間の中で、未来の技術を見る感覚が新鮮」と話します。この再利用によって、地元中小企業の技術が全国へ発信される場となり、修学旅行生や地元高校生の見学も増えています。廃校が単なる施設ではなく、教育・観光・産業を結びつける“ハブ”として再評価されているのです。
北海道から島根まで 地域の個性を生かした多彩な再利用
廃校の再利用は全国各地に広がっています。北海道では旧校舎をそのまま活かしたせんべい工場が稼働。元の家庭科室や理科室が製造ラインや研究スペースとして生まれ変わり、地元の特産品を使った「地域ブランドせんべい」の開発が進んでいます。
山梨県ではドローン開発の研究拠点が設立されました。体育館をテスト飛行スペースに改装し、旧コンピューター室を制御プログラムの開発室に。近隣の高校と連携し、学生がプログラミング体験を行うなど、教育とのつながりも生まれています。
さらに島根県では、旧小学校を利用したカワハギの陸上養殖が注目を集めています。理科室を利用した水槽設備が整い、海に面していない地域でも安定した漁業の実験ができるようになりました。これらの事例に共通するのは「地域資産の再利用」と「新しい産業の創出」。どれも地域が持つ特色を生かした挑戦です。
自治体にとっての課題とチャンス
廃校を抱える自治体にとって、課題は「維持費」と「解体費用」です。使わないままでは年間数百万円の維持費がかかり、建物が老朽化すれば取り壊すのにも多額の費用が必要になります。そのため、企業による活用は財政負担を軽くするだけでなく、地域経済にも良い循環をもたらします。
玄海町のようにデータセンターができれば、電気設備や通信環境の整備によって地元のインフラも向上します。瑞浪市のような展示場では観光客が訪れ、地域の飲食店や宿泊施設の売上アップにもつながります。こうした相乗効果は、過疎地の再生にとっても貴重なモデルケースになっています。
ただし、すべての廃校がすぐに企業利用できるわけではありません。耐震性や立地、アクセスの問題など、条件が合わない施設も多くあります。自治体は企業のニーズを聞き取りながら、どのように施設を魅力的に見せるかを工夫していく必要があります。
文部科学省の取り組みと今後の方向性
文部科学省は、全国の廃校情報を集約した「廃校活用データベース」を整備しています。このサイトでは、校舎の所在地や構造、利用可能面積などを公開し、企業やNPOが直接問い合わせできるようになっています。これにより、全国でのマッチングがスムーズに進むようになりました。
実際、文部科学省の最新調査では、企業による廃校利用はここ数年で着実に増加傾向にあります。特にIT、環境、食産業など、地域資源を生かす分野での活用が目立ちます。今後は「企業と自治体をつなぐ仕組みづくり」がさらに求められます。単なる貸出ではなく、地域の人材育成や観光振興と連動したプロジェクトとして広がることが理想です。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・全国で進む廃校の再利用は、AI・EV・食品など多分野に広がっている
・企業には「低コスト」「早期稼働」「拡張性」の利点があり、地域経済にも好影響を与える
・文部科学省による情報公開やマッチング支援で、今後さらに拡大が見込まれる
かつて地域の子どもたちが学び、思い出を刻んだ校舎が、いま再び地域の未来を支える場所へと変わりつつあります。黒板の前で夢を語った教室が、今度はAIの開発室になり、理科室が海のない町の養殖場になる――そんな“第二の人生”を歩む学校が全国で増えています。廃校は「終わり」ではなく、「新しい始まり」。地域と企業、そして人の知恵が交わる場所として、これからもその可能性は広がっていくでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


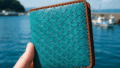
コメント