ストライク?ボール?AIが判定する新時代へ!大リーグが導入する「チャレンジ制度」とは
「今のはストライクだろ!」——そんな声がスタンドに響く瞬間、来季の大リーグでは“AI”が静かに答えを出します。2025年から本格運用される『ストライク・ボール自動判定チャレンジ制度』は、野球の歴史を変える大きな一歩。機械の目が人間の感覚にどう挑むのか、その仕組みと背景をやさしく解説します。
人とAIが協力して判定する「ハイブリッド方式」
大リーグが導入するのは『ABS(Automated Ball-Strike system)』と呼ばれる最新技術。複数の高性能カメラとセンサーがピッチャーの投球を正確に追跡し、ボールがストライクゾーンを通過したかどうかを自動で判断します。
しかし、すべてを機械任せにするわけではありません。あくまで最初の判定は人間の球審が行い、異議があった場合にだけAIの目が“裁定”を下すという仕組み。人間とAIの“ダブルチェック体制”で、これまで問題になってきた微妙な判定を補う形です。
この方式を採用する背景には、「野球の魅力である人間味を失いたくない」という意図もあります。完全自動化してしまうと、キャッチャーのフレーミング技術(捕球の見せ方でストライクを誘う技術)など、長年培われてきた戦術や駆け引きが無意味になる恐れがあるためです。AIはあくまでサポート役、人間の判断を尊重しつつ、公平性を高めるための手段として導入されます。
チャレンジ権は「1試合2回」成功すれば戻る!
各チームに与えられるチャレンジ権は基本2回。チャレンジを発動できるのはバッター・ピッチャー・キャッチャーの3人のみです。監督やコーチは関与できません。
たとえば、打者が「今の球はストライクじゃない!」と思った場合、判定の直後にヘルメットを軽くたたくなどの合図をしてチャレンジを宣言します。このとき、ベンチの指示を仰ぐことは禁止。プレーの流れを止めず、瞬時の判断が求められます。
AIによる判定で人間の球審の判定が覆れば、チャレンジは“成功”としてカウントされず、そのままチャレンジ権が維持されます。逆に、判定が覆らなければ1回分を失います。つまり、チャレンジをどこで使うかが非常に重要な戦術要素になります。
また、延長戦に入る場合、チャレンジ権が残っていないチームには追加の1回が与えられる案も検討されています。
判定は13秒で完了!AIのスピードと正確さ
チャレンジが発動されると、球場の大型スクリーンにその投球の映像とストライクゾーンが表示されます。観客の前で、AIが導き出した正確な軌道が示されるため、誰もが納得できる形で結果が共有されます。
システムは球審がコールした瞬間に同時にデータを処理しており、チャレンジが発動してから平均13.8秒で結論が出るといわれています。試合のテンポをほとんど損なわずに公平な結果が出せるのが最大の利点です。
オールスター戦ではすでに実験的に導入され、AIによる判定が人間の判断を覆す場面もありました。観客席では「おおー!」と歓声が上がり、審判も笑顔で判定を受け入れるなど、野球文化に新しい光景が生まれています。
なぜ完全自動化しないのか?AIにも課題あり
実は、大リーグでは一時期「全投球を自動で判定する方式」も検討されていました。しかし、試験運用の結果、いくつかの課題が見えてきたのです。
第一に、打者の姿勢や身長、ストライクゾーンの個人差をどこまでAIが正確に捉えられるかという問題。人間の球審は打者の構えを見てゾーンを微調整しますが、AIは数値化されたデータをもとにしか判断できません。
第二に、完全自動化すると「リズム」が変わる点。AIがすべてを管理することで試合テンポが硬くなり、観客が感じる“臨場感”が薄れるという指摘もありました。
そして第三に、キャッチャーのリード技術が無効化されてしまう懸念。捕手がどんなに巧みに構えても、AIは機械的にボールの通過点だけを見るため、職人技が生かせなくなるのです。
こうした課題を踏まえ、MLBは「まずは人間とAIの協働から」と方向転換。チャレンジ制度は、その“ちょうどいい距離感”を模索する試みなのです。
新しい戦術の誕生――「チャレンジの駆け引き」
チャレンジ制度が導入されることで、選手や監督の戦略にも変化が生まれます。たとえば、リードしている場面ではあえてチャレンジを温存し、試合終盤の1点を争う局面で使う。あるいは、流れを変えたい場面でチャレンジを敢行して相手のペースを崩す。
つまり、チャレンジのタイミングそのものが“戦術”になるのです。これにより、野球はさらに心理的な読み合いの要素が強くなります。AIが導入されても、人間の勘と判断力が勝負を左右する瞬間は残されているのです。
マイナーリーグでの成果と課題
すでに**トリプルA(3A)**では『ABS』のテスト運用が進められています。完全自動方式とチャレンジ方式の両方が実験され、選手の反応はおおむね好評。
チャレンジ制では「納得感がある」「テンポが良い」といった声が多く、平均試合時間もほぼ維持されています。一方で、「ゾーンが厳しすぎる」「打者の構えで判定が変わるのは不公平」という意見もあり、調整が続けられています。
2025年の春季トレーニングでは、AI判定の正確性・スピード・観客の受け入れ度を測るためのデータが集められました。これらをもとに、大リーグは2026年の正式導入を目指しています。
AI判定がもたらす未来――“納得できる野球”へ
これまで「誤審」は野球の一部とされてきました。時にはチームの運命を左右し、ドラマを生む要素でもありました。しかし、AI導入によって、選手・観客・審判すべてが“公平な結果”を共有できる未来が見え始めています。
AIの導入は、野球の本質を変えるものではなく、「誰もが納得できるプレー」を増やすための進化。人間が積み上げてきた経験と、機械が持つ正確さを融合させることで、野球はより奥深く、そして信頼できるスポーツへと進化しようとしています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・大リーグは『ABS(Automated Ball-Strike system)』を導入し、チャレンジ制で運用を開始する
・チャレンジは各チーム2回、成功すれば権利は維持。AIが13秒で正確に判定を返す
・完全自動化ではなくハイブリッド方式で、人間らしい野球の駆け引きを残している
AIがボールを見極め、人間が戦略を練る――その融合が、次世代の野球を形づくる時代が始まります。私たちが見る「ストライク!」の一言には、もうすぐ人間とAIの協力が詰まっているのです。
出典:
・MLB.com(https://www.mlb.com/news/automated-ball-strike-calls-mlb-spring-games)
・ウィキペディア「Automated Ball-Strike System」
・CBS Sports / FOX Sports / Reuters / AP News / capeandislands.org / kgou.org
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

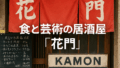
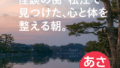
コメント