猛暑で異変!?私たちの食卓の未来は
2025年の夏、日本列島を覆ったのは過去に例を見ないほどの猛暑でした。35度を超える日が連続し、夜になっても気温が下がらない「熱帯夜」が続き、私たちの暮らしにも大きな影響を与えています。そんな中で特に深刻なのが、食卓を支える農業や畜産への影響です。今回の「クローズアップ現代」では、猛暑で揺らぐ食材供給の現場と、未来に向けた挑戦が紹介されました。この記事では、その内容をわかりやすく解説し、私たちが今後どのような備えをすべきかを考えます。
豚肉不足の現実
豚はもともと脂肪が多く、汗をかいて体温を下げることができません。そのため、猛暑は大きなストレスになります。茨城県つくば市や三重県伊賀市の養豚場では、送風機を増やしても効果が追いつかず、豚の成長が著しく遅れています。
ある養豚場では、毎週20頭を出荷していたところ、先月はわずか10頭しか市場に出せなかったといいます。しかも出荷できた豚も体重が10キロほど軽く、肉の量が減ってしまう事態に。さらに、昨年の残暑が影響し、繁殖用の母豚の妊娠率が下がり、生まれる子豚の数も減少。養豚農家にとっては、二重三重の打撃となっています。
農研機構の予測では、この傾向は今後10年でさらに広がり、九州や東北などこれまで比較的気候の安定していた地域にも波及していくと見られています。私たちが当たり前に食べてきたとんかつや豚しゃぶも、将来は「高級料理」となる可能性が否定できません。
酪農を襲う暑さと乳牛の限界
豚だけではありません。乳牛も猛暑で体力を奪われています。愛知県田原市の酪農家では、獣医師が毎日のように呼ばれ、暑さに苦しむ牛を診察しています。暑さで免疫力が落ちると、乳房炎にかかりやすくなり、乳量が大きく減少します。
また、高齢の乳牛が立てなくなり、そのまま衰弱してしまうケースも増えています。北海道を除くほぼ全国で、今後の平均気温上昇により生乳の生産量が10%以上減少するとの試算も発表されました。牛乳やバター、チーズといった乳製品の安定供給が難しくなれば、家庭の食卓から給食、外食産業まで幅広く影響が及びます。
コメの収穫量が激減する未来
温暖化が農作物にも大きな影響を与えています。農研機構が人工的に未来の環境を再現して行った実験によると、コシヒカリの収穫量は最大で4割減少。しかも半分近くが「未熟米」となり、食味が落ちてしまいました。粒が白く濁った米は市場価格も下がり、農家の収入減につながります。
米は日本人の主食であり、年間を通じて食卓に欠かせない存在です。その米が安定して収穫できなくなることは、国の食料安全保障に直結する問題でもあります。さらに、野菜でもトマトやレタスなどの夏野菜が暑さで収量を減らし、東京・大田市場では夏場の入荷量が減少。この10年で生鮮野菜の価格は約4割上昇し、スーパーでの買い物に直結する形で影響しています。
果物産地の変化と新たな挑戦
果物も同様です。静岡県は全国2位のみかんの産地ですが、気温の上昇で果実が日焼けして市場に出せないケースが増えています。そこで注目されているのがアボカド。これまで輸入に頼っていた果実ですが、温暖化によって日本でも栽培が可能になるとシミュレーションされています。静岡県は1760万円を投じて産地化プロジェクトを開始し、現在8軒の農家が栽培方法を模索中です。日本産アボカドがスーパーに並ぶ日も近いかもしれません。
暑さに強い「スリック牛」の研究
兵庫県淡路島では、暑さ対策として「スリック牛」と呼ばれる新しい牛の研究が進んでいます。これはカリブ海の熱帯地域に生息する牛と乳牛を交配して生まれた品種で、毛が短く体温調節に優れています。4年前から人工授精に取り組み、すでに9頭の子牛が誕生しました。乳量が減りにくく、牛乳の品質も変わらないことから、将来の酪農を救う存在として期待されています。
新しい農作物の広がりと課題
全国では他にも、オクラやパッションフルーツ、ブラッドオレンジといった南国の作物に注目が集まっています。暑さに適した作物を育てる試みは広がっていますが、「栽培ノウハウが少なく安定生産に時間がかかる」「需要が少ないため普及につながりにくい」という課題もあり、簡単に切り替えることはできません。
それでも、将来の食卓を守るためには新しい挑戦が不可欠です。かつてバナナやパイナップルが国内では珍しかったように、未来にはアボカドやパッションフルーツが「定番の国産果物」となる可能性もあります。
暑さに打ち勝つための技術
番組では、農家が取り組んでいる暑さ対策も紹介されました。代表的なのは遮光ネットで直射日光を遮る方法や、作付け時期を早めたり遅らせたりして猛暑を避ける栽培方法です。さらに研究機関では、高温耐性のある新品種の開発も進んでいます。しかし予測では、温暖化対策を取らなければ2100年には「未熟米」が40%を占める可能性があり、今の努力だけでは十分とは言えません。
まとめ:食卓の未来を守るには
今回の「クローズアップ現代」が伝えたのは、猛暑による食材危機は「遠い未来の話」ではなく、すでに現在進行形の問題だということです。豚肉や牛乳の減産、米や野菜の価格高騰、果物の産地の変化…。これらはすべて私たちの食卓に直結する問題です。
同時に、暑さに強いスリック牛やアボカド産地化プロジェクトなど、希望につながる新しい取り組みも始まっています。消費者としては、旬の食材を選び、国産の新しい作物に注目することが、農家や地域の挑戦を支える一歩になります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

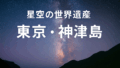
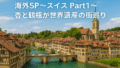
コメント