海外SPスイス編〜杏と鶴瓶が世界遺産の街ベルンを巡る〜
2025年8月25日に放送された「鶴瓶の家族に乾杯 海外SP〜スイスPart1」では、ゲストに杏を迎え、世界遺産の街ベルンを舞台に笑福亭鶴瓶と一緒に街歩きを楽しみました。杏はフランス在住で、スイスまでは2時間もかからない距離。ヨーロッパ各地に仕事で訪れることが多いと話しながら、自然豊かなスイスに期待を寄せていました。番組では、観光だけではなく現地の人との交流や偶然の出会いも数多く映し出され、スイスの魅力が存分に伝わる内容となりました。
ジグソーパズル好きの杏とベルン旧市街の探訪
杏には意外な一面があります。それはジグソーパズルが大好きということ。しかも趣味の域を超え、スペインで開かれる世界大会に2度も参加した経験を持っています。ベルンの旧市街を歩く中で、杏は「この風景がパズルになっていたらきっと楽しい」と想像を膨らませ、お土産屋に立ち寄ってパズルを探す場面も。残念ながら見つかりませんでしたが、その探す過程こそ旅の醍醐味。旧市街の美しい街並みと、杏のパズル好きが重なって、視聴者に「ベルンを歩いてみたい」と思わせるシーンでした。
老舗アンティーク時計店で触れる職人の技
スイスといえば時計。鶴瓶と杏は老舗のアンティーク時計店を訪ねました。ここでは修理工房も見学でき、緻密な作業の様子にふたりは興味津々。タイミングよく訪れたその週で1階の店舗は閉店を迎えるという話もあり、長い歴史を持つ店の貴重な瞬間に立ち会うことになりました。スイスの時計文化の奥深さと、街の移り変わりを感じられる場面でした。
ベルンの「あるある」とアインシュタインゆかりの地
旅の途中で現地コーディネーターから「ベルンのあるある」が紹介されました。代表的なのは噴水の水を直接飲めるという習慣。清らかな水が街中を流れるベルンならではの光景です。また、かつて地下の貯蔵庫として使われていた場所がカフェやショップとして利用されていること、さらに街の至る所にアインシュタインのベンチが設置されていることもユニークです。1905年に「特殊相対性理論」を発表したアインシュタインは、ベルン大学で研究を行っており、この街に深く関わりがあります。歴史と日常が重なり合う街の姿が印象的でした。
学生たちとの交流と韓国人夫婦の新婚旅行
ベルンの旧市街でアイスを食べていた鶴瓶と杏に、地元の学生たちが声をかけてきました。おすすめの観光スポットを尋ねると「クマ公園」との答え。ベルン市民にとって身近で大切な場所だと分かります。公園へ向かう途中、偶然出会ったのは新婚旅行中の韓国人夫婦。夫は大学で日本語を専攻していたと話し、日本に対する親近感が感じられる出会いでした。さらに、まだ正式にプロポーズをしていないという話題から、この旅先で思い切ってプロポーズをすることに。異国の地で起きた心温まるエピソードに、視聴者も思わず笑顔になりました。
クマ公園と鶴瓶のすれ違い
ベルンの象徴ともいえるクマ公園に到着。杏は橋の上から実際にクマの姿を見つけて大喜び。しかしその時、鶴瓶はトイレに行っており、結局見ることができませんでした。この小さなすれ違いも、番組らしいユーモラスな展開でした。旅の中で「見られる人」と「見逃す人」が出るのはリアルで、笑いと親しみを感じる場面でした。
住宅街での出会いとエルフェナウ公園
その後、鶴瓶はベルンの閑静な住宅街を散策。出会った住民の男性から「エルフェナウ公園がとてもきれい」と教えてもらいます。さらに話をするうちに、その男性は柔道経験者で、1964年東京オリンピックで銀メダルを獲得したエリック・ヘンニに指導を受けていたことが判明しました。昨年脳卒中を患ったことも語られ、健康への不安や人生の重みもにじみ出ていました。街歩きの中で偶然出会った人の人生に触れられるのが、この番組ならではの魅力です。
杏が向かった酪農の地・エメンタール
一方で杏は、スイスの代表的なチーズ産地であるエメンタールへ。地元の酪農家を訪れ、牛舎を見学しました。大きな牛との触れ合いはもちろん、そこで暮らす犬も登場。牧場で働く動物たちの存在がスイスの暮らしを支えていることが伝わります。さらに、牧場では森から水を引いて利用する生活も紹介され、自然と共に暮らす知恵に触れることができました。代々続く家族経営の営みは、土地に根ざした暮らしを象徴しています。
牧場での犬との出会いと案内
杏は牧場で牧羊犬(ボヘミアンシェパード)を見せてもらい、その働きぶりに感心しました。犬と人間、牛が一体となって営む牧場の暮らしは、日本ではなかなか見られない光景です。さらに、知り合いの乳牛を育てる牧場へ案内してもらえることになり、人と人とのつながりが次の出会いへと広がっていきました。異国の土地でも「人と人の縁」が自然に生まれていく姿は、まさに番組のテーマを体現しています。
エンディングと次回への期待
スイスPart1のエンディングでは、街歩きだけでなく、人との出会いや偶然の出来事が旅をより豊かにしていることが伝わりました。世界遺産ベルンの街並みやアインシュタインゆかりの地、クマ公園、エメンタールの牧場といったスポットが紹介され、それぞれに深い物語がありました。次回のPart2では、さらに自然や人との触れ合いが描かれることが予告され、視聴者の期待が高まります。
今回の記事では、NHK「鶴瓶の家族に乾杯 海外SP〜スイスPart1」の全エピソードをまとめました。スイス旅行やベルン観光、文化や人との出会いに興味のある方にとって、参考になる情報が満載です。
スイスが誇る“王様チーズ”エメンタールの魅力

エメンタールチーズは、スイス・ベルン州エメンタール地方で生まれた世界的に有名なチーズです。大きな穴があいた独特の見た目は「トムとジェリー」に登場するチーズのモデルとも言われ、世界中で親しまれています。スイスチーズの代表格として、長い歴史と確かな品質で「チーズの王様」と呼ばれています。
エメンタールチーズの由来と歴史
エメンタールという名前は、ベルン州を流れるエメン川とその周辺の谷を意味する地域名に由来しています。13世紀頃にはすでに製造が始まっていたとされ、ヨーロッパでも最古級のチーズのひとつです。何百年もの間、山あいの酪農家が牛の乳を使い、大きなホイール状のチーズを作り続けてきました。現在もその伝統は守られ、スイス国内で厳格な規則のもとに製造されています。
特徴的な見た目と風味
エメンタールの最大の特徴は、熟成の過程で発生する炭酸ガスによって生まれる大きな丸い穴(チーズアイ)です。黄色がかった表皮の中に並ぶ穴は、自然が作り出した模様のようで美しいです。味は塩分控えめでやさしいマイルドさがあり、ほんのり甘みとナッツのような香ばしさを感じられます。熟成期間によって風味が変化し、若いチーズはさっぱり、長期熟成品はコクと芳醇さが強まります。
製造と認証AOP
エメンタールチーズにはAOP(原産地呼称保護制度)があり、本物と呼べるのはスイス国内の限られた地域で伝統的な方法で作られたものです。AOPの認証を受けるには、無殺菌乳のみを使用し、最低4か月以上の熟成が義務づけられています。さらにチーズには焼印が押され、どの酪農家で作られたかまで追跡可能です。世界中で作られている「エメンタール風チーズ」と区別されるのは、この厳しい基準があるからです。
食卓での使い方
エメンタールは溶けやすく伸びが良い性質を持つため、チーズフォンデュの定番として知られています。スイスではグリュイエールチーズとブレンドして使うことが多く、まろやかな味わいがパンや野菜とよく合います。ほかにもグラタン、ピザ、キッシュ、サンドイッチなど幅広い料理に活躍し、オムレツやポテト料理に加えても風味がぐっと引き立ちます。
表:エメンタールの食べ方例
| 料理 | 特徴 | 合わせ方 |
|---|---|---|
| フォンデュ | よく溶けてなめらか | グリュイエールとブレンド |
| グラタン | コクが強まる | ベシャメルソースと相性抜群 |
| サンドイッチ | 香ばしい風味 | ハムや野菜と重ねる |
| オムレツ | 軽やかでマイルド | 卵に混ぜて焼く |
豆知識と文化的背景
エメンタールチーズは、直径80cm以上・重さ100kg前後の巨大なホイールで作られるのが伝統です。見た目のインパクトから観光客にも人気があり、工房では大きなチーズを見学することもできます。また、長期熟成のチーズでは穴の中に塩の結晶やしずくが見られることがあり、それは熟成の深さを示すサインです。
まとめ
エメンタールチーズは、長い歴史と伝統、そして厳格なAOP認証によって守られたスイスを代表するチーズです。マイルドで親しみやすい味わいと、料理の幅広い活用法から「家庭でもプロの料理でも愛される万能チーズ」といえます。旅行先の土産としてはもちろん、普段の食卓でも楽しめる一品です。エメンタールを通してスイスの文化や自然を感じることができるのは、世界中で愛されている理由そのものです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


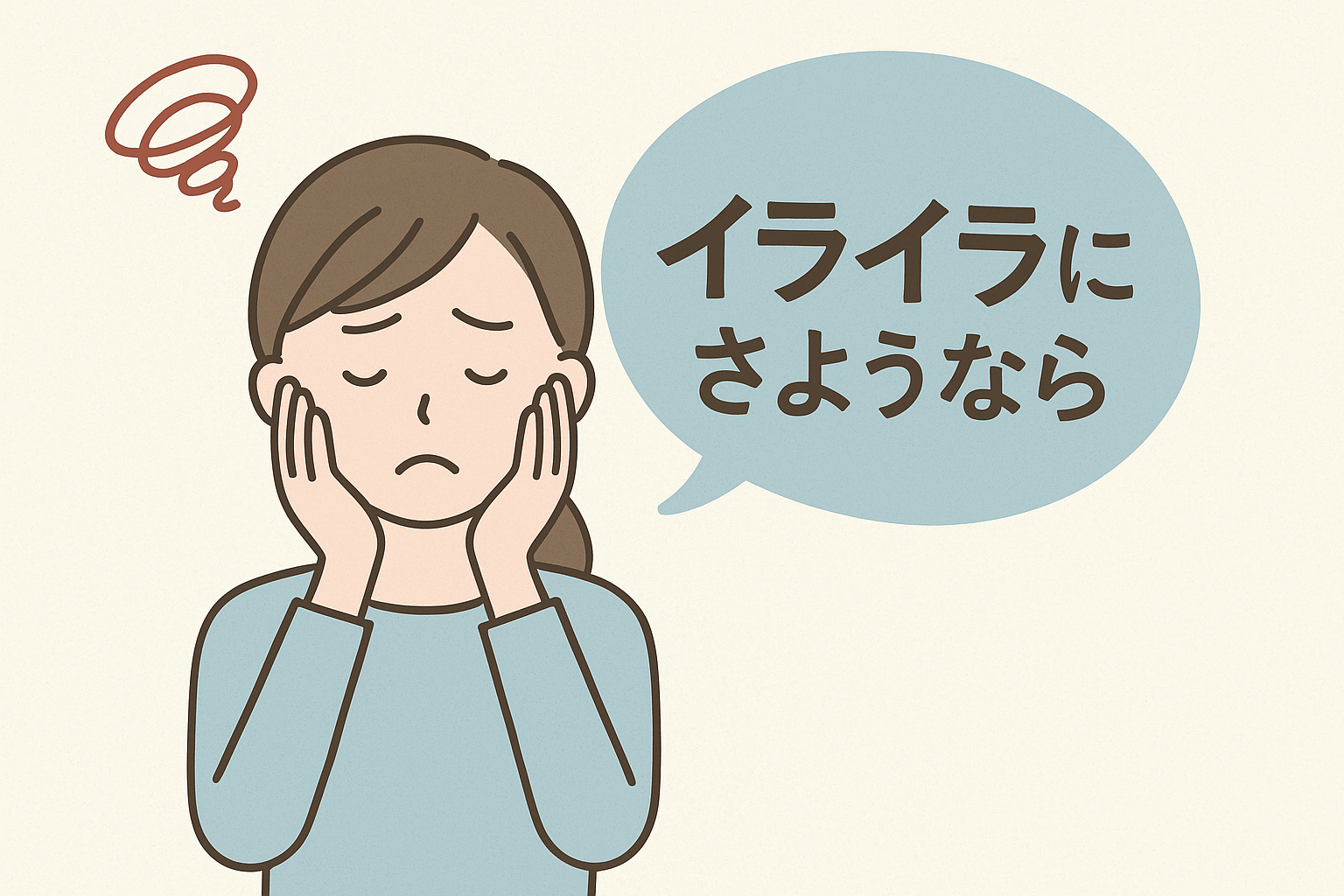
コメント