イライラにさようなら!東洋医学が教える夏のセルフケア
夏の暑さや冷房の温度差で、ついイライラしてしまうことはありませんか?実はこれは単なる気分の問題ではなく、東洋医学の視点から「寒熱の乱れ」や「気の消耗」が原因とされています。この記事では、NHKで放送される「明日から使える“新”東洋医学(4)イライラにさようなら」の内容を踏まえながら、夏に起こりやすいイライラの理由と、すぐにできる生活の工夫やセルフケアについて詳しく紹介します。読み終わる頃には、心と体を整えるヒントがきっと見つかります。
夏にイライラが起きやすいのはなぜ?
東洋医学では、自然界の気候や環境の変化が人の体や心に直接影響すると考えられています。夏は「火」の季節であり、強い熱のエネルギーが体を乾かし、心の安定を揺さぶります。この「夏の熱(Summer-Heat)」は、単なる暑さではなく病理的な要因(邪気)とされ、体のバランスを大きく崩す原因になるのです。
さらに日本の夏は湿度が高いため、「湿熱」と呼ばれる状態になりやすいのも特徴です。体に余分な湿気と熱がこもると、重だるさや頭のどんより感、集中力の低下を招きます。これに加えて現代特有の冷房環境も問題です。冷えた室内と暑い屋外を行き来することで、「寒熱の乱れ」が起こり、体表は冷たいのに体の内部には熱がこもるアンバランスな状態になります。この状態が続くと「気」が大量に消耗され、心に余裕がなくなり、イライラが強く出てしまうのです。
東洋医学で見る体と心のつながり
東洋医学の大きな特徴は、「体と心をひとつの存在」として捉える点です。体の調子が心に影響を与え、心の乱れが体にも現れるという相互作用が前提になっています。
・気・血・津液のバランス:気は体を動かすエネルギー、血は栄養と精神を支える基盤、津液は潤いを保つ体液です。気が滞ればイライラや焦燥感、血が不足すれば不眠や不安感、津液が失われると心も乾き落ち着きを失います。
・五臓と感情の関係:心は精神を司り、肝は気の流れと関係し、脾は消化や気血の生成を担います。例えば肝の働きが乱れると怒りっぽくなり、心に熱がこもると不眠や動悸が出やすくなるとされています。
・三宝(気・精・神):生命を支える根本的な要素で、これらが整って初めて心身は健康を保ちます。神(精神)が安定するためには、精(生命力)と気(活動の力)がバランスよく保たれることが必要です。
このように、体の不調はそのまま感情に結びつくため、夏のイライラを改善するには体と心の両面からアプローチすることが重要です。
今日からできるセルフケアの実践法
番組では、日常に簡単に取り入れられる工夫がいくつも紹介されました。特別な道具がなくてもできる方法なので、今日から実践できます。
・呼吸法で気を整える:ゆっくり息を吸って長く吐く「5秒吸って7〜10秒吐く」呼吸を繰り返すと、副交感神経が働き、気の巡りが整います。朝や寝る前に行うと特に効果的です。
・ツボ押し(太衝):足の親指と人差し指の骨が交わるあたりのツボを押すと、肝の気が流れやすくなり、イライラが落ち着きます。強く押しすぎず、じんわりと刺激するのがコツです。
・体を温める習慣:ぬるめのお風呂に浸かる、蒸しタオルを首やお腹に当てるなどで深部を温めると、冷えと熱のアンバランスを調整できます。冷たい飲み物の取りすぎを避けることもポイントです。
・香りで心を落ち着ける:ラベンダーや柑橘系の香りはリラックスと気の巡り改善に、ローズや白檀は心を静めるのに向いています。お茶やアロマで手軽に取り入れられます。
・軽い運動や気功:ストレッチや散歩、太極拳など、ゆったりとした運動は気を巡らせ、頭のもやもやを晴らします。早朝や夕方など涼しい時間に行うとより快適です。
食事で体の熱と心を調整する
食養生も東洋医学の大切な柱です。夏におすすめの食材は体に潤いを与え、熱を鎮める性質を持っています。
・スイカ、キュウリ、トマト、ズッキーニ、ミントなどは体を冷やしすぎずに熱を和らげます。
・菊茶やペパーミント茶は清涼感があり、心を落ち着けます。冷たくしすぎず常温で飲むのがポイントです。
・湿気がこもりやすい人は、緑豆やトウモロコシ茶、スイカの皮などで余分な湿を排出します。
・揚げ物や辛い料理は熱を増幅するため控えめにし、蒸す・煮るといった調理法で消化を助けるのも効果的です。
さらに、体質に合わせた漢方薬も選択肢になります。例えば、気の巡りを整える「香蘇散」、胃腸の不調を伴うイライラに「抑肝散加陳皮半夏」、ストレスや女性特有の不調に「加味逍遥散」などがあります。ただし漢方は体質に合うかどうかが大事なので、専門家に相談して取り入れると安心です。
生活習慣の工夫で心を安定させる
日常のちょっとした工夫も心身の安定に大きく役立ちます。
・睡眠の質を高める:寝る前にスマホを避け、ハーブティーや軽いストレッチでリラックスする時間を作ると、心(神)が休まります。
・心を満たす活動を持つ:友人との食事や趣味の時間など、小さな喜びは心の栄養になります。
・衣服や環境の工夫:通気性のよい素材を選び、寝具や室温を快適に保つことで体に余分な負担をかけないようにします。
まとめ
夏のイライラは単なる気分の問題ではなく、東洋医学の視点で見ると「夏の熱」や「寒熱の乱れ」「気の消耗」が関わっています。体と心は一体であり、体調の乱れはそのまま感情の不安定さにつながります。呼吸法、ツボ押し、食養生、香り、運動、生活習慣の工夫など、どれも日常に取り入れやすいセルフケアです。NHKの番組が伝えるように、こうした知恵を現代の暮らしに合わせて実践することで、夏のイライラを和らげ、心身を健やかに保つことができます。ぜひ今日から、自分に合った方法を少しずつ試してみてください。
抑肝散加陳皮半夏エキス錠 クラシエの詳しい商品情報

この商品は「抑肝散」に半夏(ハンゲ)と陳皮(チンピ)を加えた改良処方で、古典的な漢方理論と日本での臨床経験を組み合わせて作られています。イライラや神経過敏、不眠など心身の乱れをサポートする目的で用いられ、特に更年期に伴う精神的不安や子どもの疳症、夜泣きにも適応するのが特徴です。日常生活で起こりやすい「ストレスからくる不調」に幅広く対応できる点が大きな魅力です。
効能・適応症
この漢方は、神経が高ぶりやすい体質や精神の不安定さを整えるために使用されます。適応は以下の通りです。
-
神経が高ぶるタイプの神経症や不眠症
-
小児の夜泣き、疳症(神経が過敏になって落ち着かない状態)
-
更年期障害による精神的不安やイライラ(血の道症に相当)
-
歯ぎしりや情緒不安定など
こうした症状は、東洋医学的には「肝の気が昂ぶる」ことで起きやすく、それを抑えて調整するのがこの処方の狙いです。
成分と分量
成人1日12錠あたりには、以下の成分が含まれています。
| 生薬 | 配合量(乾燥原料換算) | 働きの目安 |
|---|---|---|
| 半夏(ハンゲ) | 2.5g | 胃腸の調子を整え、気の流れを助ける |
| ビャクジュツ | 2.0g | 余分な水分を除き、体のだるさを改善 |
| ブクリョウ | 2.0g | 精神を落ち着かせ、睡眠をサポート |
| センキュウ | 1.5g | 血の巡りをよくして頭の重さを軽減 |
| チンピ | 1.5g | 胃腸の動きを助け、気の停滞を改善 |
| トウキ | 1.5g | 血を補い、心身の安定に役立つ |
| チョウトウコウ | 1.5g | 神経の高ぶりを抑え、落ち着きを与える |
| サイコ | 1.0g | 気の巡りを整え、イライラを和らげる |
| カンゾウ | 0.75g | 他の生薬の働きを調和させる |
これらから抽出されたエキス2,500mgが含まれており、精神的な不安定さやイライラに幅広く働きかけます。
用法・用量
成人(15歳以上)は1回4錠を1日3回、食前または食間に水または白湯で服用します。服用しても1か月ほど効果が見られない場合は自己判断せず、医師や薬剤師に相談することが推奨されています。
注意点
この薬にはカンゾウ(甘草)が含まれているため、葛根湯など他の漢方薬との併用で成分が重なり、偽アルドステロン症(血圧上昇、むくみ、低カリウム血症など)を引き起こす可能性があります。また、消化器が弱い人は食欲不振や胃部不快感が現れる場合があるため、体調に注意しながら使用する必要があります。安全に使うためには、医療者に相談しつつ続けることが大切です。
関連商品
抑肝散加陳皮半夏エキスには錠剤タイプと顆粒タイプがあり、ライフスタイルに合わせて選べます。
-
クラシエ 抑肝散加陳皮半夏エキス錠 240錠(約20日分、錠剤タイプ。じっくり続けたい人向け)
-
クラシエ 抑肝散加陳皮半夏エキス 顆粒 24包(持ち運びに便利な顆粒タイプ。少量から試したい人向け)
| 商品名 | 容量 | 価格目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 抑肝散加陳皮半夏エキス錠 | 240錠(20日分) | 約5,000円前後 | じっくり服用したい方向け |
| 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 | 24包 | 約2,400円前後 | 携帯しやすく旅行や外出にも便利 |
まとめ
クラシエ漢方 抑肝散加陳皮半夏エキス錠は、イライラ、不眠、神経過敏、更年期の不安などに広く対応できる処方です。抑肝散を基本に半夏と陳皮を加えることで、胃腸を守りながら精神面を安定させる工夫がされています。用法や注意点を守れば、心の落ち着きをサポートする頼もしい漢方薬です。錠剤と顆粒があり、ライフスタイルや使用シーンに合わせて選べるのも魅力です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

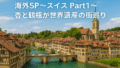
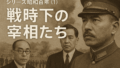
コメント