生まれ変わる西武鉄道を乗り鉄が体感!中川家が挑む激レアルート旅
鉄道好きなら一度は耳にしたことがある【鉄オタ選手権】。今回の舞台は“生まれ変わる西武鉄道”。
中川家の礼二と剛が案内役となり、特別に貸し切られた特急ニューレッドアローで、普段は絶対に走らない“激レアルート”を旅しました。
この記事では、番組内で紹介された新しいサステナ車両や工事中の東村山駅潜入、そして名車たちの歴史まで、鉄道ファンが気になるポイントをすべて紹介します。
「西武鉄道がどう変わっていくのか?」「ニューレッドアローって何が特別なの?」という方に向けて、読めば鉄道旅に出たくなる内容をたっぷりお届けします。
NHK【時空鉄道〜あの頃に途中下車〜】遠藤憲一の下積み時代と銀座線ビートルズホテル伝説|2025年4月29日放送
サステナ鉄道へ!小田急から譲渡された8000形が西武仕様に再生
今回の放送の中心テーマとなったのが、小田急電鉄から譲り受けた8000形電車の再生プロジェクト。
この車両はサステナ車両と呼ばれ、部品を再利用しながら改修・再整備を行い、西武鉄道の新しい仲間として国分寺線などに導入予定です。
西武鉄道は2030年度までにVVVFインバータ制御車両を100%にするという大きな目標を掲げています。
このVVVFインバータとは、電力消費を約50%削減できる最新技術。
ブレーキ時の回生電力を活用することで環境負荷を抑え、二酸化炭素排出量の大幅削減につながります。
車体は小田急時代の姿を残しており、ドアの開閉音や取っ手など、一部はそのまま使用。
しかし、細部の設計や安全システムは西武独自にカスタマイズされており、“過去の資産を未来へつなぐ鉄道の再生”という理念が感じられました。
番組ではクイズ形式で「サステナ車両で作り変えたのはどこ?」という問題も出題。
出演者全員が「乗務員扉の取っ手」と回答し、見事正解。
礼二は「細かいところまで気づく鉄道の職人技ですね」と感心していました。
南入曽車両基地に潜入!筋トレルームがある鉄道基地?
さらに番組は埼玉県狭山市にある南入曽車両基地へ。
ここは西武鉄道のメンテナンス拠点であり、数百両におよぶ車両が日々整備されています。
驚きだったのは、リニューアルされた社員用施設に筋トレルームが設置されていたこと。
整備士や運転士が安全に仕事を続けるためには体力と集中力が欠かせません。
そのため、社員の健康維持を目的に導入されたこの施設では、社員たちがトレーニングに励む姿が映し出されました。
鉄道という“機械の世界”に見えて、実は“人の健康”が支えているというメッセージが伝わってきます。
また、50年以上前の映像資料として、東映ニュース(1969年制作)の貴重な映像も放送。
若き鉄道員たちが手作業で車両を整備する姿が記録されており、礼二は「昔の人たちの努力の上に、今の鉄道があるんですね」と語っていました。
このシーンは鉄道ファンのみならず、多くの視聴者に胸を打った場面だったでしょう。
西武鉄道本社の社員食堂がすごい!人気は“バターチキンカレー”
続いて中川家とスタッフが訪れたのは、西武鉄道本社(所沢市)の社員食堂。
2024年に全面リニューアルされ、温かみのある照明と大きな窓が特徴の開放的な空間に生まれ変わっています。
食堂のメニューは、鉄道員たちの健康を考えたバランス重視の構成。
この日の人気メニューは、おろし焼き肉定食、カレー南蛮うどん、そして特製のバターチキンカレー。
特にカレーは、スパイスの香りとまろやかさが絶妙で、礼二が「これは駅弁にしても売れそう!」とコメントしていました。
食堂には沿線の地域食材を取り入れたメニューも多く、秩父味噌の豚丼など地元とのつながりを感じる料理も並びます。
“働く人を支える食堂”というより、“地域文化を味わう場所”へと進化している印象を受けました。
名車3選に見る西武鉄道の誇りと進化の物語
番組の中盤では、西武鉄道が誇る名車3選が登場。
そのラインナップは鉄道ファン垂涎の内容でした。
・10000系ニューレッドアロー
1993年に新宿線でデビュー。快適性を重視した7両編成の特急で、30年以上にわたり多くの人々を運び続けています。
VVVF化によって静粛性が増し、“都会と自然をつなぐ特急”として今も第一線で活躍中。
・2000系通勤車両
1977年に登場し、西武鉄道初の両開き4ドアを採用した通勤の主役。
総製造数は444両に達し、西武の歴史の中でも最も多く製造された形式。
耐久性と整備性の高さから、現在もリニューアル車が現役で走っています。
・001系特急ラビュー
2019年にデビューした最新鋭の特急車両。
丸みを帯びた独特のデザインと、全面ガラス張りのような大きな窓が印象的です。
座席のクッション性や照明の明るさも工夫され、乗客に“空を飛ぶような開放感”を与えるデザインで話題となりました。
池袋線ではすでにすべての特急列車がラビューに統一されています。
東村山駅の高架化工事を現地で取材!
番組後半では、東村山駅の高架化工事現場に潜入。
2015年から続くこの大規模プロジェクトは、2025年夏に新宿線の下り線が高架化予定となっています。
礼二たちは安全帽をかぶり、完成前のホームや線路を特別に見学。
中でも印象的だったのは、ホームドアがクレーンで空から吊り上げられて設置される瞬間。
重厚な鉄の設備がゆっくりとホームに降りていく光景に、一同から感嘆の声が上がりました。
「これが“空飛ぶドア”か!」という言葉も飛び出し、西武鉄道の安全性・利便性への挑戦がリアルに伝わるシーンでした。
ニューレッドアローで走る!“激レアルート”横断の興奮
番組のクライマックスは、ニューレッドアローによる特別ルート走行。
普段は新宿線限定のこの特急が、今回は上石神井駅→拝島線→国分寺線と横断運転を実施。
“特急が単線区間を走る”という、通常では絶対に見られない貴重なシーンが繰り広げられました。
上石神井駅では普段通過する駅に停車し、そこから車庫方面へと進入。
折り返す際には礼二らが先頭車両へ移動し、反射鉄(車窓に映る自分たちの姿を楽しむファン文化)まで満喫。
拝島線に入ると、車内は拍手と歓声に包まれ、西武社員も思わず興奮していました。
さらに国分寺線に入ると「単線を特急が走ってる!」と一同が驚き、鷹の台駅ではホームの子どもたちが手を振る温かい場面も。
“鉄道と地域をつなぐ感動”が詰まった名シーンとなりました。
熱戦の早押しクイズ!優勝は現場最強・西武社員チーム
ラストは恒例の早押し鉄道クイズ対決。
問題は「西武鉄道が特許を取得した設備は?」「西武鉄道あるある“終点じゃないのにご乗車ありがとうございましたと言いがち”」など、マニア心をくすぐる内容ばかり。
最終問題では山口線や廃食油、マルチプルタイタンパー(線路整備用車両)といった超専門的なキーワードも飛び出し、スタジオは大盛り上がり。
結果は西武社員チームが優勝し、現場愛と知識の深さを見せつけました。
礼二は「やっぱり現場の人がいちばん強い!」と笑顔で締めくくり、番組は熱気の中で幕を閉じました。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・西武鉄道は小田急から譲渡された8000形を再利用したサステナ車両で環境負荷を削減。2030年度にはVVVF制御100%を目指している。
・社員食堂や車両基地の筋トレルームなど、“働く人を支える鉄道づくり”が進化。
・ニューレッドアローが横断運転を実施し、ファン垂涎の激レアルート旅が実現した。
“生まれ変わる西武鉄道”という言葉は、単に車両や設備だけではなく、“人・地域・未来”すべてを含んだ進化の象徴でした。
中川家が案内したこの旅は、鉄道の魅力を再発見する1時間。
次回の鉄オタ選手権でも、また新たな鉄道の感動に出会えることでしょう。
【出典・参考】
・NHK総合「鉄オタ選手権 西武鉄道の陣・第二戦!激レアルートを走る特急乗り鉄旅」(2025年10月13日放送)
・西武鉄道公式サイト
・小田急電鉄プレスリリース(車両譲渡関連)
・東映ニュースアーカイブ(1969年版・西武鉄道映像)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


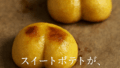
コメント