『100分de名著 ブラム・ストーカー“ドラキュラ”(2)排除される女性たち』
もしあなたが“ドラキュラ”という言葉から血と牙、恐怖の闇を思い浮かべたなら――その背後に隠されたもう一つの物語に、きっと驚くでしょう。
今夜の「100分de名著」が取り上げるのは、ブラム・ストーカーの代表作『ドラキュラ』。その第2回「排除される女性たち」では、恐怖小説の仮面の下に潜む、19世紀末の社会が抱えた“女性と自由”の問題が語られます。
ヒロイン・ミーナの親友・ルーシーが吸血鬼に変わるという衝撃的な展開は、単なる怪奇ではなく、“新しい女性像”への不安や偏見を象徴しているのです。
Eテレ【100分de名著】ブラム・ストーカー『ドラキュラ(1)』誕生の秘密とアングロアイリッシュの葛藤|2025年10月6日
社会に逆らう“新しい女性”ルーシー
『ドラキュラ』の登場人物ルーシー・ウェステンラは、外見も性格も魅力的な女性として描かれています。しかし彼女は、ただの「可憐な女性」ではありません。
彼女が象徴するのは、当時イギリスで登場し始めた“ニューウーマン”という新しいタイプの女性。結婚だけが女性の幸せではないという考え方を持ち、社会的にも経済的にも自立しようとする姿勢を示していました。
この思想は、産業革命以降に広がり始めた女性の教育機会の拡大や、都市で働く女性の増加とともに芽生えたものでした。しかし同時に、保守的な社会からは「女性の分をわきまえない」と強く反発を受けたのです。
ルーシーは、自由に恋を語り、複数の男性からの求婚を軽やかに受け止める女性として描かれます。彼女の奔放さは当時の読者にとって魅力的であると同時に、恐れの対象でもありました。
つまり、ルーシーは“恐怖”の対象となる前から、社会の中で“異端者”としての位置に立たされていたのです。
“杭打ち”という儀式に隠されたメッセージ
やがてルーシーは吸血鬼ドラキュラの毒牙にかかり、彼女自身も吸血鬼となります。そしてその後、白人中流階級の男性たちによって「杭を打たれて葬られる」場面を迎えます。
このシーンは『ドラキュラ』の中でも最も衝撃的な場面ですが、単なるホラー演出ではありません。文化社会学的に見れば、それは当時の男性社会が“女性の自由”をどのように恐れ、どう支配してきたかを象徴する儀式なのです。
吸血鬼となったルーシーは、抑え込まれていた欲望と感情をむき出しにする存在として描かれます。そこに男性たちは恐怖を覚え、彼女を“怪物”として排除することで安心を得る。
杭を打つという行為は、“社会秩序の回復”を意味します。つまり、ルーシーを葬る行為は、自由を求める女性の声を再び沈黙させるための象徴的な儀式なのです。
上智大学教授の小川公代氏は、この場面を“ミソジニー(女性嫌悪)的な社会への風刺”と読み解いています。ブラム・ストーカーは単に残酷な描写を楽しませるために書いたのではなく、当時の社会が抱える矛盾を冷静に、しかし痛烈に映し出したのです。
作者ブラム・ストーカーの視点――“弱者のまなざし”
『ドラキュラ』の作者であるブラム・ストーカーは、アイルランド出身で、幼少期に長く病床に伏せた経験があります。社会の“主流”から外れた感覚を持ち続けていた彼は、当時の権力構造や差別に対して敏感でした。
そのため、彼の作品には常に“弱者への共感”が流れています。
ルーシーの描写にも、それがはっきりと表れています。吸血鬼となってもなお彼女は哀れで美しく、社会に理解されずに苦しむ姿が丁寧に描かれています。
ブラム・ストーカーは、彼女を単なる被害者ではなく、“社会に誤解された女性の象徴”として描いたのです。
ルーシーの物語は、恐怖よりも哀しみが勝る――その筆致に、作者の優しさと痛みが滲んでいます。
“異端”は本当に恐ろしいのか?現代社会とのつながり
130年前に書かれた『ドラキュラ』が、なぜ今も私たちの心に響くのでしょうか。
それは、この物語が“異なる存在を恐れる社会の構造”を見事に描いているからです。
現代でも、価値観の違う人・声を上げる女性・新しい働き方を選ぶ人などが、時に「理解されない存在」として孤立することがあります。
『ドラキュラ』の世界でルーシーが排除されたのは、まさにその構図の原型。異端を恐れ、同調を強いる社会の姿は、いまも形を変えて私たちの周りに息づいています。
文化社会学の視点から見れば、ルーシーの悲劇は“怪物化された女性”の物語ではなく、“社会が怪物を生み出した”物語なのです。
ブラム・ストーカーは、恐怖の物語を通して、読者に「何を恐れているのか?」を問いかけているのかもしれません。
番組への期待――文学の奥にある“社会の声”を聴く
今回の「100分de名著」では、小川公代(上智大学教授)が文学研究の立場から、この作品に込められたジェンダーと権力の構造を解説します。
司会の伊集院光と安部みちこアナウンサーが投げかける問いが、作品の奥に眠る“社会の声”を引き出すでしょう。
さらに、俳優満島真之介による朗読と、加藤有生子の語りが、ルーシーの苦悩や優しさをどう表現するのかにも注目です。
文学と社会をつなぐ25分。その中で、私たちは“ドラキュラ”という物語を通して、自分たちの社会に潜む無意識の偏見を見つめ直すことになるかもしれません。
この記事のポイント
・ルーシーは19世紀の“ニューウーマン”の象徴であり、自由を求めた女性だった
・杭打ちの場面は、女性の自立を恐れた社会構造の象徴として描かれた
・ブラム・ストーカーは弱者の視点からルーシーに同情的な筆を向けた
・現代にも通じる“異端と排除”のテーマが、今もなお共感を呼ぶ
・番組ではジェンダー・文学・社会の三つの視点から深く読み解かれる予定
ルーシーの物語は、単なる恐怖の象徴ではなく、社会がどう“異なる存在”と向き合うかを問う鏡です。
私たちがその鏡をのぞき込むとき、そこに映るのは、130年前のイギリスではなく、今の私たち自身かもしれません。
出典:NHK公式番組情報(100分de名著『ブラム・ストーカー“ドラキュラ”(2)排除される女性たち』2025年10月13日放送)
リンク:https://www.nhk.jp/p/meicho/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

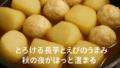
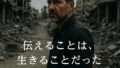
コメント