『ドラキュラ』が生まれた時代の空気を感じてみませんか?
みなさんは『ドラキュラ』という作品にどんなイメージをお持ちでしょうか?怖い吸血鬼の物語、ハロウィンやホラー映画でよく見かけるキャラクター…そんな印象を持つ方も多いはずです。でも実はこの小説、単なる怪奇物語ではなく、当時の社会の不安やマイノリティの苦悩を映し出した文学作品なのです。「なぜ100年以上前に書かれた小説が、今も読み継がれているのか?」その答えが気になる方に向けて、今回はNHKの人気シリーズ100分de名著で取り上げられるブラム・ストーカー『ドラキュラ』の第1回放送内容を紹介します。
物語の始まりは不安と恐怖の旅から
初回の番組で焦点を当てるのは、主人公ジョナサン・ハーカーがルーマニアにあるドラキュラ伯爵の城を訪ねる冒頭シーン。白人中産階級の典型といえるジョナサンが、自分とは異なる文化や存在に触れたときの恐怖が、緊張感たっぷりに描かれています。この出会いの場面は、ただのホラー演出ではなく、「異質なもの」への恐れを象徴する重要な要素といえます。
アングロアイリッシュの苦悩が怪物を生んだ
小説が書かれた当時、アイルランドではイギリスから派遣された支配層アングロアイリッシュが没落し、彼らはイギリス人でもアイルランド人でもない存在として孤立していました。作者ブラム・ストーカー自身もアングロアイリッシュで、社会から疎外される立場を体験していました。そんな複雑なアイデンティティの葛藤を、「異質な存在」である『ドラキュラ』に投影したのです。つまり、この怪物は恐怖の象徴であると同時に、社会から居場所を失った人々の姿でもありました。
怪物が照らす「異質さ」と向き合う力
第1回の放送では、『ドラキュラ』という怪物がただのフィクションではなく、当時の人々が抱いた「自分たちとは違う存在への不安」を鮮やかに映していることを解説します。この視点から読むと、吸血鬼は決して他人事の存在ではなく、現代社会に生きる私たちが抱く異質さや多様性への戸惑いを考える手がかりになります。だからこそ、『ドラキュラ』は今も読み継がれ、映像化され続けているのです。
番組の案内と出演者
この新シリーズは、英文学研究の第一人者である小川公代(上智大学教授)が講師を務め、作品の深い魅力を丁寧に解説します。司会は伊集院光と安部みちこ。学問的な裏付けと親しみやすい進行のバランスが取れた番組になることが期待されます。初回のテーマは「ドラキュラの誕生」。執筆背景に焦点を当てた解説で、作品世界の奥行きを知る絶好の機会です。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・『ドラキュラ』の冒頭シーンは、異質な存在への恐怖を象徴する大切な場面
・作者ブラム・ストーカーはアングロアイリッシュとしての疎外感を怪物に投影した
・番組では執筆背景から作品の魅力に迫り、現代にも通じるテーマを探る
『ドラキュラ』はホラーを超えた文学であり、人間社会の根源的なテーマを映し出す作品です。これからの放送では、さらに深い読み解きや名場面が紹介されるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

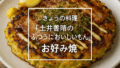
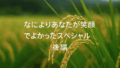
コメント