明日から使える“新”東洋医学(2)もしかして夏太り?
猛暑や残暑が続く今、「夏太り」という言葉を耳にする機会が増えています。昔は夏といえば汗をかきやすく、自然と体重が減るイメージがありました。しかし近年は、冷房の効いた室内での生活や、冷たい食べ物・飲み物の摂りすぎによって、逆に太ってしまう人が多いのが現状です。この記事では、現代の夏太りの背景と、東洋医学の知恵を取り入れた予防・改善のヒントをまとめます。
夏太りが起こる現代の背景
現代における夏太りは、いくつもの生活習慣や環境要因が重なって起こります。暑い季節にもかかわらず体重が増えてしまう背景には、日常の過ごし方や食事の傾向が深く関係しています。
冷房による代謝低下
エアコンで室温が常に快適な状態に保たれていると、体は自分で体温を調整する機能をあまり使わなくなります。この状態は「サーモニュートラルゾーン」と呼ばれ、エネルギー消費が最小限に抑えられてしまいます。本来であれば、暑さや寒さに反応して体が熱をつくったり放出したりしますが、冷房環境ではその働きが減り、結果として基礎代謝が下がります。このわずかな代謝低下が積み重なることで、消費カロリーは少なくなり、太りやすい体の状態になります。
冷たい飲食物の摂りすぎ
真夏はアイスクリーム、かき氷、冷たいジュースなどがつい欲しくなります。これらの冷えた食品や飲み物は、一時的には体を涼しく感じさせますが、胃腸を内側から冷やし、消化機能を低下させます。消化がうまく進まないと栄養や糖分がエネルギーとして使われにくくなり、体内に蓄えられて脂肪増加やむくみにつながります。特に砂糖やシロップが多く含まれる甘い飲み物は、血糖値を急上昇させ、脂肪として蓄積されやすくなります。
活動量の減少
猛暑日は外出や運動を避ける人が増えます。屋外の活動量が減るだけでなく、室内でも動かずに過ごす時間が長くなりがちです。これにより1日の総消費カロリーが減少します。また、夏はもともと基礎代謝がやや低下する傾向があるため、同じ食事量でも消費できないエネルギーが増え、体脂肪として蓄積されやすくなります。
高カロリーイベント食の増加
夏はバーベキューやビアガーデン、旅行先での外食など、普段よりカロリーの高い食事をとる機会が多くなります。さらに「特別な日だから」と気持ちが緩み、食べすぎや飲みすぎをしやすくなります。アルコールや甘いカクテルは糖分やカロリーが高く、脂肪蓄積を促進します。旅行やイベントが連続すると、その間に増えた体重を戻す前にさらに増えてしまうこともあります。
睡眠不足やストレスによる影響
暑さで寝苦しくなったり、夜更かしをしたりすると睡眠不足になります。睡眠が足りないと食欲を抑えるホルモンが減り、逆に食欲を増進させるホルモンが増えるため、食べる量が自然に増加します。また、夏のスケジュールの忙しさや人間関係のストレスも、甘い物や高脂肪食品を欲する原因となります。このように複数の要因が重なって、むくみや脂肪の蓄積が加速していくのです。
東洋医学から見る夏太りの原因
東洋医学では、夏太りは「気(エネルギー)」「血(血流)」「水(体の潤い)」のバランスの乱れによって生じると考えられています。特に、体質によって現れやすい傾向があり、主に次の2つが深く関わります。
水滞(すいたい)
水滞は、体内に余分な水分が滞っている状態を指します。体の巡りが悪くなるため、むくみや重だるさ、体の冷えが起こりやすくなります。特に、冷たい飲み物やアイス、甘い物をよく摂る人に多く見られます。水分の処理がうまくいかず、体の中に湿気がこもることで、脂肪がつきやすい状態になります。肌のくすみや下半身の冷えも、このタイプの特徴です。
気虚(ききょ)
気虚は、体を動かすエネルギー(気)が不足している状態です。疲れやすく、体を動かすことが億劫になり、自然と活動量が減って代謝も下がります。このタイプは痩せ型でも太りやすく、特にお腹まわりに脂肪がつきやすくなります。また、少し動いただけで息切れや倦怠感が出やすく、冷えやむくみも伴うことがあります。
季節と臓腑の関係
東洋医学では、夏は「心」や「小腸」の働きが高まる季節とされます。しかし、冷房による体の冷え、夜更かしによる自律神経の乱れ、冷たい飲食の習慣などによって、体に「湿」や「冷え」がたまりやすくなります。これらが巡りを妨げ、代謝低下やむくみを引き起こします。特に湿気がこもると、消化を担う「脾」の機能が弱まり、栄養の巡りも悪くなって太りやすい状態になります。
このように、東洋医学では夏太りを単なる摂取カロリー過多としてではなく、体質と季節の影響が絡み合った結果ととらえ、その改善には体の巡りとバランスを整えることが重要とされています。
放置するとどうなる?
夏太りをそのままにしておくと、体の見た目だけでなく、健康や心の状態にも影響が広がります。短期的な変化から長期的なリスクまで、注意すべき点は多くあります。
急な体重増加とむくみ
夏太りでは数キロ単位の急な体重増加が起こることがあります。その多くは脂肪ではなく、水分やむくみ由来ですが、放置すると徐々に脂肪として定着してしまいます。特に下半身や顔まわりのむくみは見た目の変化も大きく、服のサイズ感にも影響します。
リバウンド体質への変化
季節の変わり目ごとに「増えては減らす」を繰り返すと、体は脂肪をため込みやすい省エネモードに変化します。筋肉量が減って基礎代謝が落ちるため、同じ生活をしていても以前より太りやすくなります。
生活習慣病のリスク上昇
長期間の体重増加や脂肪蓄積は、糖尿病・高血圧・脂肪肝などの生活習慣病の発症リスクを高めます。特に内臓脂肪型肥満は心疾患や脳血管障害の原因にもなりやすく、早めの予防が欠かせません。
関節や腰への負担
体重が増えると、膝や腰など関節への負担が大きくなります。これにより関節痛や腰痛が悪化し、運動量がさらに減って体重増加を助長する悪循環に陥ります。
心の健康と生活の質の低下
見た目の変化や体の重さは、自尊心や自己評価の低下を招きます。さらにストレスや不安感が強まることで、暴飲暴食や夜更かしなど不健康な行動が増え、心身ともにバランスを崩しやすくなります。
このように、夏太りを放置すると健康面と精神面の両方にダメージを与え、将来的に生活の質を大きく下げる可能性があります。早い段階で生活習慣を見直し、体の巡りや代謝を整えることが大切です。
だいたいでOKのツボエクササイズ
ツボ押しは、正確にミリ単位で位置を探す必要はありません。「このあたりかな」という感覚で押しても十分効果があります。体が反応する場所を見つけて、軽く押すだけでも、巡りや代謝のサポートにつながります。
足三里(あしさんり)

足三里は、膝のお皿の下、外側のくぼみから指4本分下の位置にあります。すねの骨の外側沿いを指でなぞると、少しへこんだ感触の場所です。胃腸の働きを整え、消化不良や食欲不振の改善、水分代謝の促進に役立ちます。特に長時間座りっぱなしや、冷房の効いた部屋で体がだるくなったときに押すと効果的です。むくみが気になるときにもおすすめです。
中脘(ちゅうかん)

中脘は、みぞおちとおへそを結んだ線のちょうど真ん中にあります。お腹を軽く押すと少しへこむ場所です。胃の冷えや張り、消化の遅れを改善し、食後のもたれ感をやわらげます。冷たい飲み物を飲みすぎた日や、食欲が落ちたときに押すと、胃の働きがゆっくり整っていきます。
三陰交(さんいんこう)

三陰交は、内くるぶしの頂点から指4本分上に位置し、すねの骨の際にあります。血流を促進し、冷えやむくみ、足のだるさを改善します。特に長時間立ちっぱなしのあとや、足先が冷えるときに効果的です。女性の体調バランスを整える働きもあり、冷房による冷え対策にも向いています。
陰陵泉(いんりょうせん)

陰陵泉は、ひざ下の内側で、すねの骨の縁を上に向かってさすり上げたときに指が止まるくぼみにあります。体内の余分な水分を排出しやすくし、むくみやだるさを改善します。特に湿度が高い日や、体が重く感じる日に押すと巡りが良くなります。梅雨時期や夏場の湿気による不調にも有効です。
押し方とタイミング
どのツボも、指の腹で「少し痛いけれど気持ちいい」程度の強さで押すのがポイントです。1回3秒押し、これを5回程度繰り返します。特別な時間をとらなくても、テレビを見ながらや仕事の合間にサッとできるのが魅力です。体の反応を感じながら、無理なく続けることが大切です。
薬膳ごはんで体を整える
東洋医学では、脾と腎を整える食材が夏太り対策の基本です。
-
健脾:大豆、じゃがいも、オクラ、人参、豚肉
-
補陽:ねぎ、生姜、にら、まぐろ
-
利湿:冬瓜、きゅうり、ハトムギ、とうもろこし、緑茶
おすすめレシピは、夏野菜と鶏肉のシナモンスープ(鶏むね肉、生姜、冬瓜、シナモン)や、トマトとミョウガのピクルス(お酢で血流改善)など。身近な食材で簡単に作れます。
今できるセルフケアまとめ
-
温かい飲み物を取り入れる:白湯やハーブティーで胃腸を守る
-
冷たい・脂っこい食事を控える:蒸し料理や温スープが◎
-
涼やかな食材を活用:きゅうり、スイカ、梨、菊花茶など
-
軽い運動を継続:散歩やストレッチで代謝維持
-
過食防止:食前の水分摂取で満腹感を高める
まとめ
夏太りは、現代の生活環境と食習慣が作る新しい季節病ともいえる存在です。ツボ押し・薬膳・生活習慣の見直しで、無理なく体を整えることができます。今回の「明日から使える“新”東洋医学(2)」放送後には、番組で紹介された具体的な薬膳レシピやエクササイズを追記しますので、記事を再チェックしてみてください。
ソース
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

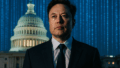
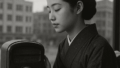
コメント