「戦時下の宰相たち」
2025年8月25日にNHK総合で放送された「映像の世紀バタフライエフェクト」シリーズ昭和百年(1)では、「戦時下の宰相たち」が特集されました。昭和初期、日本は不況と軍事拡張の狭間で揺れ動き、首相たちは苦しい判断を迫られ続けました。この記事では、番組内容をもとに浜口雄幸から鈴木貫太郎までの宰相たちの決断と国民社会の動きを丁寧に振り返ります。検索して訪れた方の多くは「なぜ日本は戦争に突き進んだのか」「首相たちはどんな役割を果たしたのか」を知りたいのではないでしょうか。この記事を読むことで、その流れと背景が理解できるはずです。
普通選挙と浜口雄幸
1930年に政権を握ったのは第27代首相・浜口雄幸でした。5年前に普通選挙が成立し、有権者が一気に4倍に増加。国民の声が政治に届きやすくなり、新聞が政治と国民をつなぐ役割を果たしました。当時の日本は世界恐慌の影響で深刻な不況に陥り、国家予算の大きな部分を占める軍事費削減が課題となっていました。しかし、経済再建の思惑を超えて軍部の存在感は増していきました。
満州事変と若槻禮次郎
1931年、満州事変が突発的に起こります。首相若槻禮次郎が知った時にはすでに関東軍が行動を開始しており、止めることは不可能でした。結果として追認せざるを得ず、政府は軍部の既成事実化戦術に屈しました。1932年には満州国建国が宣言され、軍需景気により失業率は改善。新聞は国民の喜ぶ記事を積極的に掲載し、戦争拡大に世論が同調していく流れを後押ししました。
犬養毅と五・一五事件
首相犬養毅は軍の動きを警戒し、欧米との協調を重視する姿勢を貫きました。しかし1932年、五・一五事件で海軍青年将校らに暗殺されます。事件の際、犬養が語ったとされる「話せばわかる」という言葉は、民主政治が力で押し潰された象徴として語り継がれています。これを境に政党政治は大きく後退しました。
斎藤実から二・二六事件へ
後任の首相は海軍大将・斎藤実でした。ここで政党内閣は事実上終わりを迎え、軍部は国民を巻き込んだ大規模な防空演習を行うなど、社会全体を戦時体制へと誘導していきます。1936年には二・二六事件が勃発。政財界の重鎮高橋是清や斎藤実が暗殺され、軍部が政治に対して直接的な影響力を持つようになりました。
近衛文麿と日中戦争
1937年、近衛文麿が首相に就任。華族出身で国民的人気がありましたが、軍部の圧力に屈して国家総動員法を公布します。これは国民の労働や資源を戦争に総動員できる強力な法律で、日本は本格的な総力戦体制に入りました。近衛は日本放送協会のラジオを通じて国民に戦争協力を呼びかけ、国民の熱狂を引き出しました。さらに漫才師の横山エンタツ・花菱アチャコや作家林芙美子ら文化人も戦争協力に加わり、社会全体が戦時色を帯びました。近衛はドイツ・イタリアと三国同盟を結び、アメリカとの対立は決定的になります。その結果、アメリカは石油禁輸を実施し、日本は追い詰められていきました。
東條英機と太平洋戦争
1941年、後任に就いたのが陸軍大将東條英機です。就任からわずか2か月後に真珠湾攻撃を決断。世論は一気に高揚しましたが、戦局は次第に悪化。補給不足や国力差から敗戦色が濃くなり、東條は辞職に追い込まれました。国民の熱狂は急速に冷め、やがて怒りに変わっていきます。
終戦へ導いた鈴木貫太郎
戦局が最終局面を迎える中、最後に首相となったのが鈴木貫太郎でした。1945年8月15日、昭和天皇の玉音放送を国民に伝えることで戦争終結を実現。鈴木はその直後に辞任しましたが、彼の決断は日本をさらなる破滅から救ったといえます。
戦後に問われた責任
終戦後、国民の感情は戦争指導者たちへの怒りに変わりました。東條英機は東京裁判で死刑判決を受け、近衛文麿は自宅で服毒自殺しました。さらに作家の菊池寛ら文化人も戦争協力の責任を問われました。社会全体が「誰が戦争に加担したのか」を問い直し、日本は新しい時代へと踏み出していきました。
まとめ
今回の放送は、昭和初期から終戦までの首相たちの歩みを通して、日本がいかにして戦争に突き進んだのかを描き出しました。政治家、軍人、文化人、メディア、そして国民が複雑に絡み合い、熱狂と圧力の中で判断を誤り続けたことが浮き彫りになりました。現代を生きる私たちにとっても、この歴史は「熱狂が理性を奪う危険性」を示す重要な教訓です。宰相たちの決断と責任を知ることは、二度と同じ過ちを繰り返さないための第一歩だといえるでしょう。
『昭和史(半藤一利 著)』(平凡社ライブラリー)の魅力と新版の意義

『昭和史 1926-1945(戦前篇)』は、昭和史研究の第一人者である半藤一利氏が語り下ろし形式でまとめた作品です。難しい学術書とは違い、講義を聞いているようなやさしい文章で書かれており、初心者でも理解しやすい通史として高く評価されています。特に、なぜ日本が戦争へと突き進んだのかという根本的な問いに焦点を当てている点が大きな特徴です。本書は毎日出版文化賞特別賞を受賞しており、歴史書としての信頼性と社会的評価を兼ね備えています。
新版の特徴と改訂ポイント
2025年1月には新版が刊行されました。この新版では、各章ごとの要約や重要キーワードが追加され、全体像をつかみやすい構成に整理されています。さらに巻末には詳細な人名・事項索引が付けられ、調べたい人物や出来事をすぐに探せるようになりました。加えて、編集者である山本明子氏の解説が収録され、半藤氏が伝えたかった歴史の意味を現代の視点から補足する工夫もされています。これにより、学習目的でも読書としても利用しやすくなり、従来版よりも理解度が格段に高まっています。
収録内容と目次の具体例
目次を見ると、本書が扱うテーマの幅広さがわかります。例えば、「昭和史の根底には“赤い夕陽の満洲”があった」という章では、満州の存在が昭和史にどのような影響を与えたかを説明しています。「満州事変」や「軍国主義への道」、「ノモンハン事件」といった具体的な事件の流れも詳細に解説されており、読者は歴史の道筋を順を追って理解できます。また、「四つの御前会議、かくて戦争は決断された」や「太平洋戦争への道」といった章では、戦争が不可避とされた決断の過程が描かれています。
表形式に整理すると以下のようになります。
| 主な章題 | 内容の概要 |
|---|---|
| 昭和史の根底には“赤い夕陽の満洲”があった | 満州の存在が日本の進路に与えた影響を解説 |
| 満州事変 | 軍部が行動を主導し、国際的孤立を深めた経緯 |
| 軍国主義への道 | 国民と政府が軍事拡大へ進む流れを分析 |
| ノモンハン事件 | ソ連との衝突が外交と軍事に与えた影響 |
| 四つの御前会議 | 戦争開始に至る重大決定が下された経緯 |
| 太平洋戦争への道 | 日米開戦の決断までの詳細な過程 |
このように章ごとにテーマが明確で、複雑な歴史を整理して理解できるように構成されています。
今読む意義と社会的背景
2025年は「戦後80年」、そして「昭和100年」という節目の年にあたります。この記念すべき年に新版が刊行されたことは、偶然ではなく大きな意味があります。半藤氏は生前から「歴史を直視することの大切さ」を繰り返し語っており、戦争に熱狂する空気や観念論に流される危うさを強く警告していました。現代社会でも情報のあおりや集団心理が問題になる場面が多く、この本を通じて「同じ過ちを繰り返さない」ための学びを得ることができます。
まとめ
『昭和史(半藤一利 著)』は、わかりやすい語り口と深い洞察で、昭和初期から戦争に至る過程を丁寧に描いた名著です。新版によってさらに学習しやすい構成となり、歴史を学びたい人から研究者まで幅広い読者に対応できる一冊になりました。昭和史を理解するための入門書としても、改めて読み直すための資料としても最適です。昭和という時代を知ることは、未来を考えるうえで欠かせない手がかりとなります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

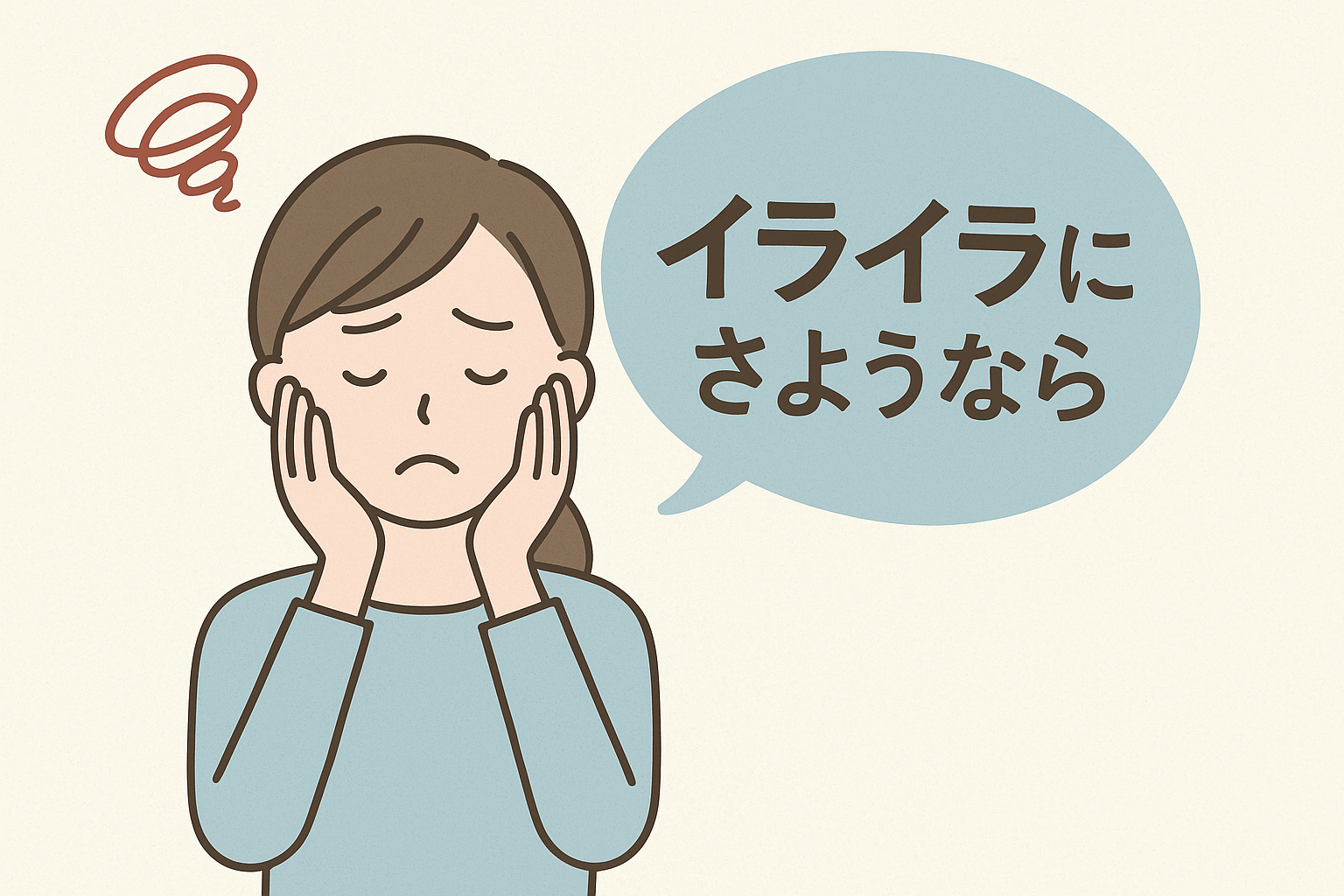

コメント