図書館が変わる!“にぎやかな図書館”が地域を動かす理由とは
「図書館って、静かに本を読む場所じゃないの?」——そう思っている人も多いでしょう。しかし、今その常識が大きく変わりつつあります。2025年10月14日放送の【クローズアップ現代】「利用者急増!“にぎやかな図書館”のヒミツ」では、全国各地で“おしゃべりOK”“子ども大歓迎”といった、新しい形の図書館が次々と生まれている現状が紹介されました。本が売れない時代、書店が減る時代に、なぜ図書館だけが人であふれているのか。そこには、地域の課題を解決し、世代を超えた交流を生み出す“仕掛け”がありました。
岐阜の奇跡“みんなの森 ぎふメディアコスモス”とは?
全国で最も注目を集める“にぎやかな図書館”の代表格が、岐阜市にあるみんなの森 ぎふメディアコスモスです。建物の中心にある巨大な木組みの天井と、まるで光の傘のような照明デザインが印象的なこの図書館。開放的で温もりある空間が、訪れる人の心をほどきます。プロデュースを手がけた吉成信夫さんは、「本の貸し借りで人がつながり、交流が起きる場を作りたかった」と語ります。
一番の特徴は“おしゃべりOK”。静けさを守ることが当たり前だった図書館の常識を覆し、子どもたちが声を出して笑い、親たちが会話を楽しむ風景が日常になりました。その結果、40歳以下の利用者がリニューアル前の22倍に急増。来館者は年間15万人から135万人にまで膨れ上がりました。
館内には静かに読書したい人のための“集中ゾーン”も併設。多様なニーズを受け入れる柔軟な空間設計が、多世代に愛される理由です。さらに、利用者同士が本を通して交流できる「BookBook交換会」、知的好奇心を刺激する「おとなの夜学」、地元の子どもたちがラジオ番組を制作するワークショップなど、年間100以上のイベントが開催されています。単なる“本の倉庫”ではなく、まちの人々が学び、語り合う“文化の交差点”となっているのです。
北から南まで広がる“地域密着型の図書館革命”
岐阜だけでなく、全国の図書館がそれぞれの地域に合わせた進化を遂げています。
北海道の札幌市図書・情報館は、働く世代に特化した“ビジネス支援型図書館”。貸出を行わず、代わりに仕事に役立つ最新の経済・経営書がずらりと並びます。館内には企業の経営相談窓口やビジネスセミナーコーナーもあり、知識と実践を結ぶ「ワーキング図書館」として人気を集めています。
一方、岩手県の紫波町図書館では、“農業支援”がテーマ。農家の高齢化や後継者不足が進む中、司書たちが自ら地域に足を運び、農業現場の声を取材し展示する取り組みを実施しています。「獣害」「物価高」「担い手不足」など、農家が抱える現実を“図書館発の発信力”で伝え、地元農業を応援しています。まさに「地域課題をともに考える図書館」へと進化しているのです。
図書館が“まちづくりの中心”に 都城市の挑戦
宮崎県都城市では、中心街の老舗デパートが閉店し、地域の空洞化が深刻化していました。そんな中、市が新たに建設したのが図書館を中核とする複合施設です。図書館の隣にはカフェ、保健センター、スーパー、ホテルを併設。日常の用事を済ませるついでに本を手に取れる動線ができ、人の流れは従来の5倍に増加しました。
さらに、市の補助制度により周辺の空き店舗への出店が活発化。この7年間で100軒以上の新店舗がオープンし、地域経済の活性化にも貢献しています。国土交通省の交付金制度を活用した「多機能型図書館」が全国に広がりつつあり、過去10年で100館を超える新しい公共図書館が誕生。
こうした施設は“週に何度も訪れる公共空間”として、地域のコミュニティづくりを支えています。
“住民が主役”の図書館も登場 高知・佐川町の物語
高知県の佐川町立図書館さくとは、住民が主体となって運営に関わる“共創型図書館”です。施設の老朽化とともに利用者が減少していた時期、町は「どうすれば人が戻るか」を住民とともに考えるワークショップを繰り返し実施。
完成した新しい図書館は、イベント企画から花壇の手入れまで地域の人々が参加する「手づくりの図書館」になりました。利用者の一人である高橋まなぶさんは、「図書館で人と出会うたびに、地域への愛着が増した」と語ります。
吉成信夫さんは番組の中で、「社会のつながりやまとまりを回復していく場所として図書館がある。人と人の関係性の豊かさが、本当の賑やかさを生む」と強調しました。図書館の“にぎやかさ”は、単なる騒がしさではなく、地域の心のつながりの象徴なのです。
若い世代を支える“心の居場所”
岐阜の図書館には、中高生が自由に悩みを打ち明けられる“相談掲示板”があります。司書が丁寧に応えるその掲示板には、これまでに2000通を超える相談が寄せられました。勉強、友人関係、将来のこと――本を介して対話が生まれ、若者たちにとって“安心できる場所”となっています。
こうした“心のよりどころ”は、家庭や学校だけでなく、地域社会全体で子どもを育てる新しい形でもあります。図書館が若い世代の居場所となることは、まちの未来を育てることにもつながります。
図書館が変える未来 地域と人をつなぐハブへ
“にぎやかな図書館”の本質は、「人が集い、考え、行動を生み出す場」にあります。静けさと賑わいが共存する空間、誰もが自然に学び、語り合える環境――そこには、地域の新しい可能性が息づいています。
これまでの“文化教養型”から、“課題解決型”へ。図書館は情報の倉庫から、社会の未来をつくる“知の拠点”へと進化しています。AIやデジタル化が進む時代だからこそ、人と人がリアルに出会える場所の価値は、むしろ高まっているのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・全国で“にぎやかな図書館”が増え、若い世代や地域住民の交流拠点になっている
・図書館が「課題解決型」「地域再生型」へと進化し、経済やまちづくりにも影響を与えている
・“静けさ”と“にぎわい”が共存する新しい公共空間が、人と地域の未来を支えている
あなたの街の図書館も、もしかしたらもう“静かな場所”ではないかもしれません。けれど、そのにぎやかさこそ、地域の元気の証。次に訪れるときは、本棚だけでなく、人の声や笑顔にも耳を傾けてみてください。
出典:NHK総合『クローズアップ現代 利用者急増!“にぎやかな図書館”のヒミツ』(2025年10月14日放送)
https://www.nhk.jp/p/close-up/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

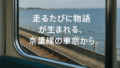
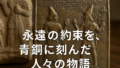
コメント