鉄よりも強かった“言葉の力” ヒッタイトが作った平和のかたち
戦争や支配の歴史の中で、“言葉”が平和を生んだ瞬間があることを知っていますか?
古代西アジアで栄えたヒッタイト帝国は、“鉄の帝国”と呼ばれる一方で、武力ではなく「記録」と「法」で国をまとめた文明でもありました。
「どうして戦いが絶えない時代に、彼らは平和を築けたのか?」この記事では、その秘密を探ります。10月15日放送の『3か月でマスターする古代文明(3)ヒッタイト “鉄の帝国”のヒミツ』では、まさにその真相が明らかになる予定です。放送前の今、ヒッタイトがどのように“文字で平和を作った”のかを整理しておきましょう。
王の言葉が国を守った ヒッタイト法のはじまり
結論から言うと、ヒッタイトの強さは“法で国を動かした”ことにあります。
古代の多くの国では、王の命令がすべてで、支配者の気分ひとつで処罰や戦争が決まることも珍しくありませんでした。けれどもヒッタイトでは、王自身も法の枠の中で統治するという考えが育っていました。これは当時としては非常に進んだ発想でした。
その礎となったのが、『テルピヌ勅令』と呼ばれる法令です。
この勅令は、王位継承をめぐる争いが絶えなかった時代に、混乱を収めるために出されたものです。
「誰が、どのような手順で王を継ぐのか」「血縁と正統性をどう守るのか」といった点を、明確な言葉で定めました。
つまり、王の地位を“神意”や“力”ではなく、“文書化されたルール”によって保障したのです。
ヒッタイトでは、これ以前に内乱や暗殺が相次ぎ、王族内の不信が高まっていました。テルピヌ王はその負の連鎖を断ち切るため、記録に基づく公正な統治を掲げました。これにより王家の安定が保たれ、国家としての秩序が再び取り戻されました。
この法令は単なる政治文書ではなく、“国を守る盾”としての役割を果たしました。
ヒッタイト人にとって“文字で残すこと”は、争いを防ぎ、未来の人々に正しい判断を託すための手段でした。
文書には「王も人であり、法の前に立つ存在である」という考え方がにじんでおり、これは後の時代の法思想にも通じる重要な一歩でした。
さらにヒッタイトでは、この勅令以降も条約や法律を粘土板に楔形文字で記録する文化が発展しました。外交文書や契約も同じく文書化され、言葉による約束を最も尊重する文明として知られるようになりました。
つまりヒッタイトの強さは、剣や鉄よりも“書かれた言葉の力”にありました。
それは人々の間に信頼を生み、王国をひとつにまとめるための見えない武器だったのです。
平和を記録した粘土板 “世界最古の条約”
ヒッタイトの“文字の力”が最も発揮されたのは、外交の場でした。
当時の西アジアは、覇権を争う強国がひしめく時代。隣国同士の戦争は日常のように起き、同盟と裏切りが繰り返されていました。そんな中で、ヒッタイトは「武力よりも言葉で国を守る」という道を選びました。彼らは外交交渉や和平の約束を、粘土板に楔形文字で記録し、相手国と正式な文書として交わしたのです。
紀元前13世紀、ヒッタイト王ハットゥシリ3世とエジプトのラムセス2世が結んだ『和平条約』は、世界で最も古い国際条約として知られています。
この条約は、長年にわたる戦争を終わらせるために結ばれたもので、両国が「互いに攻めず、同盟関係を保つ」ことを約束しました。文書には「敵が攻めてきたら助け合う」「逃亡者は保護せず返還する」といった、現代の外交条約にも通じる条項が細かく記されています。
興味深いのは、この条約が両国の言語で2種類作られている点です。
一方はヒッタイト語で書かれ、もう一方はエジプトのヒエログリフで刻まれました。互いが同等の立場であることを示すために、内容を正確に写し、両国の宮殿で保管したのです。これにより、ヒッタイトとエジプトの関係は戦争から友好へと転じ、以後は王族同士の婚姻も結ばれるほど信頼関係が深まりました。
現在、この『和平条約』の写本は、エジプトのカイロ博物館と、ヒッタイトの首都ハットゥシャ遺跡の出土資料の中に残されています。条文の一部は国際連合本部の壁にも複製として掲げられており、3000年以上前に「平和のために言葉を選んだ人々」がいた証として、現代にその精神が受け継がれています。
この出来事は、ヒッタイトが単なる軍事国家ではなかったことを物語っています。彼らは、言葉を使って信頼を築き、記録によって約束を守り続けた文明でした。
それは、剣ではなく“文字”が国をつなぐ力になるという、古代にして現代的な知恵だったのです。
金属に刻まれた約束 永遠を願う“青銅の板”
さらに、ヒッタイトは条約の中でも特に重要なものを、粘土板だけでなく青銅の板に刻むという特別な方法で残しました。これが『ハットゥシャ青銅板条約』と呼ばれるもので、ヒッタイト王トゥルハリヤ4世と、属国クルンタとの間で交わされた内容が刻まれています。
青銅という金属を選んだ理由は明確です。“永遠に残す”という意志を形にするためでした。
粘土板は焼いて硬化させても、時間が経てば割れたり崩れたりします。けれど青銅は、時を経ても腐食しにくく、王国の誓いを未来まで伝えるにふさわしい素材でした。
つまり、この条約は単なる政治文書ではなく、神々と人間の前で交わされた“永久の契約”として位置づけられていたのです。
条約の文面には、王の名とともに多くの神々の名が登場します。内容は「王トゥルハリヤ4世の後を継ぐ者たちは、この誓いを守らねばならない」「もし破ったならば、神々の怒りがその者と子孫に降りかかる」といったもので、宗教と法律が深く結びついていたことがわかります。
当時の人々にとって、条約を破ることは単なる反逆ではなく、神々への冒涜にあたりました。だからこそ、文字にするだけでなく、金属に刻んで「神々も見ている」と示すことが重要だったのです。
この青銅板は、首都ハットゥシャの遺跡から発見され、現在もトルコ・アンカラのアナトリア文明博物館で保管されています。板の大きさはおよそ45センチ×30センチほどで、表面には細かい楔形文字がびっしりと刻まれています。その姿は、まるでヒッタイトの信義と誇りを象徴するかのようです。
『ハットゥシャ青銅板条約』は、ヒッタイトが“言葉の重み”をどれほど大切にしていたかを物語ります。
粘土では儚く、紙はまだ存在しない時代に、彼らは青銅という素材で約束の永遠性を実現しました。
そしてその一枚の板が、3000年以上経った今も私たちに「信頼とは何か」を静かに語りかけています。
文字がつなぐ信頼と秩序
ヒッタイトにとって“文字”は、武器よりも確かな“信頼の証”でした。
戦争が頻発した古代の西アジアにおいて、彼らは剣や槍ではなく、粘土板に刻まれた文字で国を動かしました。条約や契約、法律を文字で残すことで、互いの立場を明確にし、誤解や裏切りを防いだのです。そうした“記録の文化”こそ、ヒッタイトを長く安定させた最大の力でした。
彼らが使っていたのは『楔形文字(けっけいもじ)』と呼ばれる書記体系です。もともとはメソポタミアで誕生した文字でしたが、ヒッタイト人はそれを自国語に取り入れ、外交・宗教・法律などあらゆる分野に活用しました。粘土板に刻まれた文字は、単なる情報ではなく“国と国をつなぐ橋”でした。
ヒッタイト王国は他民族を多く抱える国家だったため、文書はしばしばアッカド語やヒュッリ語など、複数の言語に翻訳されました。相手の言葉で書かれた条約を交わすことで、どの国も内容を正確に理解でき、対等な関係を築けたのです。これは、現代の国際条約や外交文書の原型ともいえる仕組みでした。
文字を持つことは、単に“記録する力”だけでなく、“信頼を証明する力”でもありました。
たとえば、ヒッタイト王が属国の王と同盟を結ぶとき、その条約文書は双方の神々の名において誓われました。文字に残された約束を破ることは、神への背信とみなされ、国家の恥とされたのです。文字は、約束の重みと誠実さを保証する手段でした。
このように、ヒッタイトは“言葉を刻む文明”として発展しました。
鉄の剣は時が経てば錆びますが、文字は数千年後の私たちにまで残り、当時の人々の考えや願いを伝えています。
「鉄よりも強いものは、信頼を築く言葉の力である」――ヒッタイトの歴史は、その事実を静かに証明しています。
まとめ:言葉が平和を作る、それがヒッタイトの知恵
ヒッタイトの文明は、鉄ではなく“記録”で世界を動かした国でした。争いを法で防ぎ、文字でつながり、信仰で守った。その哲学は、今の国際社会にも通じるものがあります。
この記事のポイントは以下の3つです。
・ヒッタイトは文字と法で国をまとめた“秩序の文明”だった
・世界最古の『和平条約』を残したことで、外交史の礎を築いた
・青銅板や楔形文字が“永遠の信頼”の証となった
今の時代にも、ヒッタイトのように“対話と記録”を重んじる姿勢が必要です。
どんな時代でも、平和は武器ではなく言葉から始まる――そのことを、彼らの歴史が教えてくれます。
(番組:『3か月でマスターする古代文明(3)ヒッタイト “鉄の帝国”のヒミツ』NHK Eテレ 2025年10月15日放送)
ソース:NHK公式サイト https://www.nhk.jp/p/ts/GVJ6VP2L8P/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


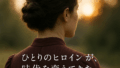
コメント