めまい・息切れ・だるさ…それって『貧血』かも?薬と食事で変わる体のサイン
最近、「なんだか疲れやすい」「立ち上がるとふらっとする」「動悸が気になる」と感じることはありませんか?それ、もしかしたら貧血のサインかもしれません。特に女性の多くが悩まされているのが『鉄欠乏性貧血』。自覚がないまま進行するケースも多く、放っておくと心臓や脳にまで影響することもあるのです。
2025年11月2日放送予定のNHK「チョイス@病気になったとき」では、『貧血の最新治療法 薬・食事で改善』と題して、健康診断から分かる初期サインや最新の治療薬、そして家庭でできる食事改善のポイントが紹介されます。この記事では放送前の時点で分かっている情報を、専門的な視点からやさしく解説します。読めば、「なんとなくだるい」の正体が分かり、体を守る行動が見えてくるはずです。
【あしたが変わるトリセツショー】“カチカチ心不全”に要注意!心臓を守る歩き方と生活習慣
健康診断で気づく『かくれ貧血』のサイン
貧血とは、血液中の酸素を運ぶヘモグロビンが減ることで、体が十分な酸素を受け取れなくなる状態です。特に女性では、月経や妊娠・出産などで鉄を失いやすく、知らないうちに貧血が進行することがあります。
健康診断でまず見るべきはヘモグロビン(Hb)値。成人女性で12g/dL未満なら貧血が疑われます。ただし、ヘモグロビンがギリギリ正常でも油断は禁物。次に注目したいのが、赤血球の大きさや色の指標であるMCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)、MCHC(平均赤血球血色素濃度)です。これらが低い場合は、赤血球が小さく、色の薄い「小球性低色素性貧血」である可能性が高く、鉄欠乏によるものと考えられます。
さらに重要なのがフェリチン。これは体内の“貯蔵鉄”の量を示す指標で、正常でも20ng/mL以下なら、体の中の鉄がすでに枯渇しかけている可能性があります。つまり、血液中に出てくる鉄が足りないため、将来的に貧血を起こしやすい状態です。いわば「隠れ貧血」のサインといえるでしょう。
血液検査では他にもTIBC(総鉄結合能)やトランスフェリン飽和率(TSAT)といった値があります。鉄欠乏が進むと、体が鉄を運ぶたんぱく質であるトランスフェリンを増やすため、TIBCは上昇し、逆にTSATは低下します。これらの数値を総合的に見ることで、貧血のタイプを正確に把握することができます。
自覚症状が軽くても、数値のわずかな変化が体の不調につながることがあります。「疲れやすい」「頭が重い」「朝から動けない」と感じるときは、まず健康診断の結果を見返し、フェリチンやMCVの値を確認することが第一歩です。
最新の治療法と薬の選び方
貧血の原因が鉄不足である場合、治療の基本は「鉄を補うこと」です。最初に行われるのが経口鉄剤による治療です。代表的な薬には、フェロミア(クエン酸第一鉄ナトリウム)、フェルム(フマル酸第一鉄)、フェロ・グラデュメット(乾燥硫酸鉄)などがあります。これらは医師の処方で服用し、体の中に少しずつ鉄を補給します。
服用の際に注意したいのは、副作用。鉄剤は胃腸への刺激が強く、便秘・吐き気・胃のムカつき・便の黒化などが見られることがあります。こうした症状が出た場合は、量を調整したり、胃薬と一緒に飲むなどの工夫をすることで軽減できます。
症状が重い場合や、消化器の病気などで経口鉄剤を吸収できないときには、注射による鉄補充(静脈注射)が行われます。静脈鉄剤は血液中に直接鉄を補うため、即効性があり、短期間で効果が出やすいのが特徴です。最近では副作用が少ない新しい注射鉄剤も登場しており、治療の選択肢が広がっています。
医師の多くは「ヘモグロビンが正常になってもすぐにやめないこと」を強調します。なぜなら、体の中の鉄貯蔵庫=フェリチン値が回復するまでには時間がかかるからです。途中でやめてしまうと、再び鉄が不足して貧血が再発するリスクが高くなります。治療は「数値の改善」ではなく「体の中の鉄を戻すこと」を目標に続けることが大切です。
鉄を補う食事の工夫とポイント
薬と並んで大切なのが、毎日の食事です。鉄は食材からも摂取できますが、吸収率には大きな違いがあります。
まず、吸収されやすいのはヘム鉄。これは動物性食品に含まれる形の鉄で、豚レバー(100gで約20mg)、牛赤身肉、あさりの水煮缶(100gで約30mg)などが代表的です。これらは吸収率が高く、効率よく鉄を体に取り入れられます。
一方で、植物性食品に含まれるのは非ヘム鉄。ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆、納豆などに多く含まれますが、吸収率は動物性の約10分の1ほど。ただし、ビタミンCを一緒に摂ることで吸収率を高めることができます。たとえば、レモン汁をかけたり、トマトやブロッコリーを添えたりするのが効果的です。
また、鉄の吸収を妨げるものもあります。コーヒーや紅茶に含まれるタンニン、玄米や豆類のフィチン酸、食物繊維の取りすぎなどです。これらは食後すぐに摂取せず、時間をずらすことで影響を減らせます。
食事では、「主食・主菜・副菜」をバランスよく組み合わせることが基本。鉄はたんぱく質・ビタミンB群・葉酸とセットで働くため、肉や魚、野菜をまんべんなく取り入れると良いでしょう。特に成長期の女性や妊婦、授乳中の方は鉄の需要が高く、意識して摂取することが推奨されています。
見逃してはいけないサインと隠れた病気
貧血の怖さは、「症状が軽いまま進むこと」。初期は「なんとなくだるい」「立ちくらみがする」といった小さな違和感から始まり、進行すると「動悸」「息切れ」「顔色の悪さ」「爪が反り返る」「氷をかじりたくなる」など、さまざまな症状が出てきます。
しかし、貧血の背景には別の病気が潜んでいることもあります。女性では子宮筋腫や子宮内膜症、子宮がんによる出血が原因のこともあり、月経が多い、期間が長いと感じるときは婦人科の受診が勧められます。
男性や閉経後の女性の場合は、胃潰瘍・ポリープ・胃がん・大腸がんといった消化管出血が原因で鉄が失われることもあります。こうしたケースでは、内視鏡検査などで原因を確認することが重要です。
貧血を放置すると、体の酸素運搬能力が下がり、心臓への負担が増します。動悸や息切れが慢性化し、心不全や脳の機能低下を招く危険性もあります。高齢者では特に気づきにくく、知らないうちに進行していることもあるため、早めのチェックが欠かせません。
まとめ
この記事では、貧血の兆候から治療、食事改善までを紹介しました。最後にポイントを整理しましょう。
・健康診断ではヘモグロビンとフェリチン値の両方をチェックする
・経口鉄剤・注射鉄剤を正しく使い分け、途中でやめずに治療を続ける
・鉄を多く含む食材(レバー・あさり・赤身肉など)を取り入れ、ビタミンCで吸収を高める
・コーヒー・紅茶・玄米などの摂取タイミングに注意する
・「疲れやすい」「動悸がする」などの症状を軽く見ず、早めに検査を受ける
貧血は放っておくと全身のバランスを崩す病気ですが、早めに気づけば確実に改善できます。北里大学の鈴木隆浩教授による放送内容では、さらに最新の治療薬や食事療法のポイントが紹介される予定です。あなたの体が出す小さなサインを見逃さず、今からできるケアを始めましょう。
番組の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

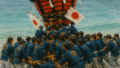

コメント