SNSと高齢者の関係を探る「最深日本研究
高齢者がSNSを使う意味や効果に関心を持っている方は多いです。「おじいちゃんやおばあちゃんにSNSは難しいのでは?」「高齢者がSNSを使うと孤独は減るの?」「危険性はないの?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。この記事では、2025年8月17日に放送されたNHK総合「最深日本研究〜外国人博士の目〜“SNS×高齢者”を知りたい」をもとに、番組で紹介された研究内容や事例を整理しました。読めば、日本の高齢社会でSNSがどのように役立つのかがよくわかります。
高齢者とSNSの課題
日本は世界有数の高齢化社会として知られています。長寿大国とも言われますが、その一方で、高齢者の暮らしにはさまざまな課題が潜んでいます。特に大きな問題の一つが、家族と離れて暮らす高齢者が増えているという現実です。子ども世代が都市部に移り住み、親世代は地方や郊外に残るケースも多く、その結果として日常の中で孤独を感じる場面が少なくありません。
また、現代の情報社会を支える存在となったSNSは、どうしても若い世代が中心のツールと見られがちです。「高齢者には難しそう」「本当に使いこなせるのだろうか」といった不安や先入観を持つ人も多いのが現実です。そのため、高齢者がSNSを使うこと自体に抵抗感を覚える家庭もあり、利用をためらうケースも少なくありません。
こうした状況に対して、周奕辰さんの研究は非常に意義深いものです。周さんは、高齢化が進む日本社会の中で、高齢者とSNSの関わりを丁寧に調べています。高齢者自身がどのように感じ、どう受け止め、実際にどのような使い方をしているのか。こうした問いに正面から向き合い、質的研究を通じて明らかにしようとしているのです。
もしこの問題を放置すれば、孤独感の増加や社会的なつながりの喪失といった深刻な影響が広がっていく可能性があります。それは一人の高齢者だけの課題にとどまらず、社会全体に関わる大きなテーマです。人と人とのつながりが薄れることで地域の活力が失われたり、健康や精神面にも悪影響が及ぶ可能性があるからです。その意味で、SNSと高齢者の関係を探る研究は、これからの日本にとって欠かせない取り組みだといえます。
番組で語られた結論のポイント
番組を通じて示された結論はとても明快でした。つまり、SNSには高齢者の社会的つながりを広げる大きな効果があるという点です。これまで高齢者は「家族や近所との関係が薄れていくのは仕方ない」と思われがちでしたが、SNSという新しい道具が加わることで、その常識が変わりつつあります。
特に日本社会では、家族の距離感が欧米に比べてやや遠い傾向があると指摘されます。親子やきょうだいであっても、生活の拠点が離れていることが多く、会える回数も限られがちです。そこでSNSを介することで、日常の出来事を気軽に共有できたり、写真やメッセージを通じて「つながっている安心感」を持てるようになります。
さらに、SNSは家族だけでなく地域の人や友人とも関係を保つ手段になります。例えば、昔の同級生との再会や、地域活動の情報交換、趣味のグループでの交流など、これまで諦めていたつながりを再び取り戻すことも可能です。番組では、そうした可能性を実際の事例を交えて紹介しており、SNSが高齢者の生活をより豊かにする大切な役割を果たしていることが伝えられました。
周奕辰さんの研究アプローチ
番組に登場した周奕辰さんは、東京大学大学院に所属するコミュニケーション学の研究者です。彼の研究スタイルは「質的研究」と呼ばれる方法で、単なる数値データではなく、対象者と直接向き合い、丁寧なインタビューを通じてその人の心理や行動の背景を深く掘り下げていくのが特徴です。
実際に周さんは、千葉県柏市で高齢者と一緒にワークショップを行い、SNSに対する考え方や利用状況を観察しました。また、東京・文京区では高齢者に個別インタビューを行い、どのようにSNSを日常生活に取り入れているのかを詳しく調査しました。これにより、数字では見えない「高齢者の本音」や「生活に根ざした使い方」が浮かび上がったのです。
さらに周さんは、日本社会の独特な文化にも注目しました。例えば「日本人は紙が好きで、どんな情報もプリントして残す」という点です。これは手帳や印刷物を大切にする習慣に表れており、デジタル時代になっても根強く残っています。周さんは、このような文化的背景とSNSの活用が両立していることを紹介し、紙文化とデジタル文化が共存する日本ならではの特徴として強調していました。
海外研究との比較
番組では、欧米の研究事例も取り上げられました。そこでは、SNSが家族と離れて暮らす高齢者の交流を増やす効果があるという結果が示されており、日本の状況とも大きく重なります。物理的に距離があっても、オンラインを通じて日常を共有できることが、高齢者の安心感や生きがいにつながることが分かってきたのです。
さらに、周さん自身の故郷・中国安徽省の黄山にまつわるエピソードも紹介されました。彼の祖母は亡くなるまで黄山で暮らし続けましたが、その姿は「地元のコミュニティに根ざした生活」と「SNSによって広がる交流」を重ね合わせて語られました。周さんは、自身の家族の経験と研究対象である日本の高齢者を対比させながら、SNSの持つ普遍的な価値を伝えていたのです。
特に日本の場合、家族関係の特徴として“親密すぎない距離感”が挙げられます。欧米のように頻繁に直接交流するのではなく、一定の距離を保ちながら関係を続けるのが一般的です。そのため、SNSのように「つながりすぎず、ほどよい距離感を保ちながら交流できる」手段は、特に日本の高齢者にとって大きな意味を持ちます。孤独を和らげるだけでなく、文化的な背景に合ったコミュニケーション手段としてSNSが機能していることが強調されました。
実際の高齢者のSNS活用事例
番組で紹介された高齢者の事例は、とても印象深く心に残るものでした。
まず一人目は、東京・新橋で暮らす男性です。彼は生成AIの音声認識機能を活用し、自らの半生を振り返った自伝の執筆に挑戦していました。これまでは手書きやタイピングでは負担が大きかった作業も、声に出して話すだけで文字に変換される仕組みを利用することでスムーズに実現できるようになったのです。AI技術を取り入れることで、自分の思い出を次世代に残すという大きな夢を叶えていました。
もう一人は、定期的にリモート女子会を開いている女性です。仲の良い友人たちとオンラインで集まり、おしゃべりや情報交換を楽しんでいる様子はとても生き生きとしていました。外出が難しい時でも、SNSやオンラインツールを通じて人と関わり続けることができ、日々の楽しみや生きがいにつながっています。
これらの事例は、単なる「便利な道具」としてのSNSにとどまらず、高齢者の暮らしそのものを豊かにする可能性を強く示しています。周奕辰さんも「日本の高齢者の想像力は豊か」と語り、テクノロジーを柔軟に取り入れながら新しい生活スタイルを築いている姿勢を高く評価しました。SNSやAIは、単なる連絡手段を超えて、人生をより充実させる大切な道具になりつつあることが伝わってきました。
専門家の意見
番組には東京大学の牧野篤教授も登場し、高齢者がSNSを利用することの社会的な意味について丁寧に解説しました。牧野教授は、単に「若者文化を真似る」という視点ではなく、SNSが高齢者にとって孤独を和らげる役割や、社会との接点を保ち続ける重要なツールになっている点を強調しました。
さらに、番組は視点を広げ、シンガポール国立大学のタン准教授の意見も紹介しました。タン准教授は「SNS利用は高齢者の生きがいにつながる」と語り、SNSが単なる交流手段にとどまらず、日常に張り合いや活力をもたらすことを指摘しました。趣味の共有やコミュニティ活動への参加が、心身の健康や長寿にも良い影響を与えるとされ、その価値は日本だけでなく国際的にも共通するものだと説明しました。
これらの専門家の意見を総合すると、SNSは世界中で高齢者の生活を支える可能性を秘めたツールであることが浮き彫りになります。地域や文化が違っても、年齢を重ねた人々が「人とのつながり」を求める気持ちは同じであり、その架け橋としてSNSが機能していることが裏付けられたのです。
高齢者がSNSを活用するための工夫
番組の内容を踏まえると、高齢者が安心してSNSを活用するためには、いくつかの工夫がとても有効であることがわかりました。
まず、基本的な工夫として文字を大きく表示する設定があります。スマホやタブレットには文字サイズを調整する機能が備わっているので、小さな文字が読みにくい高齢者でも無理なく画面を見ることができます。視認性を高めるだけで、操作のハードルはぐっと下がります。
次に大切なのは、家族や地域の人が一緒に教えてサポートすることです。新しい技術は一人で学ぶのは不安が大きいですが、身近な人が横で教えてくれると安心感が生まれます。親子や孫との交流のきっかけにもなり、「一緒に覚える楽しさ」がモチベーションにつながります。
また、定期的にオンライン交流会を開くのも効果的です。リモート女子会や趣味のサークルなど、顔を見ながら話せる場を持つことで、日常的にSNSを使う習慣が自然に身につきます。孤独を和らげ、生活に張り合いを与える大きな力となります。
さらに、紙にメモを残すといった従来の習慣と併用することも、日本ならではの工夫です。操作方法やパスワードを紙に書いて手元に置いておけば安心でき、紙文化を大切にしてきた高齢者にとって心理的な負担も減ります。
こうした工夫を組み合わせれば、SNSは高齢者にとって「難しいもの」ではなく、日常を豊かにし、人とのつながりを広げる大切な味方になっていきます。
よくある質問(FAQ)
Q:高齢者がSNSを使うのは危険では?
A:詐欺や情報流出のリスクはありますが、使い方を学び家族や地域で見守れば安全に利用できます。
Q:SNSを使うメリットは?
A:孤独感の軽減、趣味や興味の共有、新しい生きがいの発見などが挙げられます。
Q:紙文化とSNSは両立できる?
A:できます。周さんの指摘どおり、プリントアウトや手帳とSNSを併用する人も増えています。
まとめ
今回の放送から見えてきたのは、SNSは日本の高齢者にとって孤独を防ぎ、生活を豊かにする有効な手段であるということです。周奕辰さんの研究や高齢者の具体的な事例を通して、SNSが単なる若者の道具ではなく、誰にとっても可能性のあるものだとわかりました。これからの社会において、高齢者が安心してSNSを楽しめる仕組み作りがますます重要になっていくでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

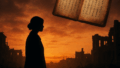

コメント