“復興のシンボル”パンダを守れ〜神戸の動物園が起こした奇跡〜
阪神・淡路大震災から立ち上がろうとする神戸で、多くの市民を励まし続けたのがパンダのタンタンでした。番組「新プロジェクトX」では、神戸市立王子動物園のスタッフが24年にわたり奮闘し、世界的にも前例のない治療や取り組みを実現した感動の記録が描かれました。この記事では、タンタンと動物園スタッフの挑戦をすべて振り返り、どのように「希望の星」が守られてきたのかを詳しく紹介します。
阪神・淡路大震災と神戸にやってきたパンダ
1995年1月17日、阪神・淡路大震災が神戸を直撃し、街は一瞬にして壊滅的な被害を受けました。建物は倒壊し、道路や鉄道などのインフラも寸断され、人々の生活は大きく揺さぶられました。中でも、多くの命が失われたことで市民の心には深い傷が残りました。震災直後、王子動物園の敷地内には遺体安置所が設けられ、多くの遺族が大切な人を探し、悲しみに包まれる光景が広がっていたのです。動物園は本来、子どもや家族が笑顔で訪れる場所でありながら、その時は涙と絶望に覆われていました。
そんな悲しみの中から立ち上がろうとする神戸の人々のもとに、2000年7月16日、新たな希望の象徴として中国からやってきたのが2頭のパンダ、コウコウとタンタンでした。この2頭のパンダは、震災復興のシンボルとして特別な意味を持ち、人々の大きな期待を背負って神戸に迎えられました。
パンダの名前は市民の公募によって決められ、誰もが親しみを込めて呼べるようにと願いが込められていました。一般公開の日には、待ちわびていた大勢の市民が王子動物園に足を運び、パンダたちの姿をひと目見ようと長蛇の列を作りました。その光景は震災で失われた笑顔を取り戻す瞬間でもあり、見に来た人々の表情には自然と笑みが広がっていったのです。
震災で心に深い傷を負った人々にとって、コウコウとタンタンは単なる動物以上の存在でした。彼らは「生きる希望」であり、再び前を向いて歩き出す勇気を与えてくれる存在として、神戸市民に強く愛されていったのです。
経験ゼロからの挑戦と繁殖の試み
当時、飼育員の兼光秀泰と同僚は、なんとパンダの飼育経験がまったくありませんでした。にもかかわらず、彼らに与えられた使命は「中国からの大切な借り物であるパンダを必ず守り抜くこと」でした。その責任は非常に重く、もし失敗すれば国際問題に発展しかねない緊張感の中で、彼らは一から知識と技術を学び、手探りで日々の世話に励んでいったのです。
やがて新たに課せられた挑戦は、さらなる困難を伴うものでした。それはパンダの繁殖です。世界的に見ても繁殖は難しいとされ、成功するには高度な専門知識と経験が必要でした。しかし、神戸の動物園スタッフは諦めることなく、資料を読み込み、試行錯誤を重ねながら挑戦を続けました。
その長年の努力の結晶として、2008年についに赤ちゃんパンダが誕生しました。市民も職員も大きな喜びに包まれ、「神戸に新しい命が生まれた」と感動に沸きました。けれどもその幸せは長く続きませんでした。赤ちゃんはわずか4日で命を落としてしまい、園内は再び深い悲しみに包まれたのです。
追い打ちをかけるように、2010年にはオスのコウコウが急死してしまいました。震災からの復興の象徴として期待を背負ってきた存在が次々と失われる中、動物園に残されたのはタンタン1頭だけ。そこから彼女の、孤独と向き合いながら生きる日々が始まったのです。
食のこだわりと「偽育児」の苦しみ
タンタンには他のパンダにはあまり見られない独特の習性がありました。特に夏になると「偽育児」と呼ばれる行動をとり、本当は赤ちゃんがいないのに子どもを抱えているように振る舞い、食事をほとんど取らなくなってしまうのです。この状態が続くと免疫力が低下し、健康に深刻な影響を及ぼす恐れがありました。
さらに困難だったのは、タンタンの食に対する強いこだわりです。普段から竹の好みが非常に細かく、少しでも気に入らない種類だと全く手を付けずに残してしまうことも珍しくありませんでした。飼育員にとっては、彼女の体調を守るために「食べてくれる竹をどう確保するか」が大きな課題となっていったのです。
そんな状況で力を発揮したのが、飼育担当に加わった吉田憲一でした。もともと造園の専門家であった吉田は、これまでの経験と知識を活かして園内に数多くの竹を植え、種類ごとにタンタンの反応を徹底的に観察・分析しました。竹の香りや硬さ、季節ごとの鮮度など、細かい要素をひとつずつ調べ上げ、タンタンが好む竹を突き止めていったのです。
その結果、タンタンは再び食欲を取り戻し、体調も回復に向かいました。吉田の工夫と努力は、パンダと人との信頼関係を築くだけでなく、命を支える大きな力となったのです。
世界初の挑戦「ハズバンダリートレーニング」
次の大きな転機をもたらしたのは、飼育員の梅元良次による新しい発想でした。彼が掲げた目標は「人間並みの健康診断をパンダに行う」という、当時としては前例のない挑戦です。これまでパンダの検査や治療は、動物に大きな負担をかける全身麻酔に頼ることが多く、命のリスクとも隣り合わせでした。そこで梅元は、動物が自ら協力して診察を受けられるようにする方法を模索し、たどり着いたのがハズバンダリートレーニングでした。
ハズバンダリートレーニングとは、動物に少しずつ動作を覚えさせながら医療行為を可能にする仕組みです。梅元はタンタンの大好物であるリンゴを報酬にして、一歩ずつ信頼関係を築いていきました。例えば、合図に合わせて腕を出すとリンゴを与える、その動作を繰り返しながら採血の手順を覚えさせるという具合です。こうしてタンタンは強制的に抑え込まれることなく、安心して検査に協力できるようになっていきました。
その積み重ねの末、タンタンは採血やレントゲン検査、心臓のチェックなど10種類を超える医療行為に対応できるようになりました。これは世界的に見ても初めての成功例であり、中国の専門家からも「こんな方法が実現できるとは」と驚きをもって受け止められました。梅元の粘り強い努力は、タンタンの長寿と健康を守る大きな支えとなり、同時に動物医療の新たな可能性を切り開くものとなったのです。
心臓疾患との闘い
25歳を過ぎた頃、長年市民に愛されてきたタンタンの体に異変が見つかりました。診断の結果は心臓疾患。高齢のパンダにとっては命に関わる重大な病気であり、すぐに獣医師の菅野拓を中心とした医療チームが結成されました。しかし、中国の専門家に相談したところ返ってきたのは「心臓疾患の有効な治療法は確立されていない」という厳しい答えでした。現実は想像以上に厳しく、チームは大きな壁に直面することになったのです。
やがて病状は進行し、タンタンの体には腹水がたまり始めました。お腹が張って食欲も落ち、命の危機がすぐそこまで迫っていました。本来なら腹水を抜くために全身麻酔を施す必要がありますが、高齢のタンタンにはそのリスクが非常に高く、命を落としかねません。そこで梅元たちは思い切った決断を下しました。それは、全身麻酔を使わずに腹水を抜くという、世界でも前例のない挑戦でした。
成功の鍵となったのは、これまで積み重ねてきたハズバンダリートレーニングと、タンタンが好んで飲んでいた赤ちゃん用ミルクでした。治療中、タンタンがミルクに夢中になっている間に局所麻酔で処置を行い、ついに腹水を安全に抜くことに成功したのです。この奇跡的な施術によってタンタンの体調は一時的に回復し、再び大好きなタケノコを口にできるほどになりました。
この取り組みは、世界的に見ても画期的な出来事とされ、中国の専門家をはじめ多くの研究者から驚きと称賛の声が寄せられました。梅元たちの勇気ある挑戦と、タンタンとの深い信頼関係があったからこそ成し得た、大きな一歩だったのです。
市民との絆と「ひまわりの花」
治療のため観覧中止が続き、市民が直接タンタンに会えない日々が続いていました。しかし「支えてくれた人々に少しでも感謝を伝えたい」という思いから、動物園スタッフは新しい試みを始めます。それが、パンダ舎の屋上にひまわりを植える取り組みでした。
このひまわりには、タンタンの排泄物を肥料として利用する工夫がされており、「タンタンとつながっている花」として育てられました。鮮やかに咲き誇るひまわりは、会えなくても市民に希望と元気を届ける象徴となり、多くの人々がその姿に励まされました。
その後もスタッフの献身的なケアと医療チームの尽力により、タンタンは高齢とされる年齢を大きく超えて生き続けます。そしてついに28歳を迎えました。これは人間に換算するとおよそ100歳近い長寿にあたり、世界的に見ても非常に稀なケースでした。
最期の時までスタッフに見守られながら、タンタンは穏やかにその一生を終えました。その姿は「希望の星」として神戸の人々の心に深く刻まれ、震災を乗り越えて歩んできた街の記憶と重なり続けています。
最後の日と市民の感謝
2024年4月、長年市民に寄り添い続けたタンタンが静かに息を引き取りました。知らせが伝わるとすぐに王子動物園には献花台が設けられ、そこには全国から大勢の人々が訪れました。その数はおよそ20万人にのぼり、花や手紙、そして感謝の言葉が絶え間なく捧げられました。人々にとってタンタンはただのパンダではなく、震災からの歩みを共にしてきた「希望のシンボル」だったのです。
さらにその後、SNS上には「タンタンのひまわり」の写真が次々と投稿されました。動物園で配られた種を受け取った人々が育てたひまわりが各地で咲き誇り、その姿がシェアされることで、タンタンの存在は命のつながりとなって広がっていきました。ひまわりの花は、タンタンが残した優しさと希望を象徴するものとして、人々の心の中で生き続けています。
まとめ
パンダのタンタンは、震災からの復興のシンボルとして、神戸の人々に希望を与え続けました。そして動物園スタッフの24年にわたる努力と挑戦が、彼女の長寿と穏やかな最期を支えました。医療技術の革新だけでなく、「動物と人との絆」がどれほど強い力を持つのかを証明した物語です。この記事を読んで、神戸のパンダと人々の歩みを思い出し、命を守る挑戦の大切さを感じていただけたらと思います。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

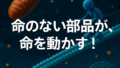
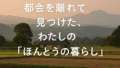
コメント