具志堅用高とその一族が語る沖縄100年の歴史と誇り
2025年5月16日(金)22:30〜NHK総合で放送された『時をかけるテレビ』では、池上彰さんが案内役を務め、1979年のNHK特集「わが沖縄〜具志堅用高とその一族〜」を振り返りました。沖縄初の世界チャンピオン・具志堅用高さん本人をスタジオに迎え、一族の歩みと沖縄の激動の歴史が重なるドキュメンタリーの再発見が行われました。
琉球王国の末裔・具志堅一族の壮絶な歴史
具志堅用高さんの家族は、かつて琉球王国に仕えていた士族の家系です。王国時代には役人として誇り高く生きていましたが、明治12年の「琉球処分」によって琉球王国は消滅し、沖縄県として編入されました。この政策により、具志堅一族も地位と収入を失い、生活の基盤が崩れました。没落した一族は、本部町をはじめとする沖縄各地に散らばり、新しい土地で生きていくことを余儀なくされました。
-
職を失った旧士族たちは、農業や漁業に従事する生活へと移行
-
沖縄本島だけでなく、離島や遠方の地域へも移住が進行
-
移住先での生活は厳しく、日々の糧を得ることに必死でした
その後、明治31年には徴兵令が沖縄にも適用され、一族の多くが軍へ入隊します。中でも、具志堅さんの祖父・用高(おじ)は明治44年に徴兵されました。当時、沖縄の若者たちは標準語をほとんど話せず、軍隊内での意思疎通も困難でしたが、用高は銃剣術で抜群の腕前を見せ、部隊内で特に評価される存在となりました。言葉が通じなくても、武技で信頼を得るその姿勢は、一族の誇りとして語り継がれています。
-
言葉が通じない環境でも技能を認められた用高
-
努力と誇りで旧士族の精神を貫いた一例
時代は昭和に入り、沖縄の経済状況はさらに厳しくなります。そこで、多くの沖縄出身者が南洋群島(パラオ、サイパンなど)へ移住しました。具志堅一族の中にも、そうした場所での漁業に従事する人々が増えました。南洋での漁師の稼ぎは当時としては非常に高く、一時は沖縄県知事の年収を超えるほどの収入を得る者もいたとされています。
-
南洋への移住は生活再建のための大きな決断
-
遠く離れた異国の海で命がけで漁に出る日々
-
稼いだお金を沖縄の家族に送金し、故郷を支える人も多かった
しかし、太平洋戦争の勃発により、そのような生活も一変します。移住先の南洋諸島も戦場となり、多くの民間人が巻き込まれることになりました。具志堅一族の中にも、多数の戦死者が出ました。その数は、一族全体の4分の1にも及ぶほどで、家族の再会が叶わぬまま命を落とした人も少なくありません。
-
サイパン、パラオ、ボルネオなどでの戦闘により犠牲者多数
-
住んでいた島からの避難や強制収容を経験した家族もいた
-
一族の歴史の中でも、もっとも過酷な時代となりました
こうした戦争や移住、徴兵の記録は、具志堅用高さんの背景にある「生き抜く力」と直結しています。王国時代から続く誇りを胸に、幾多の苦難を乗り越えてきた一族の歩みこそが、彼の原点です。個人の活躍の背後には、常に家族と歴史の支えがあったことが、この物語を通して浮かび上がってきます。
戦後の苦難と復興、そしてチャンピオンの誕生
終戦後、具志堅用高さんの一族が長年暮らしていた沖縄・崎原の地は米軍に接収され、故郷は廃村となりました。3代にわたって守り続けてきた土地を失い、家も墓も移転を余儀なくされ、一族は新たな生活を強いられることになります。失ったのは住まいだけでなく、心のよりどころである“帰る場所”そのものでした。復興の兆しが見えない中でも、家族は地道に働き、日々を積み重ねていきました。
-
土地の接収により家族の拠点が消失
-
墓も移さざるを得ず、祖先とのつながりも揺らいだ
-
戦後の沖縄は経済的にも厳しく、食料や仕事にも困る生活
沖縄がようやく本土に復帰したのは1972年。それからわずか2年後、具志堅さんは大きな決断をします。**1974年、沖縄から上京してプロボクサーの道を選んだのです。**高校時代にはオリンピック候補としても注目されていましたが、彼が選んだのは「金メダルよりカネ」という現実的な選択でした。当時の沖縄の経済事情を考えれば、この判断には重い意味があったといえます。
-
協栄ボクシングジムに所属し、東京でトレーニングに励む
-
1976年、WBA世界ジュニアフライ級王座を獲得
-
以後、13度の防衛を果たし、日本ボクシング史に名を刻む
このような偉業の背景には、家族の力強い支えがありました。母のツネさんは沖縄・久高島の出身で、父・用敬さんは岐阜の工場で働いた後に沖縄へ戻り、カツオ漁師として家族を養ってきた人物です。二人は出稼ぎ先で出会い、厳しい時代を共に生き抜きました。具志堅さんが地元・石垣島に新築の家を建てることができたのも、こうした家族の努力と犠牲の上に成り立っていたのです。
-
ツネさんは明るく、強い母親として子どもを支えた
-
用敬さんは働き者で、若いころから本土で労働に励んだ
-
一家の夢がかなった時、それは一族全体の誇りでもあった
さらに、具志堅さんの試合が沖縄の伝統行事・清明祭と重なることもありました。この祭りは祖先を敬い、墓前で家族が集まる大切な日。試合当日、一族は墓前に集まり、彼の勝利を祈って手を合わせていた様子が映像でも紹介されています。その姿からは、スポーツを超えた精神的な絆や、地域全体が具志堅さんに託した願いが伝わってきます。
-
清明祭は沖縄文化に根ざした祖先崇拝の象徴的な日
-
墓前で手を合わせる姿は、家族と歴史のつながりの証
-
試合の勝利は、一族と郷土全体の喜びとなった
こうして、具志堅用高さんはただのボクサーではなく、沖縄という土地の記憶と希望を背負った存在となりました。復興の道を歩んできた家族とともに、リングの上で沖縄の魂を体現し続けたその姿は、多くの人々の心に深く刻まれています。
9度目の防衛戦と一族の思い
1979年7月29日、福岡県小倉市で行われた具志堅用高さんの9度目の世界タイトル防衛戦は、一族にとって特別な意味を持つ一日でした。対戦相手は世界ランキング1位のラファエル・ペドロサ選手。過去の対戦相手とは一線を画す実力者との一戦に、具志堅さんは並々ならぬ覚悟で臨みました。
この試合の日、具志堅一族は全国各地から集まり、それぞれの場所でテレビの前に陣取り試合を見守りました。沖縄本島はもちろん、本部町、石垣島、名護市、横浜、大阪、岐阜などに暮らす親族が、同じ時間に同じ思いで応援するという、一族の絆を象徴するような時間が生まれていました。
-
試合は終始接戦となり、緊張感のある展開が続いた
-
判定の結果、具志堅さんが見事防衛に成功
-
ただし、KO勝ちには至らず、一族の表情には安堵と惜しみの混ざった複雑な感情もにじみました
この一戦は、単なる防衛記録更新という意味だけでなく、一族全体の誇りと連帯を改めて感じさせる節目となりました。
さらに同年、具志堅さんと同じ名前を持つ親族の用高さんが米寿(88歳)を迎える年でもありました。この親族の用高さんは、明治時代に沖縄に入植し、戦争と戦後の混乱、土地の喪失、そして再出発と、沖縄の激動の歴史を生き抜いた人物です。
具志堅さんはこの年長者に対して、「自分はこの人たちの背中を見て育ってきた。尊敬している」と感謝の言葉を口にしています。自分と同じ名前を持つ先人が過酷な時代を乗り越えたこと、そしてその命のリレーの末に自分がいるという思いが、リングに立つ彼の力の源となっていました。
-
88歳の親族の存在は、家族の記憶をつなぐ象徴
-
戦争と復興を体験した人生への敬意と感謝が具志堅さんの心に深く刻まれていた
-
「ないちゃー(本土人)には負けられない」という信念を貫く具志堅さんの姿勢は、こうした一族の歴史と経験に支えられていた
このように、9度目の防衛戦は具志堅さんにとっても一族にとっても、勝利という結果以上の大きな意味を持った戦いとなりました。そこには、琉球王朝の時代から続く一族の誇り、そして歴史を受け継ぎながら現代を生き抜く力強さが、確かに存在していました。
沖縄の誇りを背負って戦った男
スタジオでの回想パートでは、案内役の池上彰さんの進行のもと、具志堅用高さんが世界チャンピオンとして活躍していた当時の心境を振り返りました。リングに立つとき、具志堅さんがいつも胸に抱いていたのは、「自分は沖縄を背負っている」という強い意識だったと語ります。ただの一選手ではなく、一族、故郷、そして沖縄の人々の代表として戦っていたという責任感を感じていたのです。
-
試合は個人の戦いであっても、一族や地域の思いを背負っていた
-
勝利は自分だけでなく、沖縄全体の誇りに直結していた
その気持ちは、世界チャンピオンとなった直後の帰郷エピソードにも表れています。具志堅さんが沖縄に凱旋した際、地域住民が総出で迎えてくれたという場面が紹介されました。道路にはたくさんの人が集まり、笑顔と拍手でチャンピオンを迎えた光景は、沖縄にとって彼がどれほど特別な存在だったかを物語っています。
-
空港や街道での出迎えには、老若男女が詰めかけた
-
沖縄県民全体が“誇り”として具志堅さんの帰りを祝った
また、試合後のインタビューやテレビ出演などでは、沖縄の方言を使い続けていたことにも言及。標準語が当たり前とされる放送の場においても、あえて方言を交えることで、「自分が沖縄の出身であることを隠さず、誇りとして伝えたい」という思いがにじんでいたといいます。
-
方言を使う姿に、「自分たちの言葉で話してくれてうれしい」と感謝の声
-
出身地に対する誇りを、言葉という形で守り抜いた姿勢が伝わった
具志堅用高さんは、ただ勝つためだけにリングに立っていたのではありませんでした。一族の歴史と、戦後を生き抜いてきた沖縄の人々の思いを、自らの拳に乗せて世界と向き合っていたのです。だからこそ彼の勝利は、人々の心を震わせ、希望となり、今も語り継がれているのです。
高円寺の沖縄料理店と具志堅を支えた人々
番組では、具志堅用高さんの活躍の陰にあったもうひとつの“ふるさと”とも言える場所として、東京・高円寺にある沖縄料理店が取り上げられました。この店は、具志堅さんがまだ世界チャンピオンになる前から通っていた思い出の場所であり、石垣島出身の初代店主が営んでいた店です。
-
初代店主は、沖縄から上京し、地元の味を東京に広めた人物
-
具志堅さんにとって、都心の中で沖縄を感じられる大切な場所だった
具志堅さんの試合がテレビ中継される日は、この店が沖縄出身者の“応援の場”として盛り上がる光景が当たり前になっていたそうです。狭い店内には試合開始前から人があふれ、まるで沖縄の集落のような一体感に包まれていたといいます。テレビの前で拳を握りしめ、声援を送る人々。その中心に、具志堅さんの勝利を心から願う仲間たちの存在がありました。
-
試合日は立ち見が出るほどのにぎわい
-
勝利のたびに島唄や泡盛が飛び交い、まるで祭りのような雰囲気に
現在は、東京出身の2代目店主がその味と空間を引き継いでおり、沖縄の伝統文化を次世代に伝える活動にも取り組んでいると紹介されました。地元出身ではなくとも、沖縄の精神を尊重し、料理や空間、音楽やことばを通してその文化を守ろうとする姿勢に、新たな「つながり」の形が見えてきます。
-
2代目店主は沖縄文化を愛し、守る“本土の継承者”
-
店は現在も沖縄出身者が気軽に立ち寄れる“心の拠り所”として存在
具志堅さんがボクシングの世界で戦っていたころ、この店はまさに「東京の中の沖縄」でした。遠く離れていても、共に一喜一憂し、支え合える仲間がいる――そんな場所があったからこそ、具志堅さんはより強くなれたのかもしれません。この料理店の物語は、スポーツと地域文化、そして人の絆が織りなす小さな奇跡のような存在として、番組の中でも印象的に描かれていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

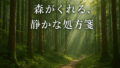

コメント