夜中にクレーンゲームが大暴走!?ロボットとゲーマーが拓く未来の働き方革命
2025年5月17日(土)18時05分からNHK総合で放送予定の『所さん!事件ですよ』では、「夜中にクレーンゲームが勝手に動き出す」という驚きの情報をもとに、働き方を大きく変えようとしているロボット技術とゲーマーの可能性に迫ります。番組では、埼玉県のある工場で起きている現象を取材し、そこに隠された新しい社会のかたちを探ります。さらに、外に出られない人がロボットを通じて社会とつながる方法や、訪日観光客も巻き込むカフェの取り組みなど、令和時代ならではの働き方についても深く掘り下げていきます。
夜の巨大倉庫で動き続ける330台のクレーンゲームの正体

今回番組で最初に取り上げられたのは、埼玉県にある巨大な倉庫型施設でした。その広さはテニスコート約12面分にもおよび、まるで体育館を何棟もつなげたような圧倒的なスケールです。その広い空間には、330台を超えるクレーンゲーム機が所狭しとぎっしり並んでいる光景が広がっていました。並んだ機体はすべて同じ方向を向いて整然と配置され、まるでロボット軍のような静かな迫力を感じさせます。
この機械群はすべて、24時間稼働が可能なオンライン対応型のクレーンゲームです。スマートフォンやパソコンを使えば、全国どこからでも遠隔でゲーム操作ができ、景品は自宅に配送される仕組みになっています。
この倉庫には、コロナ禍で閉店した全国のゲームセンターから引き取られた中古機が再利用されており、不要になった機材に新たな命が吹き込まれている形です。再利用されているとはいえ、整備や修理が丁寧に行われ、稼働状況は良好。ゲームセンターではなく、インターネット上に仮想のゲーセンを築いたとも言える存在です。
利用者層については、次のような傾向が明らかになっています。
-
ユーザーの8割は20〜40代の男女
-
もっとも利用が集中するのは夜間の22時〜25時
-
スマホひとつで操作可能な手軽さが人気の理由
特に深夜の時間帯に人気が集中している理由として、番組ではクレーンゲームの「コトン」という景品が落ちる音に快感を覚える脳の反応に関する専門家の見解も紹介されていました。この“音の刺激”が、無意識のうちにストレスの軽減や満足感につながっている可能性があるとのことです。
-
「コトン」という音は脳の報酬系を刺激するという仮説
-
自分の操作が「成功」に直結する快感がある
-
深夜の静けさの中で集中しやすいことも影響
このように、この倉庫は単なるゲーム施設ではなく、現代人のストレス解消や癒し、自己達成感を満たす“夜のエンタメ空間”としての役割も担っていると考えられます。光るゲーム機が並ぶ光景は、どこか未来的でありながら、使われなくなった機械たちの再生という意味でも、温かみのある挑戦ともいえます。
ゲーマーの技術が建設現場を変える?若者の感覚と“遠隔操作”の新時代

番組で次に紹介されたのは、北海道・赤平市にある建設会社が取り組む重機の遠隔操作システムについてでした。この会社では、人手不足や危険な現場作業に対応するため、オフィス内から建設重機を操作できる遠隔システムを導入しています。導入されたシステムには、実際の建設機械のコックピットとほぼ同じ構造のシミュレーター型操作台が備えられており、モニターやレバー、ペダルなどを通じて、現場に設置された重機をリアルタイムで動かすことが可能です。
この新たな取り組みのなかで、ある学生の声が技術の進化に拍車をかけたとして紹介されました。
-
「ゲームのコントローラーだったらもっと上手くできる」という発言
-
その意見を受けて、実際にゲーム用のコントローラーを活用した操作システムを試験的に導入
-
結果、若者がスムーズに操作できるようになり、作業の精度も向上
こうした事例からも分かるように、ゲームに慣れた世代が培ったスキルが、建設業のような現場仕事にも応用できる時代が到来しつつあります。従来は特殊な訓練が必要とされた重機の操作ですが、“感覚的にわかるUI(ユーザーインターフェース)”によって、若者が即戦力として活躍できる可能性が広がっています。
-
ゲーム世代の特徴:反応速度が速い、視覚処理能力が高い
-
コントローラー操作によって緊張感を軽減
-
遠隔操作による安全性の向上
ただし、技術だけでは埋められない課題も存在しています。スタジオゲストの國井康晴教授は、遠隔操作の限界についても言及しました。人が現場で自然に感じ取っている温度、湿度、風、地面の微細な揺れなどの“感覚的な情報”は、現在の遠隔システムではまだ十分に伝えきれないという点が課題です。
-
現場では視覚・聴覚以外にも複数の感覚が必要
-
操作する側の“違和感”や“読み違い”が生じる可能性
-
現場との信頼関係や判断力が補完要素として重要
それでも、こうした取り組みは間違いなく、建設業界に新しい可能性をもたらしていることは確かです。「ゲーム=遊び」という既成概念を超え、若者のスキルが社会を支える力に変わる未来が、すでに現実として始まりつつあることを感じさせる内容でした。
医療・船・宇宙まで広がる“遠隔操作”の革新技術
番組では、建設現場を超えて広がる遠隔操作技術の可能性についても詳しく紹介されました。もはや「遠隔で操作する」という技術は、ゲームやクレーンゲームの枠を超え、社会インフラや未来科学の根幹を支える要素として注目されているのです。
まず取り上げられたのは、海運業界の未来を見据えた国家的プロジェクト「MEGURI2040」です。このプロジェクトは、2040年までに国内で運航する船の50%を無人化・自律運航化することを目標に掲げており、すでに茨城県・大洗港や北海道・苫小牧港などで実証実験が進行中です。
-
船舶の自動運航により、航行ミスや事故リスクの軽減が期待される
-
慢性的な船員不足を解消する新たな手段として注目
-
陸地のコントロールセンターからの遠隔操縦が可能なシステムを構築中
つづいて紹介されたのが、医療分野における“触覚伝達”型の手術支援ロボットです。これは、内視鏡手術において術者が遠隔地にいながらリアルな触覚情報を感じ取れるロボット技術で、すでに国内9つの病院に導入されているとのことです。
-
ロボットを通じて患者の組織の柔らかさや圧力を感じながら手術が可能
-
遠隔地の名医が、物理的に移動することなく医療支援に参加できる
-
医療過疎地域への高精度医療提供も可能になる
このように、人間の“感覚”を遠隔で再現するという進化が、医療の質と安全性を大きく向上させています。
さらに、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが進めている月面探査プロジェクトでも、遠隔ロボットの導入が進められています。たとえば、月面に送られた無人探査車を、地球から遠隔で操縦し、地形の調査や資源探査を行うという取り組みです。これは、将来的には有人活動の前段階として、ロボットが危険な場所を先に調査する役割を担うと期待されています。
-
地球と月の間でもコマンド操作による遠隔探査が技術的に可能
-
自律行動と人の遠隔指示を組み合わせたハイブリッド型運用
-
探査だけでなく、月面での建設準備や実験支援なども視野に
このように、「遠隔操作」はもはや“サブ的な補助技術”ではなく、本格的な社会インフラや先端医療、宇宙開発に必要不可欠な存在となりつつあります。番組では、こうした事例を通じて、「人がいない場所でも人の意志と技術が届く時代」がすでに始まっていることを強く伝えていました。技術は、人を遠ざけるのではなく、むしろ“届かない場所”を可能にする手段へと変わりつつあるのです。
外出できない人の“働く力”を支える分身ロボットカフェの挑戦

まとめ
『所さん!事件ですよ』2025年5月17日放送回は、“遠隔操作”という技術が持つ可能性を通して、人と社会の新しいつながり方を探る内容でした。クレーンゲームから始まり、重機、医療、宇宙、そして分身ロボットまで、あらゆる分野で「現場にいなくても関われる」未来が現実となりつつあることを実感させてくれる放送でした。働き方や生き方に新しいヒントを与えてくれる回となりました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

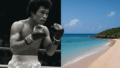

コメント