桃の香りと甘みが魅力!沖縄・石垣島のピーチパイン特集
2025年5月18日(日)放送のNHK総合「うまいッ!」では、沖縄・石垣島で育つ希少なパイナップル「ピーチパイン」の特集が放送されました。桃のような優しい香りと強い甘みが特徴で、普通のパイナップルとは一味違う美味しさがあります。番組では、その香りや甘みの理由を探るため、現地の生産者や栽培の工夫、さらには家庭で楽しめるレシピも紹介されました。生産の背景には沖縄農業の歴史や苦労もあり、改めてピーチパインの価値を知ることができる放送でした。
桃の香りがする!?ピーチパインの特長と誕生秘話

ピーチパインは、沖縄県が生み出したオリジナル品種のパイナップルで、その魅力は何といっても桃のような甘く華やかな香りと、一般的なパイナップルにはない果肉の白さにあります。果肉は繊細でやわらかく、ひと口食べれば果汁がじゅわっとあふれ、口いっぱいに香りと甘みが広がります。
・香りは甘くてやさしく、桃に似た香気成分が含まれているため、まるでフルーツミックスのような華やかさを感じさせます。
・果肉の色は白く、一般的な黄色のパインと見た目から大きく異なり、清涼感のある印象を与えてくれます。
このピーチパインは、全国に流通するパイナップルの中でもとても貴重です。日本国内で出回っているパイナップルの量は全体のわずか約4%程度であり、そのうちの大部分が沖縄県で作られています。そのため、国産パイナップルの中でもピーチパインはさらに希少価値の高い存在といえるでしょう。
ピーチパインが育つ石垣島は、1年を通して温暖な気候に恵まれています。この地域特有の気候や風土が、ピーチパインの香りと甘みをより一層引き立てているのです。また、石垣島の農家では、手間を惜しまずに1株ずつ大切に育てており、収穫までには2年近くの時間がかかります。
・ピーチパインは手でちぎって食べられるほど実がやわらかく、繊維が細かいため、ナイフを使わずに簡単に分けて食べることができるのも特徴です。
・「ポコット・パイン」という品種も同様に手で割けるタイプですが、ピーチパインの方が香りと甘みに特化している点で差別化されています。
贈り物としても人気があり、見た目のかわいらしさと香りのよさが特別感を演出してくれます。箱を開けた瞬間に広がる甘い香りは、まさに南国からの贈り物といった印象を与えます。石垣島の自然と人の手によって丁寧に育てられたピーチパインは、香り・味・見た目の三拍子がそろった特別なフルーツなのです。
生産者のこだわりと石垣島ならではの工夫

沖縄県石垣島には、約70軒のパイナップル農家が存在し、島全体の人口はおよそ4万9000人です。その中で番組に登場したのが、生産者の山城海(やましろ うみ)さん。彼の畑では、一本一本の苗を丁寧に育てる姿勢が印象的でした。パイナップルという果物は、1つの株に1個しか実をつけないため、1玉の価値が非常に高く、生産者の手間と愛情がそのまま味に反映される作物といえます。
・石垣島は沖縄本島から約400kmも南西に位置し、年間を通して気温が高く、日照時間も長いという恵まれた気候条件が揃っています。
・この温暖な気候によって、パイナップルの糖度がしっかりと高まり、香りや味に奥行きが出るのです。
また、石垣島ならではの特徴として、酸性の赤土と呼ばれる特殊な土壌があります。日本では通常、中性の土壌で栽培される作物が多い中、パイナップルは酸性土壌との相性が良く、根から効率よく栄養を吸収できるのです。この赤土の存在が、甘くてジューシーな果実づくりに貢献しています。
苗を畑に植え付けてから、実際に収穫されるまでにはおよそ2年の年月がかかります。この間にも生産者の工夫は続きます。
・1年目は十分に肥料を与え、葉を健康に育てて光合成をしっかりと促す
・2年目には肥料を控えることで、葉に蓄えられた養分が果実へと集中し、甘みが凝縮される
こうした長期的な視点に立った育成法は、経験と知識の積み重ねがなければできない技術です。
収穫時期の見極めにも細心の注意が払われています。ピーチパインの皮の色が緑から徐々にオレンジ色へと変化するタイミングが、収穫の目安とされていますが、それだけでは不十分です。山城さんのような生産者は、自ら試食して果実の状態を確認し、一番おいしい瞬間を見極めて収穫します。
そして、収穫されたパインは、ある程度葉を取り除いた状態でJA(農業協同組合)の集荷場へと運ばれます。ここでも厳しいチェックが行われます。
・表面にわずかな虫食い跡があるだけでも「規格外品」として扱われる
・そのような果実は加工用へと回され、生食用としては出荷されないほど徹底した品質管理
このように、生産のすべての工程において丁寧さと高い品質意識が保たれているからこそ、ピーチパインはあれほどまでに香り高く、甘みのある果実として私たちのもとに届けられるのです。
地元の自然環境と生産者の絶え間ない工夫と努力が、ピーチパインの美味しさを支えているということが、今回の番組から強く伝わってきました。
沖縄農業の苦境とピーチパイン誕生の歴史
沖縄県では1950年代からパイナップルの栽培が盛んになり、特に1960年代には缶詰用として全国に出荷されるほど発展しました。しかしその後、海外からの安価なパイナップルの輸入が増えたことにより、沖縄のパイン産業は一気に衰退してしまいます。
さらに1990年代にはパイン缶詰の輸入が自由化され、生産コストの高い国内産パインはますます苦しい状況に。そこで農業関係者たちは方向を転換し、「食べておいしい」パイナップル、つまり生食用のパインの開発に力を入れました。
当時主流だったパインは酸味が強く、生で食べるには向いていませんでした。そのため、沖縄県農業研究センターなどが中心となって品種改良を重ね、10年という長い年月をかけて1999年にピーチパインが誕生しました。この成功により、沖縄のパイン農業は再び注目されるようになり、生産者にとっても希望の光となりました。
家庭で楽しむピーチパインレシピ2品
番組では、家庭でも気軽に楽しめるピーチパインのアレンジレシピとして、「パインロール」と「パインケーキ」が紹介されました。どちらも石垣島産ピーチパインの甘みと香りを活かしたスイーツで、見た目も華やかです。食感や香りの違いを比べながら楽しむのもおすすめです。
まずはパインロール。春巻きの皮を使って簡単に作れるのが魅力です。外はパリッと、中はとろけるような食感になり、揚げたては特に香ばしさと甘さが引き立ちます。ジャムの濃厚さとココナツの風味が加わることで、南国感たっぷりの味わいに仕上がります。
-
ピーチパインを皮ごとよく洗ってから一口サイズにカットする
-
鍋に入れ、グラニュー糖(目安:パインの重量の1/3)を加えてよく混ぜる
-
一晩そのままおいて水分が出てくるのを待つ
-
翌日、弱火にかけて水分が減ってとろみが出るまでじっくり煮詰める
-
レモン汁少々とココナツパウダー(大さじ1)を加えて風味をつける
-
出来上がったジャムを冷まし、春巻きの皮にのせて巻く
-
さらにもう1枚の皮を重ねて巻き、表面に溶かしバターを塗る
-
中温の油できつね色になるまで揚げて完成
次にパインケーキ。こちらはピーチパインをたっぷり使って焼き上げるケーキで、キャラメルと果実の甘さが絶妙にマッチします。生地に細かく刻んだピーチパインも混ぜ込むことで、食べるたびに果肉のジューシーさが感じられる仕上がりです。
-
ピーチパインを輪切りにし、芯をくり抜く(必要であれば皮もむく)
-
鍋に入れ、水とグラニュー糖(適量)を加えてコンポートにする(中火で10分ほど)
-
ケーキ型にキャラメルソースを流し入れ、コンポートしたパインを並べる
-
ボウルに卵2個、生クリーム100ml、薄力粉100g、細かく刻んだピーチパイン50gを加えてよく混ぜる
-
型に生地を流し込み、160℃のオーブンで約30分焼く
-
焼き上がったら冷まし、型から外す
-
最後にピーチパインジャムを表面に塗って艶を出す
どちらも素材の風味を引き出すやさしいレシピなので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して作れます。旬のピーチパインを存分に味わえる2品、ぜひ家庭で楽しんでみてください。
スタジオでの試食と感想紹介
番組のスタジオでは、ピーチパインの生果実と2種類のスイーツを実際に試食。果肉の白さが際立ち、桃のような香りと甘さが口いっぱいに広がるピーチパインは、見た目からもおいしさが伝わってくる一品です。
パインロールとパインケーキもそれぞれ、果肉のジューシーさや香りの余韻が評価され、特に鼻に抜けていく甘く上品な香りが印象的でした。焼き菓子にしてもフレッシュ感がしっかり残り、ピーチパインならではの個性が生きているレシピでした。
おわりに
「うまいッ!」の今回の放送では、沖縄の自然と人の知恵が育んだピーチパインの魅力がたっぷりと伝えられました。気候や土、栽培技術、品種改良、すべてが合わさって完成するこの甘く香り高い果実は、まさに石垣島の宝といえる存在です。生食でも、スイーツでも、家庭で簡単に楽しめるピーチパイン。今後さらに人気が高まること間違いなしです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


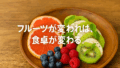
コメント