清流が育てた岐阜の恵み なまずが主役の“うまいッ!”旅へようこそ
「なまずって食べられるの?」「臭みが強そうでちょっと抵抗がある…」――そう感じる人は少なくありません。実際、なまずは日本の川に広く生息していますが、食卓に並ぶ機会はごくわずか。ところが、岐阜県海津市ではこの“なまず”がご当地グルメの主役として長年親しまれてきました。三つの大河――木曽川・長良川・揖斐川に囲まれた海津市は「水の都」と呼ばれるほど水が豊かで、昔から川魚文化が根づいています。
2025年10月5日放送の『うまいッ!』では、番組ナビゲーターの天野ひろゆき(キャイ〜ン)と塚原愛アナウンサーがスタジオから、岐阜・海津市のなまず料理を特集しました。現地取材を行ったのは番組リポーターの本田さん。実際に取材した彼は「なまずのイメージが覆された」と驚きの声を上げていました。岐阜では古くからなまずを食べる文化があり、今では養殖技術の進化により、天然に劣らぬ味わいが楽しめるようになっています。
参道に香る甘辛ダレの誘惑 千代保稲荷名物“なまずの蒲焼”
岐阜県海津市の観光名所といえば、千代保稲荷神社。地元では親しみを込めて“おちょぼさん”と呼ばれ、商売繁盛のご利益を求める参拝客で一年中にぎわいます。参道には串カツ、どて煮、みたらし団子などの屋台が並びますが、訪れた人が思わず足を止めるのが、香ばしいなまずの蒲焼の香り。
老舗の川魚料理店では、注文を受けてから一尾まるごとを炭火で丁寧に焼き上げます。タレは甘すぎず、控えめな味つけが特徴。うなぎのようなこってり感ではなく、ふっくらした身の中にあっさりとした脂の旨みが広がります。皮目は香ばしく、骨は柔らかく処理されており、食感も上品。店によっては、ご飯の上に蒲焼をのせて“なまず丼”として提供しており、地元の定番ランチとして親しまれています。
なまずが名物となった背景には、この地域特有の“水との共生”があります。川の氾濫を防ぐ堤防の整備が進む一方で、川魚を大切にする文化が残されてきました。なまず料理は、自然への感謝とともに育まれてきた味なのです。
若き養殖家が挑む!レンコンが生んだ“岐阜なまず”の新時代
番組の中でも特に印象的だったのが、岐阜県羽島市でなまず養殖を営む南谷夫妻。夫は23歳という若さで、年中無休で約5000匹のなまずを育てています。その姿勢はまさに「新しい地域の担い手」。若者が一次産業に夢を見られる場所を作ろうと、日々奮闘しています。
南谷さんのこだわりは、まず「水」。養殖池には清らかな井戸水を使用し、常に循環させることで、なまず特有の泥臭さをなくしています。そしてもう一つの秘密が「エサ」。地元の特産品である羽島レンコンを粉末状にして混ぜ込み、栄養価を高めています。レンコンはビタミンやミネラルが豊富で、なまずの健康な成長を支えるだけでなく、身のしっとり感や脂の質を向上させる効果があるのだそうです。
こうして育てられたなまずは、泥抜きが不要で、なんと刺身でも食べられるほどの品質。スタジオで試食した天野ひろゆきは「白身魚みたいで、脂がしっかりしているのにさっぱり」とコメント。塚原アナも「見た目からは想像できないほど繊細な味」と感動していました。まさに“岐阜ブランド”の新たな誕生です。
和の職人が生み出す、なまずの新しい味わい方
岐阜の料理人たちは、この高品質な養殖なまずを使い、伝統と創作を融合させた新しいメニューを次々と生み出しています。羽島市の日本料理店では、うなぎの「う巻き」にヒントを得た“な巻き”を考案。ふわふわの卵焼きの中に、香ばしく焼いたなまずを包み込んだ一品です。口に入れると卵の甘みと魚の旨みがとろけるように合わさり、うなぎとはまた違った軽やかさが楽しめます。
さらに、なまずのあらでじっくり出汁を取ったなまず味噌汁は、まろやかなコクと深い旨みが特徴。臭みが全くなく、白味噌との相性が抜群です。そして外はサクッ、中はふんわりのなまず天ぷらも人気メニュー。天つゆや塩でシンプルに味わうと、なまずの甘みが際立ちます。
番組では、なまずに含まれるEPAやDHA、ビタミンEなどの抗酸化成分が老化防止にも効果的だと紹介され、栄養面から見ても“美容と健康にうれしい魚”として注目を集めています。
伝統を守る最後のなまず漁師 川とともに生きる男たち
現代の養殖技術が進む一方で、天然なまずの漁を続ける人々もいます。岐阜県揖斐川で50年以上なまず漁に携わる三浦秀人さんは、その道の第一人者。夜明け前、川面を静かに進み、仕掛けを確認する三浦さんの姿には、長年の経験と自然への敬意がにじみ出ています。
なまずは夜行性のため、漁は夜中に行われます。三浦さんはうなぎと同じ仕掛けを使い、流れの緩やかな場所を見極めて網を張ります。取材では、見事にエメラルドグリーン色をした美しい天然なまずを捕獲。この幻想的な色の理由は科学的にも解明されていませんが、清流の環境が大きく関係していると考えられています。
現在、岐阜県内で天然なまずを獲る漁師はわずか数人。高齢化や川の環境変化が課題となる中、三浦さんのもとには若い弟子が5人育ち、伝統の技を未来へと受け継いでいます。こうした人々の努力が、岐阜の川魚文化を支え続けているのです。
水と人が紡ぐ“なまずの都”の物語
番組のエンディングで、天野ひろゆきは「水がきれいだからこそ生まれる味。人の努力がそのおいしさを育てている」と語りました。塚原アナも「この地域の人たちの誇りを感じました」と締めくくります。
なまず料理は、単なる郷土グルメではありません。自然環境・地域産業・文化の継承が一体となって守られている、まさに“岐阜の宝”です。養殖の革新と伝統漁の共存、それを支える人々の情熱が、地域の未来を照らしています。
観光として訪れる人も、食の魅力を通して「水とともに生きる岐阜の精神」を感じることでしょう。参道に漂うタレの香り、川辺に響く水音、そして食卓で広がるやさしい味——そのすべてが、この土地の物語を語っています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・海津市は“水の都”として、古くからなまずを食す文化を持つ。
・若手養殖家が地域特産レンコンを活用し、泥抜き不要の高品質ななまずを育てている。
・天然漁を守る職人が、岐阜の川とともに生き続けている。
清流と人の知恵が織りなす「なまずの町」。岐阜を訪れるなら、ぜひ千代保稲荷神社の参道を歩きながら、香ばしい蒲焼の香りに誘われてみてください。その一皿の奥に、海津の豊かな自然と人々の物語が息づいています。
出典:NHK総合『うまいッ! 門前の名物 味わい豊か!なまず料理〜岐阜・海津市〜』(2025年10月5日放送)
https://www.nhk.jp/p/umai/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

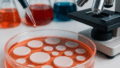
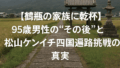
コメント