動物と話せる未来は来るの?“言葉と心の境界線”
犬や猫が言葉を話したら――そんな想像をしたこと、ありませんか?「うちの犬、私の気持ちを分かってる気がする」「猫がため息をついたのは怒ってるから?」。動物と暮らす人なら、きっと一度は思ったことがあるはずです。2025年10月7日に放送されたNHK『未来予測反省会』では、「20世紀に人と動物は自由に会話ができるようになる」という100年以上前の“未来予測”をテーマに、人類と動物の関係を見つめ直しました。番組では、予測が外れた理由と、今なお進化を続ける“動物とのコミュニケーションの科学”が紹介され、人間の想像力と科学の限界、そして希望が交錯しました。
NHK【未来予測反省会】風呂掃除ロボットはなぜ普及しない?AIが変える未来|2025年5月5日
100年前の新聞が描いた「人と動物の会話の時代」
番組冒頭で取り上げられたのは、明治時代の報知新聞に掲載された「二十世紀の予言」。当時の編集総長村井弦斎は、フランスの小説家ジュール・ヴェルヌの言葉「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」を引用し、未来の姿を大胆に描きました。そこには、今でいうエアコンを指す「暑寒知らず」や、テレビ会議の原型となる「写真電話」など、驚くほどの的中がありました。
そして、その中にあったのが「獣語の研究が進み、人と動物が自由に会話できるようになる」という夢のような予測です。当時の人々にとって、科学の進歩があらゆる壁を超える象徴だったのでしょう。人と動物の心が通じ合う未来は、現実の延長線上に見えていたのです。
今回の番組には長谷川忍(シソンヌ)と影山優佳が出演。そこに、動物研究の第一線で活躍する3人の専門家――山極壽一(霊長類学者)、鈴木俊貴(動物言語学者)、稲見昌彦(東京大学教授・身体情報科学研究者)――が加わり、未来予測の“的中と誤算”を掘り下げました。
犬は言葉を話せないけれど、「会話」は成立している?
まず議論になったのは、「実現しなかった」と言い切れるのかという点です。鈴木俊貴は「完全に外れたとは言えない」と語ります。確かに、犬や猫は人間の言葉を発しませんが、感情や意図は十分に伝わっています。たとえば犬は飼い主の声のトーン、表情、仕草から状況を理解し、喜びや不安を伝える行動を見せます。
さらに、東アフリカ・モザンビークに生息するノドグロミツオシエという鳥は、驚くべき行動をします。この鳥は自分でハチミツを採ることができないため、人間にハチの巣の場所を「教える」のです。人間が巣を壊すと、残った蜜を鳥がもらう――まさに“共生の会話”といえます。150年以上も前から確認されているというこの行動は、言葉を超えた意志のやり取りの代表例とされました。
「環世界」──動物の感じる“世界”を理解する
ここで登場したのが、ドイツの生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した概念「環世界(Umwelt)」です。これは、「生き物はそれぞれ自分にとって意味のある世界を生きている」という考え。
例えば、マダニには視覚も聴覚もありません。しかし嗅覚と温度感覚が極めて発達しており、木の上で動物の体温や匂いを感じ取ると「落ちる」という行動をとります。人間にとっての世界と、マダニにとっての世界は全く違うのです。つまり、動物と“話す”ためには、私たちがその動物の感じている世界を理解する必要がある――これが、未来予測が外れた最大の理由かもしれません。
人間は「聞こう」としてこなかった
番組では、アメリカの動物学者リチャード・リンチ・ガーナーの映像が紹介されました。彼は1890年代にサルの声を蓄音機に録音し、別のサルに聞かせて反応を調べるという画期的な研究を行いました。自ら檻の中に入り、チンパンジーたちの声を観察するほどの情熱を持っていましたが、当時の学界は冷淡でした。「動物に言葉がある」と主張しても、誰も信じなかったのです。
山極壽一は「人間以外に言葉はない」とする価値観が長く支配してきたと指摘。自身の恩師である伊谷純一郎がサルの発声を「叫ぶ」「ほえる」「呼び声」「ささやき声」に分類した際も、学会では猛反発が起きたといいます。科学の壁は、時に想像力の欠如によって作られる――それを象徴する逸話です。
“話す”から“理解する”へ──研究の進化
やがて研究の方向は変わり始めます。1940年代、ヘイズ夫妻はチンパンジー“ヴィキ”に人間の言葉を教えようとしましたが、結果は4語だけ。「パパ」「ママ」「カップ」「アップ」しか話せませんでした。原因は発声器官の構造。チンパンジーの口はU字型で、人間のように舌を動かして音を作れないのです。
しかしその後、ガードナー夫妻が手話を導入し、生後10か月のチンパンジー“ワショー”が250語の手話を習得。さらに1980年代にはランボー夫妻がボノボの“カンジ”を研究し、絵文字で意思を表す実験を成功させました。カンジは約500のシンボルを覚え、3,000語の英単語を理解したといいます。これは“会話”に最も近い実例として知られています。
一方、オウムの仲間ヨウムも英語の単語を意味とともに理解する能力を示しました。ここで明らかになったのは、人間が「教える側」ではなく「理解する側」になる必要があるということ。人間中心の言語観を捨てなければ、動物との対話は本当には成立しないのです。
“動物の言葉”を聴く研究が始まった
今、世界の研究者たちは「動物の言葉に耳を傾ける」研究を進めています。鈴木俊貴が注目するのはシジュウカラ。この鳥は敵の種類によって鳴き声を変え、しかも鳴き声を組み合わせて“文”を作るような行動を示します。語順を逆にすると仲間に伝わらなくなるという実験結果もあり、文法的構造の存在が示唆されています。
さらに、犬のしっぽの振り方が右なら幸福、左なら不安を表すなど、感情表現の解読も進んでいます。AI技術の発達により、表情や動作から動物の感情を解析するシステムも登場。なんとイルカの鳴き声を再現するAIモデルまで開発されているのです。
植物にも“声”がある?生物の意思を感じ取る時代へ
意外なことに、動物だけでなく植物の研究も進んでいます。稲見昌彦は、虫の視点で花を見ると「植物がどうやって昆虫を誘っているか」が分かると語りました。花の形や色は、虫を“操作”するための戦略。つまり、植物もまた他の生物に「メッセージ」を発しているのです。AIがその仕組みを読み解くことで、人間には見えなかった自然界の“会話”が聞こえてくるかもしれません。
まとめ:言葉の未来は、人間が“聞く側”になることで始まる
この記事のポイントは3つです。
・100年前、人々は「動物と話す未来」を本気で信じていた。
・動物の感じる世界=「環世界」を理解することが、会話の第一歩。
・AIの進歩で、人間が“話す”から“聞く”へと立場を変え始めている。
動物たちは言葉を持たないのではなく、私たちがまだその“音”を理解できていないだけ。科学がその翻訳者となる日、人と動物の関係は新しい段階に進むでしょう。未来を外した過去の予言は、今や再び現実に近づきつつあります。
出典:NHK総合『未来予測反省会「20世紀に人と動物は自由に会話ができる」』(2025年10月7日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

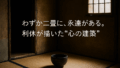
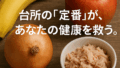
コメント