「風呂はロボットが掃除してくれる」は実現するのか?
2025年5月5日にNHK総合で放送された『未来予測反省会』では、「風呂はロボットが掃除してくれる」というテーマで、かつての予測がどこまで実現されているかを検証しました。洗濯機や掃除ロボットが当たり前になった今、なぜ風呂掃除だけは人間の仕事のままなのか。その理由と未来の可能性を追いました。
1964年に描かれた理想と2025年の現実
番組冒頭では、MCの影山優佳さんと長谷川忍さんが登場し、今回のテーマである「風呂掃除ロボット」について紹介しました。取り上げられたのは、1964年のロボット工学者メレディス・スリング氏による未来予測。彼は「1984年には風呂掃除を含むほとんどの家事をロボットが担うようになる」と断言していました。
しかし、40年以上が経った現在でも、風呂掃除は多くの人が手作業で行っている家事のひとつです。このギャップを検証するべく、「風呂はロボットが掃除してくれる」という予測がなぜ実現していないのか、専門家たちが議論を展開しました。
風呂掃除がロボット化されない理由とは?
番組では、ロボット研究の専門家として尾形哲也氏、滝本敬太郎氏、北角俊実氏が登場し、風呂掃除のロボット化がなぜ実現していないのかについて具体的に説明されました。その理由はひとつではなく、複数の複雑な要因が重なっているといいます。
まず大きな壁となっているのが、浴室の構造の複雑さです。浴室は天井、壁、床、浴槽など、さまざまなパーツでできており、それぞれに高さや角度、素材の違いがあります。特に天井部分の掃除はロボットにとってハードルが高く、人間でも手が届きにくい場所です。
-
壁はタイル、床は滑り止めのシート、浴槽は樹脂やホーローなど、素材ごとに掃除の仕方が変わります。
-
形状も直線だけでなく曲面やコーナーが多く、隅々までブラシやスプレーを届かせるのが難しいのです。
次に問題になるのが、汚れの多様性とそれに伴う掃除法の違いです。風呂場には、性質の異なる多くの汚れが発生します。番組でも紹介された通り、主な汚れは次のように分類されます。
-
黒カビ:浴室のゴムパッキンや壁の目地などに根を張るしつこい汚れ
-
水アカ:鏡や蛇口、浴槽の縁などに白く固まるアルカリ性の汚れ
-
皮脂汚れ:湯船やイスなどに残るヌルヌルとした脂分
-
ピンク汚れ:シャワーホースや床の隅に発生する細菌性の赤っぽい汚れ
これらの汚れはそれぞれ原因が違い、落とすために必要な洗剤の種類や掃除方法もバラバラです。黒カビには塩素系、皮脂汚れには中性洗剤、水アカには酸性洗剤が有効とされており、1台のロボットにこれらを的確に判断・処理させるのは至難の業です。
-
場所によっては汚れが複数重なっていることも多く、洗剤の選択ミスが素材を傷つける原因になることもあります。
-
たとえば鏡は水アカ専用の処理が必要で、同じ方法では浴槽の汚れは落とせません。
さらに、湿気と水にさらされる浴室という環境自体がロボットにとって過酷であるという点も無視できません。湿度が常に高く、使用後は水滴が天井や壁、床のいたるところに残ります。このため、電子部品が劣化しやすく、防水性と耐久性を両立させるには高価な素材と設計が必要です。
-
万が一、水が内部に入り込んだ場合は漏電や故障のリスクが高く、安全性が損なわれるおそれがあります。
-
長時間の使用や繰り返しの動作に耐えられる設計も求められ、これが家庭用ロボットとしての実用化を難しくしています。
こうした条件をすべて満たすロボットを開発し、しかも一般家庭に普及できる価格で提供するのは、現時点ではまだ難しいとされてきました。風呂掃除は単に「汚れを落とす」という行為にとどまらず、「多様な素材を傷めずに安全に、しかも効率よく掃除する」という高度なバランスが求められる作業なのです。
そのため、これまでのロボット化の流れにおいても、風呂掃除だけは取り残される形となってきたのが実情です。ですが、こうした課題がひとつひとつ解決に向かっている今、ようやく風呂掃除ロボット実現の兆しが見え始めているともいえます。
メーカーの工夫と“セルフクリーニング”への取り組み
番組内では、風呂掃除の完全自動化がまだ難しい中で、国内メーカーが工夫を凝らして「掃除の手間を減らす」ために取り組んできた技術や製品も紹介されました。その中でも注目されたのが、“セルフクリーニング”という考え方です。
まず、清掃の負担を軽くするために開発されたのが、汚れにくい特殊素材を使用した浴槽や壁面です。たとえば、親水性の高い素材やコーティングを施すことで、水分が汚れの下に入り込みやすくなり、カビや皮脂汚れが定着しにくくなる構造になっています。
-
水が汚れと素材の間に入り込んで浮かせる「防汚コーティング」
-
カビの原因菌が付きにくい「抗菌樹脂」や「銀イオン配合の素材」
-
水垢をつきにくくする「撥水加工」や「すべり落ち加工」
こうした素材の進化により、掃除の頻度を減らすことは可能になってきました。水で流すだけでもある程度の汚れが落ちるため、毎回ゴシゴシこする必要がなくなるというメリットがあります。
また、それだけでなく、浴槽そのものが自動で洗浄する「セルフクリーニング機能」の開発も進んでいます。これは、入浴後にボタンひとつで浴槽内に洗浄水や泡が噴射され、自動で洗ってくれる仕組みで、すでに一部の高機能ユニットバスには搭載されている機能です。
-
入浴終了後に排水と同時にノズルから泡を噴射し、浴槽を一周して洗浄
-
定期的にぬるま湯や除菌水で自動洗浄を行い、ぬめりや菌の繁殖を防止
-
水の使用量や洗剤の量を自動で最適化し、エコ運転が可能
このように、「掃除をロボットがする」のではなく、「掃除がそもそもいらない状態をつくる」という方向からもアプローチが進んでいるのです。
しかし、こうした機能が浴槽に限定されていることもあり、依然として壁や床、鏡、排水溝といった範囲には手作業が必要です。特に床の目地や壁の高い位置、浴室扉のパッキン部分など、カビや汚れがたまりやすい部分は、自動化が難しい箇所の代表格となっています。
-
排水溝のヌメリは定期的なブラシ掃除が不可欠
-
浴室ドアのパッキンは黒カビが発生しやすく、目視点検と除去が必要
-
天井の水滴によるカビの発生も、手拭きが今もなお主流
つまり、メーカーの工夫によって掃除の負担は確実に軽くなっているものの、「風呂掃除ゼロ」の状態にはまだ届いていないというのが現状です。
それでも、これまでの進化を見れば、完全自動化への道が確実に近づいていることがわかります。セルフクリーニング機能の進化と、素材開発の積み重ねが未来の風呂掃除のあり方を大きく変えていくかもしれません。
AIが語る未来の風呂掃除は?
番組の終盤では、未来の風呂掃除がどうなっているかを探るため、AIに「20年後の風呂掃除はどうなっているか?」という問いかけが行われました。そこで返ってきた回答は、「カビ・アカ・ヌメリは人間が掃除しなくてはならない」という非常に現実的なものでした。この答えは、多くの視聴者にとって意外だったかもしれません。
つまり、現在の技術では、浴室に発生する複雑でしつこい汚れに対して、まだ完全な自動化は実現できていないということです。カビの根の深さ、水アカの固着力、ヌメリの広がりやすさといった性質は、今なお人間の目と手で対処するしかない場面が多いのが現状です。
とはいえ、未来がまったく閉ざされているわけではありません。番組では、AIやロボティクス技術の急速な進化が、風呂掃除の未来に明るい兆しをもたらしていることも紹介されました。特に次のような技術が注目されています。
-
AI画像解析技術:汚れの種類をカメラで識別し、それぞれに適した掃除モードを自動で選択。黒カビ、水アカ、皮脂汚れなどをリアルタイムで見分け、効率よく処理することが可能に。
-
自動清掃アーム:浴室内の立体的な構造をセンサーで読み取り、壁の角や床の隅、浴槽の縁までアームが動いて清掃。これにより、人の手が届きにくい部分の掃除も機械に任せられるようになります。
-
IoTとの連携:風呂の使用頻度、室温、湿度、残留水分のデータをもとに、「このタイミングで掃除したほうがカビの発生を防げます」といった提案を自動で行う仕組みも開発されています。
-
泡やスチームを使った非接触洗浄:微細な泡やナノスチームで汚れを浮かせ、こすらずに除去する技術が進化。洗剤を使わず、素材にも優しいため、環境にも安全性にも配慮された次世代の掃除方法として注目されています。
これらの技術はすでに、一部の住宅メーカーのモデルハウスや実験的なスマートバスルームで導入が始まっています。たとえば、浴槽の縁に沿って自動で移動する清掃ノズル付きのユニットや、掃除の予約をスマホで管理できるIoT機能付きバスなどが登場し始めています。
つまり、「ロボットが風呂を掃除してくれる」という未来は、決して遠い話ではなくなってきています。“完全自動”の風呂掃除は、かつて夢見られた未来予測がようやく現実に追いつこうとしている段階にあるのです。
今のところ、AIも「人間の掃除はまだ必要」と語っていますが、それは“今の時点では”という前提つき。今後さらに技術が進めば、風呂掃除の完全自動化が当たり前になる日が来るかもしれません。人の手が不要になる未来は、想像よりもずっと近くに迫っているのです。
番組のまとめと今後への期待
『未来予測反省会』の中で明らかになったのは、予測が外れたからといって、その未来が無意味だったわけではないということです。予測は希望であり、方向性を示すもの。そしてその希望に向かって、技術者たちは挑戦を続けています。
今後さらにAIが進化し、家庭環境に最適化されたロボットが開発されれば、風呂掃除の完全自動化もついに実現するかもしれません。
未来の風呂掃除ロボットに期待が高まる一方で、今の技術でできることも増えています。浴室の構造や使い方に合わせて、“掃除を減らす工夫”と“掃除の質を上げる技術”が両立する日が近づいていると感じられる放送内容でした。
これからの家事の未来、特に「めんどうな風呂掃除」がどう変わっていくのか。今後の動向に注目です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

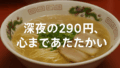

コメント