ダ・ヴィンチの超絶技巧と3つの謎を科学で解明!「モナ・リザ」と「最後の晩餐」に迫る
2025年5月14日放送の『歴史探偵』では、レオナルド・ダ・ヴィンチに迫るスペシャル企画が放送されました。ルネサンス期の天才として知られるダ・ヴィンチの代表作「モナ・リザ」と「最後の晩餐」を中心に、3つの謎を科学とVR技術で徹底調査。佐藤二朗さんと片山千恵子アナウンサーの進行のもと、美術史家の池上英洋さんが専門的な視点から解説を行いました。絵画、科学、感情が交差する45分でした。
「モナ・リザ」の技法に迫る科学調査

番組の前半では、ルーブル美術館に収蔵されている「モナ・リザ」に焦点が当てられました。50万点を超えるルーブルのコレクションの中でも、とりわけ特別な存在として知られるこの作品。ダ・ヴィンチは繊細な影の濃淡のみを使って、神秘的なほほ笑みを表現したとされています。その“微笑み”の秘密を、番組では科学の視点から解き明かしていきました。
まず注目されたのは、酸化鉛という特殊な顔料の存在です。科学者フィリップ・ヴァルテール氏によると、「モナ・リザ」の下地からは、この酸化鉛が検出されており、これが肌に温かみと深みを与えていると考えられています。この顔料は当時のルネサンス絵画では一般的ではなく、レオナルドが独自の判断で使用した可能性があるとのことです。
-
絵の下層に施された下地には、茶褐色の酸化鉛が使われていた
-
この顔料の効果で、光が肌に柔らかく吸収され、自然な輝きを生んでいる
-
温もりのある肌のトーンは、この顔料と光の反射のバランスによるものと判明
さらに、X線を用いた非接触の科学調査では、影の部分に茶色と黒の顔料が用いられていることも確認されました。これらはすべて、スフマート技法による柔らかいぼかしを支える重要な要素です。実際に顔料は極めて薄く、十数回にわたって塗り重ねられていたことが、科学の力によって明らかになっています。
-
一つ一つの層は非常に薄く、厚みはわずか数ミクロン
-
グラデーションのなめらかさは、塗っては乾かし、を繰り返す緻密な作業の賜物
-
肌の陰影に奥行きを与え、表情を生きているように見せる工夫がされている
このような分析を踏まえ、池上英洋さんはダ・ヴィンチの技法を再現する実験に取り組みました。同じ材料を用いて、「モナ・リザ」の口元の影を塗っては乾かすというプロセスを何度も繰り返し、グラデーションの再現を試みました。
-
実際の再現作業でも、口元の影の部分は最も難易度が高かった
-
材料や工程は一致していても、肌に宿る透明感や柔らかさは再現できなかった
-
細部の光と影のバランス、塗り重ねのタイミングや筆圧の差が影響している可能性
池上さんは試行錯誤を重ねた結果、「同じ材料でも、ここまで自然な肌の表現は非常に難しい」と述べ、ダ・ヴィンチの技巧に対する深い敬意をあらわにしました。この体験を通して、彼の絵が単なる筆遣いではなく、計算と観察、そして技術の集大成であることが証明されたのです。
このように、番組は絵画をただ“見る”だけでなく、描かれた背景と技術を“読み解く”ことの大切さを教えてくれました。ダ・ヴィンチが命を吹き込んだ「モナ・リザ」のほほ笑みは、科学の力でその仕組みが明らかになった今でも、なお人々を魅了し続けています。
「最後の晩餐」をVRで体験!構図の秘密を検証

番組の後半では、レオナルド・ダ・ヴィンチの代表作「最後の晩餐」に注目が集まりました。描かれたのはミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の修道院食堂。劣化や修復を繰り返してきたため、現在は部分的にしか当時の姿が残っていないこの壁画を、最新のVR(仮想現実)技術を使って再現する取り組みが紹介されました。
この試みによって、絵の中に描かれた空間が立体的に再現され、まるで絵の中に入り込むような体験が可能になりました。VR映像で見ると、画面の奥行き、光の入り方、人物の配置など、ダ・ヴィンチが描こうとした空間構成が立体的に理解できるようになります。
-
中央のイエスを頂点とする遠近法が空間全体に適用されており、視線が自然に中心へ導かれる
-
背後の3つの窓と天井の直線が一点透視法を構成し、奥行きを強調している
-
光の表現も計算されており、現実の修道院の窓の位置と一致して描かれていたことが判明
しかし、実際にVR内で人物像を等身大に修正して表示したところ、絵としての迫力が失われるという結果に。これは、ダ・ヴィンチが意図的に人物のサイズや遠近感を誇張して構成していたことを示すものでした。
-
実物よりも大きく描かれた人物像は、食堂に座る修道士たちが見上げたときに最も自然に見えるように調整されていた
-
イエスを囲む12人の弟子たちの動きやジェスチャーは、対話と感情の流れを視覚化するため、視線や手の動きに強調が加えられている
-
人物と空間のスケール感は、鑑賞者の視点によって“最も美しく見える”ように設計されていた
さらに、この作品に使われた画材にも注目が集まりました。調査により、顔料にはラピスラズリが使用されていたことが明らかに。この鉱石は当時、金よりも高価で、特別な場面にのみ用いられる貴重な素材でした。背景に使われた青の深みは、その素材の高価さと、絵に込めた芸術的敬意を象徴しています。
-
ラピスラズリの顔料は、透明感と奥行きのある色調を生み出す特性があり、空や衣服などに使われていた
-
ダ・ヴィンチは、経済的な制約がある中でも、画材の質に妥協しない完璧主義を貫いていた
-
修道院の依頼で描いた宗教画にもかかわらず、素材の選定から構図まで、あくまで芸術性を優先していた姿勢が浮き彫りに
番組では最後に、ダ・ヴィンチの制作スタイルに触れ、完成させた作品は生涯でわずか15点ほどだったことが紹介されました。これは、ひとつの作品に何年もの歳月をかけ、構図、色彩、視覚効果を極限まで突き詰めた結果といえます。
「最後の晩餐」は単なる宗教画ではなく、空間、心理、視覚、芸術を融合させたダ・ヴィンチの総合的表現でした。現代のVR技術を通して、私たちはようやく、彼が目指した“見え方”に近づくことができたのかもしれません。500年前の天才の頭の中に描かれた世界が、デジタル技術で今、現実のものとして再び命を吹き込まれているのです。
芸術×科学でよみがえる“天才の頭の中”
今回の『歴史探偵』は、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品を美術史・科学・感情の3つの視点から徹底的に分析した内容でした。絵の裏側にある技術的な緻密さ、VRで読み解かれる空間構成、そして絵に込められた個人的な感情——どれも500年経った今でも人の心を揺さぶる普遍的な力を持っていることが示されました。
科学の力でダ・ヴィンチの超絶技巧を解明する時代が到来した今こそ、私たちは彼の本当の姿に近づきつつあるのかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


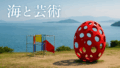
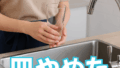
コメント