島に誇りを取り戻した奇跡の物語
瀬戸内海の島々がかつて「瀕死の海」「はげ山」「ゴミの島」と呼ばれていたことをご存じでしょうか。今では世界中から観光客が訪れる人気スポットですが、そこに至るまでには大きな挑戦と失敗、そして人々の再起の物語がありました。今回の「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」は、直島や豊島をアートの力でよみがえらせた人々の軌跡を紹介しています。この記事では、番組で描かれたすべてのエピソードをまとめ、検索して訪れた方が知りたい「なぜアートで島が蘇ったのか」「誰がどんな挑戦をしたのか」という疑問に答えていきます。
直島の衰退と再建への挑戦
直島は高度経済成長期に工場の煙に覆われ、美しい自然が失われてしまいました。山々は草木が育たなくなり、荒れ果てた姿から「はげ山」と呼ばれるようになったのです。子どもたちが誇りをもてるはずのふるさとは、人々から後ろ指をさされる存在になっていきました。直島出身の奥田俊彦も、自分の生まれ育った島を語ることを避けるほどで、島の人々の心からは誇りが消えていました。
しかし、このままでは未来がないと町の人々は危機感を抱きました。そして島の再建を福武書店(現ベネッセ)に託すことを決意します。依頼を受けた社長の福武總一郎は考えました。島に工場以外の新しい価値を生み出すにはどうしたらいいか。その答えとして浮かんだのが、自身が収集していたアートの力を活かすという発想でした。美術と宿泊を組み合わせた、これまでにない施設を作る。そうして1992年、アートホテルがついに開館したのです。
ところが、期待に反して観光客はほとんど訪れませんでした。話題性はあったものの、島には人が集まらず、経営は赤字が続く厳しい状況に陥りました。島の未来を託された一大プロジェクトは、早くも暗礁に乗り上げてしまったのです。
そのホテルに、学芸員として人生を懸けたのが秋元雅史でした。秋元はかつて「ザ・スコップマン」という独特なパフォーマンスを路上で行っていた芸術家です。銀座の街角でスコップを叩き、通行人の反応を追い求める日々を10年も続けました。しかし世間からの評価は得られず、やがて芸術の道を諦めてアルバイトで生計を立てるようになっていました。そんな彼にとって、アートホテルの学芸員という仕事は、まさに人生をやり直す最後のチャンスだったのです。
秋元は情熱を注ぎ込み、かつて競い合った仲間の芸術家を呼び寄せ、展覧会を開催しました。奇抜で最先端の作品を展示すれば注目を集められると信じていました。しかし、客は一向に増えませんでした。次には海外からアーティストを招いて新作を制作しましたが、それでも客室は埋まらず、島の人々の反応も冷ややかなままでした。結果として、ホテル事業は縮小を余儀なくされ、社員はわずか3人にまで減ってしまいました。秋元自身も疲弊し、心は次第に荒んでいきました。
そんなある日、町役場から一本の電話がかかってきます。「倒壊寸前の民家を活用できないか」。それは築200年を超える古い家、島の人々から「角屋」と呼ばれてきた建物でした。荒れ果て、持ち主の高齢者には手に負えない状態になっていました。しかし、その場所は島民にとって長年の記憶が宿る大切な象徴でもありました。
秋元は角屋を目にした瞬間に直感しました。「ここなら、直島でしか作れないアートを生み出せる」。失敗を重ねた彼にとって、この出会いは再び挑戦するための希望の光だったのです。
角屋再生と島民参加型アート
1997年、ついに角屋再生プロジェクトが動き出しました。中心となったのは、現代アートの第一人者である宮島達男でした。しかし、初めて角屋を見た宮島は「ここでは作品を作るのは不可能だ」と首を横に振ります。荒れ果てた古民家はあまりに傷んでおり、制作環境としては到底ふさわしくないと考えたのです。
それでも、学芸員の秋元雅史はあきらめませんでした。彼は何度も宮島に直島の魅力を語り、「この場所にしかないアートを作るべきだ」と熱心に説得しました。その情熱に心を動かされた宮島は、ついに挑戦を受け入れます。
宮島が考え出したプランは革新的なものでした。角屋の内部にLEDのデジタルカウンター125台を設置し、それぞれの点滅する速度を島民一人ひとりに設定してもらうというものです。数字は生と死、そして時の流れを象徴し、参加者の「命のリズム」を作品に刻み込むという発想でした。
呼びかけに応じたのは、なんと5歳の子どもから95歳の高齢者まで125人。世代を超えて島の人々が一つの作品に関わることになりました。こうして誕生したのが、後に代表作と呼ばれる**「Sea of Time ’98」**です。暗い空間の中で光る無数の数字は、まるで島民一人ひとりの鼓動が重なり合っているように見え、訪れる人に強い感動を与えました。
再生を遂げた角屋は単なる美術作品ではなく、島民の誇りそのものとなりました。やがて直島では「自分たちも島を支える力になれる」と考える住民が増え、自主的にガイド活動を始める人々も現れました。かつて誇りを失っていた島は、アートを通じて少しずつ輝きを取り戻し、新しい未来へと歩み出していったのです。
ゴミの島と呼ばれた豊島の挑戦
一方で、直島からほど近い豊島は深刻な問題を抱えていました。1970年代から行われた不法投棄によって、島のあちこちに産業廃棄物が積み上げられ、海や土地が汚染されてしまったのです。全国に大きく報道されたこの事件の影響で、豊島は「ゴミの島」と呼ばれ、長く負のイメージに苦しむことになりました。かつては自然豊かで恵みを育んできた島も、観光客どころか島外の人々から避けられる存在となり、衰退は止まらない状況に追い込まれていました。
特に打撃を受けたのがみかん農家の山本彰治でした。丹精込めて育てた豊島みかんは、かつては地域の自慢でした。しかし事件後はブランド力が失われ、問屋から「商品名から豊島の名前を消してほしい」とまで言われるようになったのです。山本にとって、これはただの経済的打撃にとどまらず、故郷の誇りそのものが踏みにじられるような出来事でした。
そんな折、島に大きな転機が訪れます。豊島美術館を建設する計画が持ち上がったのです。コンセプトは「島の棚田を舞台にした美術館」。自然と共生する芸術の場をつくるという、従来にない壮大な構想でした。しかし問題となったのは、その舞台となる棚田がすでに荒れ果て、雑草に覆われていたことです。面積は東京ドーム2個分に相当し、再生には少なくとも数年が必要と見られていました。多くの人が「不可能だ」と口にするほどの難題でした。
それでも山本は諦めませんでした。島の未来を信じ、毎日曽我晴治のもとを訪ね、頭を下げ続けたのです。曽我は長年米作りを続けてきた農家で、最初は「棚田の再生は無理だ」と断言していました。しかし山本の粘り強い姿勢に心を動かされ、ついに協力を約束します。その後は口コミで仲間が集まり、最終的には島民17人が力を合わせて棚田再生に挑みました。
炎天下での作業は過酷でしたが、人々の努力は実を結び、1年後には見事に棚田が蘇りました。そして2010年10月、ついに豊島美術館(内藤礼「母型」)が開館します。白く有機的な曲線を描く建物は棚田と溶け合い、訪れた人々を静寂と感動に包みました。開館の年、人口わずか1000人の島に17万人もの来訪者が押し寄せ、大きな成功を収めたのです。豊島は「ゴミの島」から「アートの島」へと生まれ変わり、島民の誇りを取り戻すきっかけとなりました。
アートが広げた島々の未来
アートによる島の再生は、直島や豊島だけにとどまりませんでした。その動きはやがて瀬戸内国際芸術祭という形となり、瀬戸内海に点在する11の島々へと広がっていきます。芸術祭の開催によって、これまで忘れられていた小さな島々が再び注目されるようになったのです。
その象徴的な例が男木島でした。人口が200人を切り、過疎化が深刻で、学校は休校となり子どもの姿も消えていました。しかし、芸術祭をきっかけに島の魅力が知られると、全国から移住希望者が増え始めました。島に新しい家族が加わり、閉ざされていた小中学校が再び開校。校庭には久しぶりに子どもたちの声が響き、島民たちは大きな喜びを分かち合いました。
一方、かつて「ゴミの島」と呼ばれた豊島も確かな変化を遂げていました。美術館の成功とともに若い移住者が次々にやって来て、農業や観光に新しい力を注いでいます。長年傷つけられてきた豊島みかんの名も名誉を回復し、山本彰治が守り続けたブランドは再び誇りの象徴となりました。
そして2025年4月。瀬戸内国際芸術祭2025が開幕すると、世界中から訪れる観光客の数は100万人を超えました。瀬戸内海は「アートの海」としてかつてない輝きを放ち、人と人、人と自然を結びつける舞台となったのです。
番組に登場した島民の言葉が、この物語を端的に表しています。アートは決して「評価されるため」だけに存在するのではなく、「島を面白い場所にする」ためのもの。つまり、そこに暮らす人々の生活と誇りを取り戻し、外から訪れる人々とも心をつなぐ大きな力になったのです。瀬戸内海の島々は今、アートと共に新しい未来を切り開いています。
まとめ
今回の「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」は、衰退した瀬戸内海の島々がアートをきっかけに誇りを取り戻し、世界から注目を集めるまでの過程を描きました。秋元雅史や宮島達男、山本彰治といった挑戦者たちの熱意と、島民が一体となった努力が未来を切り開いたのです。直島や豊島の物語は「地域再生のヒントはその土地にしかない魅力をどう引き出すか」という問いを投げかけています。これからも瀬戸内の島々が、アートと人の力で進化を続けていく姿に注目していきたいです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


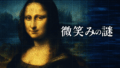
コメント