デジタル技術で追い詰める“暗黒船”とは?
2025年8月18日放送のNHK「BSスペシャル デジタル・アイ 暗黒船を追え」は、世界中の海で問題となっているIUU漁業(違法・無報告・無規制の漁業)の実態と、それをデジタル技術で監視する最前線を伝えた内容でした。魚が好きな私たちにとっても、食卓に並ぶ水産物がどのように獲られているのかを考える大切なきっかけになります。この記事では番組の要点をわかりやすく整理しました。
IUU漁業とは何か?
IUU漁業とは、各国のEEZ(排他的経済水域)に無許可で侵入して漁をしたり、定められた漁獲量を超えて魚を獲ったりする違法な漁業のことです。また、捕った魚の量をごまかしたり、禁止されている手法を使ったりするケースも含まれます。こうした船は「暗黒船」と呼ばれ、広い海で位置を消して活動するため摘発が困難です。今や世界の水産資源の約4割が過剰に捕獲されており、放置すれば将来的に魚が食べられなくなる可能性すらあると警告されています。
南太平洋での取り締まりとデジタル監視
番組で紹介されたのは、ニュージーランド出身の元漁師であるフランシスコ・ブラハさん。彼はマグロ資源を守る活動を続け、最新の監視技術を使って暗黒船を追いかけています。利用しているのはスターボードという船舶追跡ソフト。人工衛星からの位置情報を解析し、漁船の不審な動きを検出することが可能です。
実際にブラハさんがキリバス周辺で怪しい航跡を発見。韓国の冷凍運搬船がFADs(集魚装置)を落としながら動き回っていたと推測しました。この情報を元にタイ当局が港で調査し、結果として10億円相当のマグロの荷下ろしを阻止することに成功しました。
公海での“転載”の実態
さらに危険視されているのが公海です。ここはどこの国の管轄にも属さないため、監視が行き届きません。暗黒船はここで漁船と運搬船が合流し、魚を積み替える転載を行います。これにより漁獲量や漁獲場所がごまかされ、IUU漁業を助長することになります。調査の結果、多くの船がわざわざ遠回りしてまで公海上で転載を行っていることがわかり、国際機関でも規制の議論が始まっています。
中国船団の拡大と影響
番組では中国の遠洋漁業船の実態にも迫りました。中国は世界最多の約2500隻を所有し、漁獲量は世界全体の2割を占めます。衛星データからは、韓国の4倍にあたる約200万時間もの漁業活動が確認されました。
さらに中国はガーナをはじめとする各国に漁業インフラを整備する資金協力を行い、その見返りとして漁業資源を囲い込んでいます。ガーナでは国民のタンパク源の6割を魚が支えているため、中国船による乱獲は大きな社会問題にもなっています。
日本への影響と“闇マグロ”
日本の市場にもIUU漁業の影響は直結しています。豊洲市場で取引されるマグロの半分は輸入品であり、その一部が闇マグロと呼ばれる不正漁獲の可能性があります。実際に番組の調査では、中国の漁船から運ばれたマグロが日本の港で荷揚げされていたことが判明しました。
水産庁は漁獲証明書の提出を義務付けていますが、実際には相手国の管理を信頼しているだけで、日本側が詳細を追跡できていません。流通業者も納品書以外に確認手段がなく、チェック体制の甘さが浮き彫りになりました。
未来に必要な取り組み
水産学の専門家である勝川俊雄さんは、日本にもトレーサビリティ制度の導入が不可欠だと指摘しています。これは漁獲から消費者に届くまでの情報を一元的に管理する仕組みで、ノルウェーではすでに政府主導で実施されています。
また、番組では日本の漁業者がスーパーと連携し、自分たちの船で獲ったマグロにQRコードをつけて販売する試みも紹介されました。消費者が魚のルーツを確認できる仕組みは、今後の資源保護の大きな一歩となりそうです。
まとめ
「暗黒船」と呼ばれるIUU漁業は、遠い海の問題ではなく、私たちの食卓に直結する課題です。デジタル技術で不正を可視化する取り組みは大きな成果を上げていますが、それだけでは十分ではありません。消費者が正しい知識を持ち、持続可能な水産物を選ぶ意識を持つことも欠かせません。
魚を未来に残すために、私たち一人一人ができる行動が求められているのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


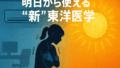
コメント