女性がいなくなった!男女平等の国アイスランドとは?
「世界で最も男女平等な国」と呼ばれるアイスランド。その背景には、1975年10月24日に起きた歴史的な出来事「女性の休日(Kvennafrí)」があります。この日は国内の成人女性の約9割が一斉に家事も仕事もやめ、社会に女性の存在の重要性を示しました。この記事では、当時の社会状況、行動の経緯、成果、そして世界への影響までを放送前情報から詳しく解説します。
1970年代アイスランドの男女格差
1970年代のアイスランドでは、女性が置かれていた状況は非常に厳しく、不平等が社会のあらゆる場面に根深く存在していました。たとえば、同じ仕事内容であっても、女性が受け取る賃金は男性の40〜60%程度にとどまるケースが多く、経済的な格差は明らかでした。さらに、職場においても女性は昇進の機会を得にくく、専門職や高い責任を伴うポジションへの道はほとんど閉ざされていました。
また、家庭に目を向けると、家事や育児といった家庭内労働は当然のように女性の役割とされ、その価値は社会的にも経済的にも正当に評価されていませんでした。多くの女性は日中に外で働いた後、帰宅してからも家事や子どもの世話を担い、結果的に「二重負担」という過酷な生活パターンを強いられていたのです。
さらに政治の世界でも女性の存在感はごくわずかでした。1970年代当時、国会における女性議員の割合はわずか5%前後で、他の北欧諸国と比べても非常に低い水準にありました。社会の意思決定の場に女性がほとんど関われない状況は、こうした不平等の固定化を一層深刻なものにしていたのです。
国連「国際婦人年」と行動のきっかけ
1975年は国連が定めた国際婦人年であり、世界各国で女性の地位向上や平等の実現に向けた取り組みが活発化した節目の年でした。この国際的な流れを受け、アイスランドでも変革の機運が高まり、フェミニスト団体である「レッドストッキンズ(Redstockings)」が動き出しました。彼女たちは、女性が社会や経済において果たしている役割を広く可視化し、その重要性を世間に強く訴える行動を計画します。
このとき提案されたのが、全国規模で女性が一斉に日常の労働を止めるという大胆なアイデアでした。しかし、過激な印象を避け、より多くの人が安心して参加できるようにと、行動の名称には「ストライキ」ではなく、あえて「女性の休日(Women’s Day Off)」という柔らかな表現を採用します。これにより、職場での解雇リスクを減らしつつ、主婦やパートタイム労働者などあらゆる立場の女性が気軽に加われる仕組みを整えたのです。
周到な準備と呼びかけ
1975年6月、アイスランド国内の5大女性団体の代表が一堂に会し、「女性の休日(Women’s Day Off)」を実現するための実行委員会が正式に結成されました。この委員会は、運動を全国規模へと広げるために、労働組合や各地の女性団体、さらには新聞・ラジオ・テレビといったメディアと密接に連携しながら準備を進めます。
具体的な広報活動としては、「なぜ女性が休日をとるのか?」という明確なメッセージを掲げたリーフレットを47,000部印刷・配布。さらに、街中や職場で目に入るよう、ポスターやステッカーを大量に制作し、衣服やカバン、窓などに貼られることで視覚的な訴求力を高めました。加えて、テレビやラジオを通じて繰り返し呼びかけることで、運動の存在と目的が全国民に広く知られるようになりました。
こうした名称の工夫や、計画的かつ多面的な広報戦略が功を奏し、当初は一部の活動家の間だけで始まった構想が、瞬く間に全国規模のムーブメントへと成長。参加の輪は驚くほどのスピードで広がっていったのです。
1975年10月24日「国が止まった一日」
この日、アイスランド国内では女性の90%以上が、有給の仕事だけでなく家庭での家事や育児といった無償労働までも一切行わず、社会から完全に“姿を消す”形となりました。結果として、国のさまざまな機能が一斉に停滞します。
まず、電話交換業務が止まり、全国的に通信が麻痺。新聞は発行されず、女性が多く働いていた印刷工場の稼働も完全にストップしました。さらに、学校は休校や短縮授業を余儀なくされ、教育現場も大きな影響を受けます。銀行や空港、さらには水産加工場といった産業の現場でも業務が停止し、経済活動全体が一時的に止まったのです。
首都レイキャビクでは、2万5千人もの女性が中心部の広場に集まり、大規模な集会が開催されました。街の風景も一変し、父親が子どもを職場に連れて行く光景や、スーパーでソーセージが売り切れるといった日常のちょっとした混乱も生まれました。
この衝撃的な一日は、後に「長い金曜日(The Long Friday)」と呼ばれ、アイスランドの歴史だけでなく、世界の女性運動史にも刻まれる象徴的な出来事となりました。
成功を後押しした要因
この運動が成功した背景には、まず圧倒的な参加率がありました。全国の女性の90%以上が一斉に行動を共にしたことで、社会や経済がほぼ停止し、その存在の重要性が誰の目にも明らかになったのです。さらに、事前から周到に仕組まれた全国規模の広報戦略も大きな要因でした。リーフレットやポスター、ステッカーの配布に加え、ラジオやテレビを活用した情報発信により、都市部から地方まで幅広い層にメッセージが届きました。
また、「ストライキ」ではなく「休日」と呼ぶことで、行動に参加する心理的ハードルを大きく下げ、雇用や立場への影響を不安視する人々も加わりやすくなりました。加えて、この抗議は暴力や混乱を伴わない平和的かつ象徴的な行動であったため、一般市民からの共感を得やすく、批判を最小限に抑えることができました。
当日の様子は国内だけでなく国際的な関心を集め、多くのメディアが大きく報道しました。この報道によって世界的にも「女性がいなければ社会は動かない」というメッセージが広がり、結果として政治や制度への圧力が一層高まっていったのです。
その後の変化と制度改革
1975年の「女性の休日」からわずか1年後の1976年、アイスランド議会は画期的なジェンダー平等法を成立させました。この法律により、職場や教育の場などあらゆる分野での性差別禁止が明文化され、さらにその実施状況を監督するための監督機関も設立されました。これは、法的な枠組みの中で男女平等を推進する大きな一歩となりました。
そして1980年には、世界で初めて民主選挙によって選ばれた女性大統領、ヴィグディス・フィンボガドティルが誕生します。彼女は大統領在任中、教育や文化、女性の地位向上に尽力し、象徴的存在として国際的にも高く評価されました。
その後も改革は続き、育児休暇制度の拡充や父親にも休暇を義務付ける「父親クオータ制」など、家庭内の平等を促す政策が次々と導入されます。さらに2018年には、世界で初めて同一労働同一賃金法を義務化し、企業に対して賃金格差是正の監査と改善を強く求める仕組みが整えられました。
現在では、アイスランドの国会議員の約半数が女性という高い水準を維持しており、この流れは1975年の大規模行動が切り開いた道のりの延長線上にあるといえます。
世界への影響
この1975年の「女性の休日」は、単なる国内の抗議活動にとどまらず、その後の世界的な女性運動のモデルケースとなりました。数十年後の2016年には、ポーランドで「ブラック・マンデー」と呼ばれる抗議行動が行われ、女性たちが一斉に仕事や家事を放棄し、中絶禁止法案や制度的不平等に反対の声を上げました。この行動は、明らかにアイスランドでの先例からインスピレーションを受けたものでした。
さらに2017年から2018年にかけては、複数の国で国際女性ストライキ(International Women’s Strike)が実施され、「仕事も家事もやめる」という形式の抗議が世界的な連帯の象徴として広がりました。これらの運動は、女性の労働と存在が社会の根幹を支えていることを改めて可視化し、各国での制度改革や意識変革を後押ししました。
こうして1975年のアイスランドの行動は、国境を越えたフェミニズムの連帯を促し、世界中で女性たちが権利を求めて立ち上がる際の象徴的な原点となったのです。
まとめ
1975年の「女性の休日」は、女性がいなければ社会が成り立たないことを国全体に突きつけ、制度改革と意識改革を同時に進めた歴史的な行動です。今回の放送では、その準備から当日の様子、そして長期的な影響までが証言とアニメで描かれる予定です。放送を見れば、男女平等の先進国と呼ばれるアイスランドがどうやってその地位を築いたのか、その原点を深く知ることができます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

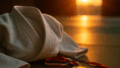

コメント