どんなご縁で ~ある老作家夫婦の愛と死~再放送で見えた認知症介護の原点
2025年5月23日放送の『時をかけるテレビ』(NHK総合)では、1988年に放送された名作ドキュメンタリー『NHK特集 どんなご縁で ~ある老作家夫婦の愛と死~』が再び紹介されました。今回はその再放送を通じて、作家・耕治人さんと妻・ヨシさんの晩年の生活、そして認知症と向き合う姿が深く描かれました。ゲストのにしおかすみこさんも、自身の体験を交えて思いを語りました。
再放送された「どんなご縁で」―認知症を描いた私小説をもとに

1988年、東京・中野区で作家の耕治人さんが82歳で亡くなりました。彼の晩年を描いたドキュメンタリー『どんなご縁で』は、自らの体験を基にした私小説をもとに制作された番組です。当時は「認知症」という言葉がまだ一般的ではなく、「痴呆」「ボケ」といった表現が使われていた時代でした。その中で、認知症を患う妻との生活を真摯に見つめた耕さんの姿が、多くの視聴者の心に深く残りました。
耕さんは、日常を題材にした私小説の名手として知られ、家庭での出来事を率直に書く作風でした。代表作のひとつである「天井から降る哀しい音」には、妻が火の不始末で火事を起こしたときの様子が描かれています。日常の中にある危うさと切実さを、耕さんは淡々とした筆致で綴っています。こうした作品は、当時の社会が見過ごしがちだった老いと向き合う視点を、文学として真っ向から取り上げたものでした。
また、番組では耕さんの若い頃の出来事も紹介されました。16歳のときに単身で訪ねたのが、宮崎県にある「新しき村」です。そこは作家・武者小路実篤が理想郷を目指して作った村でしたが、耕さんは「若すぎる」という理由で村には迎え入れてもらえず、その場を後にしました。
その後、耕さんは画家・中川一政さんのもとを訪れ、芸術や表現に触れる機会を得ます。中川さんとは長年にわたり交流が続き、耕さんと妻ヨシさんの夫婦関係にも関わっていきました。
耕さんの妻、ヨシさんは「主婦の友社」で編集者として働いていました。当時の女性誌は、生活や育児に関する実用情報を多くの女性たちに届ける重要なメディアであり、ヨシさんもそうした仕事に携わっていました。
-
結婚後、ヨシさんは編集の仕事を離れ専業主婦となります
-
ただしその後も、俳画や文章など多彩な活動を続けていたことが番組内で語られました
-
耕さんが初めて出版した小説は、ヨシさんとの生活を綴ったもので、夫婦の関係をそのまま文学に落とし込んだ内容でした
-
ヨシさんは独身主義を貫くと話していたにもかかわらず、耕さんがその考えを変えさせ、結婚に至ったという経緯も紹介されました
こうして、二人は互いに芸術と生活を支え合う存在となり、老いの時代にもその絆は強く残り続けました。番組では、その丁寧な描写を通して、認知症という言葉すらなかった時代において、夫婦がどのように寄り添って生きたのかをあらためて見つめ直す時間が描かれていました。
妻との生活、そして別れ
ヨシさんの認知症が進行する中で、家庭内の安全対策が求められるようになりました。ガスコンロの使用が難しくなったため、ガス警報器が設置されるなど、事故を防ぐための工夫が施されていました。ヨシさんは長年、俳画の創作活動にも励んでいましたが、症状の悪化により筆を置くことになり、最後に描いたのは、柔らかな表情を浮かべた観音様の絵だったといいます。その絵には、内面の静けさと穏やかさがにじみ出ており、彼女の心の姿が映し出されているようでした。
耕さんもまた、74歳のときに不治の病と診断され、身体的にも精神的にも大きな変化が訪れます。その後、彼は若き日に訪れた宮崎県「新しき村」を再び訪ねることとなりました。病を抱えた中での旅路には、過去との再会や自らの人生を見つめ直す意志が込められていたと考えられます。
やがて耕さんは東京医科大学病院に入院し、ヨシさんは老人ホームに入所。夫婦にとって初めての別居生活が始まりました。面会が叶ったある日、看護師がヨシさんを車椅子に乗せて病室へ連れてきます。付き添っていた年配の女性が「ご主人ですよ」と声をかけると、ヨシさんは少し間を置いて「そうかもしれない」と低く確かな声で答えました。
-
このときヨシさんは入れ歯をつけておらず、発する言葉の内容がはっきりと聞き取れなかった
-
それでも、耕さんは手を握り、冷たさを感じたことで涙があふれた
-
ティッシュを取ろうとしたがうまくいかず、ヨシさんはポケットを探して紙を取り出そうとしていた
こうした一つひとつの所作には、夫婦としての長い年月を感じさせる情感が宿っていました。
耕さんは入院中も、言葉を紡ぐ力が衰えながらも、小説を書く手を止めることはありませんでした。ある日のノートには、次のように記されています。
「真夜中の三時頃から息苦しく、ベッドの上で座ったりうずくまったりしている。たんが切れないか、我慢できずブザーを押す。舌がんという言葉が何度も浮かんだ。次の作がかけるかどうか不安である。書けなくても仕方がない気がする。あと12日で正月、82歳になることを考え、老人ホームの家内も82歳になる」。
満足に食べることも話すこともできない状態でも、彼はノートに言葉を残し続けていました。それを見た画家・中川一政さんは、「僕だったらワーワー言ってるだけだった」と感嘆の言葉をもらしたといいます。耕さんにとって小説とは、生きる力であり、自分の人生そのものを表す手段だったのです。こうして、夫婦の時間は静かに終わりへと向かっていきました。
にしおかすみこが語る、家族の介護
スタジオには、芸人でありエッセイストでもあるにしおかすみこさんがゲストとして出演しました。彼女は、自身の家族介護の経験をもとに、認知症というテーマに深く向き合った発言をしました。にしおかさんの母親も認知症を患っており、その日々の介護体験はエッセイとしてもまとめられています。
番組を観たにしおかさんは、1988年という時代に、認知症を真正面から描いたこのドキュメンタリーが制作されていたことに対し「驚いた」と話しました。当時はまだ「認知症」という言葉すら一般には知られておらず、「痴呆」や「ボケ」といった差別的な表現が当たり前のように使われていた時代です。介護保険制度も存在しておらず、家族だけで介護を担うのが常識とされていたことを考えると、この番組の存在自体が貴重だったといえます。
にしおかさんは、介護中に母親から受け取った手紙の言葉を紹介しました。
-
「来年はもっとひどくなる」
-
「それでも勘弁してちょうだい」
-
「迷惑かけます ごめんなさい」
これらの言葉は、認知症が進行する中でもなお母親が自身の状態を把握し、家族に対して気遣いを続けていたことを物語っています。介護する立場からは辛さや大変さばかりに目が向きがちですが、にしおかさんはそこにある本人の思いにもきちんと目を向けていました。
そして彼女は、次のように語ります。
「その人を見てリスペクトすることが大事」「認知症について知るよりも、その人について知ることが大事」
この言葉は、認知症を「病気」として一括りにするのではなく、ひとりの人間としてその人の人生や人格を理解しようとする姿勢の大切さを教えてくれます。にしおかさんの実体験に基づいたこの発言は、多くの視聴者にとって心に響くものとなったに違いありません。認知症介護において「知識」以上に「敬意」や「共感」が求められることを、あらためて感じさせてくれる一幕でした。
今も続く「老老介護」の現実

番組の後半では、現在の介護の現場を象徴するような事例として、岐阜県大垣市に住む86歳の桐山淳さんの生活が紹介されました。桐山さんは、81歳の妻を自宅で介護しており、妻は67歳のときにパーキンソン病と認知症を併発。
それから現在に至るまで、痰の吸引や食事の用意、日々の見守りといった多くの介護を一人で担っている様子が番組に映し出されました。
とはいえ、桐山さんは介護保険制度を利用しながら、以下のような支援も受けています。
-
専門スタッフによる入浴介助
-
機能回復を目指したリハビリ
-
その他生活サポートに関わる多様な福祉サービス
しかしながら、こうした支援があっても、日々の大半は自分の手で介護を行う「老老介護」の現実がそこにはありました。番組の中で、桐山さんはこう語りました。「彼女がここにいてくれることが、私の生きがい」。この一言には、長年連れ添ってきた夫婦の絆、そして介護をただの義務ではなく“日常の一部”として受け入れている姿勢がにじみ出ていました。
こうした実情は、かつて耕治人さんが妻ヨシさんと過ごした日々と重なります。昭和から令和へと時代が変わっても、高齢者が高齢者を支えるという構図は変わっていないことを痛感させられます。
実際に、厚生労働省の調査によると、同居する家族間での介護のうち「老老介護」の割合は63.5%にも上ります。また、軽度も含めて認知症の症状を持つ人は全国で1000万人を超えるとされ、超高齢社会における深刻な課題として浮かび上がっています。
このように、『時をかけるテレビ』は、過去に放送された耕治人夫妻のドキュメンタリーと、現在の介護現場のリアルを交差させることで、「家族介護のあり方」そのものを見つめ直す構成となっていました。過去の記録が、今の私たちに何を語りかけているのかを静かに問いかけてくれる内容でした。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。この記事の内容について感じたこと、皆さんの体験などもぜひコメントで教えてください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

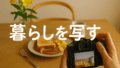
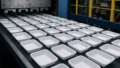
コメント