写真家・鈴木さや香と学ぶ“日常写真”の楽しみ方
2025年5月23日(金)よる8時からNHK教育(Eテレ)で放送される『おとな時間研究所 日常写真研究』では、写真家・鈴木さや香さんを講師に迎え、「誰にでもできる日常写真の楽しみ方」をテーマに、写真を通して日常の時間を見つめ直す方法を伝えます。自分の暮らしを撮ることが、心の整理や癒しに繋がる――そんな気づきを、写真家の視点から丁寧に紹介してくれる内容です。放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
鈴木さや香さんの写真が伝える“日常の美しさ”

鈴木さや香さんは、東京都出身の写真家です。広告写真の世界で培った確かな技術とセンスをもとに、現在は「暮らしを写す」というテーマで日常写真の魅力を発信し続けています。彼女の写真には、特別な舞台や派手な演出はありません。それでも、見た人の心をふっと和ませるような温かさが込められています。
・被写体は日常にあるもの…朝の食卓、差し込む光、散らかった子どものおもちゃなど、誰の暮らしにもある風景が主役です。
・「今」の記録としての役割…鈴木さんは、日々の写真を「未来に向けた記憶のしおり」として捉えています。
また、鈴木さんは写真集の出版や、日常写真に関するワークショップの開催も積極的に行っています。講座では、スマートフォンでも気軽に始められる撮影法や、暮らしをどう切り取るかといった構図の工夫まで、初心者にもわかりやすく教えています。撮影場所も特別なスタジオではなく、自宅や近所のカフェ、道ばたの草花などどこでも写真が撮れることを伝えています。
・「写真は誰でも始められるもの」という考え方を大切にしている
・フィルターや高価な機材に頼らない自然な表現が多い
番組では、こうした鈴木さんの視点をもとに、「写真を通して自分の時間を見つめ直す」ことの意味を深く掘り下げていく予定です。写真を撮ることで、忙しい毎日の中にも“気づき”が生まれ、自分の暮らしに対する愛着も増していく。そんな日常写真の可能性が紹介される見込みです。
何気ない1枚が、「今日の私を写す」かけがえのない記録になる――鈴木さや香さんの作品は、そんな視点をそっと教えてくれます。
自分らしい日常写真のテーマを見つけるには

日常写真をもっと楽しむためには、まず自分らしいテーマを見つけることが大切です。特別な場所に出かけなくても、身の回りに目を向けるだけで、魅力的な被写体はたくさん見つかります。鈴木さや香さんも「暮らしをそのまま写すことで、自分の時間を見直せる」と語っています。
・身近なものに注目する
毎日の生活にあるものが、テーマになります。例えば、テーブルの上のコーヒーカップや、脱ぎっぱなしのスリッパ、いつも見ている窓辺の光など。写真にすることで、普段は気づかなかった“美しさ”や“味わい”が浮かび上がってきます。
・感情に寄り添ったテーマ選び
「懐かしさ」や「少し切ない」といった感情を出発点にすると、写真に自然と気持ちが乗ります。たとえば、昔使っていた文房具や、祖母からもらった湯のみなど、自分の記憶とつながる物を撮ると、その人だけのストーリーが写真に込められます。
・色やかたちを意識する
視覚的に楽しいシリーズを作るには、テーマにルールを決めるのも効果的です。
— 赤いものだけを集める
— 丸い形のものばかりを撮る
— 朝の影だけをテーマにする
こうした縛りを加えることで、写真にまとまりが生まれ、見る人にも伝わりやすくなります。
テーマは難しく考える必要はありません。自分の気になるもの、好きなものを選ぶだけで、それが立派なテーマになります。そしてその積み重ねが、自分だけの「日常写真集」になっていきます。
写真を通して、自分が何に心を動かされているのかを発見する――それこそが、日常写真のいちばんの魅力です。
特別な機材がなくてもできる“身近なフィルター撮影”

写真を始めるときに「機材がないと難しい」と思いがちですが、鈴木さや香さんは「身近なもので十分」と教えてくれます。そのひとつが、身の回りにある物をレンズの前にかざしてフィルター代わりに使う方法です。これだけで、写真にやわらかさや色の変化を加えることができます。
・ストッキングや排水ネットを使う
レンズに薄くかぶせると、全体がふんわりとぼけて、やさしい印象のソフトフォーカスになります。特に逆光の時に使うと、光が滲んで幻想的です。
・セロファンやカラーフィルムを通す
赤や青、黄色のセロファンをかざすだけで、写真全体に色の雰囲気が加わります。被写体に合わせて色を変えれば、印象が大きく変わります。
・葉っぱや薄い布でフレーム効果をつくる
被写体の手前にかざすだけで、自然に画面の一部がぼけて奥行きが生まれます。光が透ける素材を使えば、柔らかい透過光もプラスされて、ナチュラルな演出ができます。
・CDケースやプラスチックの透明容器を当てる
斜めにかざすと、光が屈折して虹のような反射や歪みが入り、独特なアート感のある写真になります。特に晴れた日の窓際で試すと、ユニークな色の出方が楽しめます。
これらの方法は、すべて身の回りにある物だけでできるのが魅力です。高価なレンズやエフェクトソフトがなくても、アイデアひとつで写真の表情が変わります。そして、その「どんな物をどう使うか」は撮る人の自由。つまり、写真そのものに自分の感性をそのまま映すことができる手段でもあります。
簡単に始められて、仕上がりは人それぞれ。だからこそ、「同じ景色を撮っても、誰の写真とも違う一枚」が生まれます。遊び心を持って、いろんな素材で試してみることが、この“アナログフィルター”撮影のいちばんの楽しみです。
暮らしの中の“余白”を写し出す
鈴木さや香さんの写真には、ただ目に見えるものを記録するだけでなく、空気や時間、そして感情までもが静かに映し込まれています。その特徴のひとつが、「余白」の存在です。余白とは、写真の中で空白のように見える部分。けれど実際には、その空間こそが、見る人の想像を広げ、“心の余裕”を感じさせる重要な要素になっています。
・陽の光が床に落ちる瞬間
ただの光と影が作る模様でも、写真として切り取ると「その時間、その場にいた気配」を感じさせてくれます。
・読みかけの本のページ
手を止めたまま置かれた本は、読む人の気持ちや暮らしのリズムまでも想像させる存在になります。
・後ろ姿だけの子ども
顔が映っていないからこそ、見る人自身の記憶や想いが重なりやすくなる。それが余白の力です。
このような“何も起きていないように見える瞬間”を撮ることこそ、日常写真の深さと豊かさです。何かを説明しようとせず、そっと寄り添うように撮る。それが鈴木さんのスタイルでもあります。
写真には被写体が写りますが、同時に「撮った人のまなざし」も写ります。それは「何に気づき、どう見つめていたか」という記録でもあり、見る人にじんわりと伝わります。
番組では、おそらくこうした“感情を写し込む方法”や“余白の生かし方”についても具体的に紹介されるでしょう。何気ない瞬間を、ていねいに見つめ、ていねいに撮ることが、「暮らしの美しさ」を残す写真につながる。それが、鈴木さや香さんの写真が教えてくれることです。
自分の暮らしを“見つめ直す”時間
日常写真は、記録でもあり、自分を見つめ直す手段でもあります。「忙しさに流されがちな毎日を、一度立ち止まって見つめてみる」。その時間が、写真を撮ることで自然に生まれてきます。この番組では、そうした写真の力や意味も掘り下げてくれるでしょう。
これからの放送に注目!
番組では、司会に常盤貴子さんと杉浦友紀アナウンサーを迎え、視聴者と同じ立場から、鈴木さんの話を引き出してくれそうです。実演形式の撮影例や、鈴木さんの作品紹介、ワークショップ風景なども登場することが予想されます。
日常写真に興味がある人、何か新しい趣味を探している人にとって、きっと心に響く45分になるはずです。放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
放送予定:2025年5月23日(金)20:00〜20:45(NHK教育)
番組名:おとな時間研究所「日常写真研究」
出演:写真家・鈴木さや香/司会・常盤貴子、杉浦友紀
📺録画予約を忘れずに!
📝コメントや感想もお待ちしています!
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

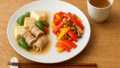
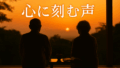
コメント