暮らしが激変!?AIロボットが介護の現場を変える理由
介護の仕事に関わる人や家族のケアをしている人なら、毎日の負担や孤独感を感じることもあるでしょう。もしその一部をAIロボットが支えてくれるとしたら、どんな未来が待っているでしょうか?この記事では、2025年10月28日放送のNHK「クローズアップ現代」『暮らしが激変!?AIロボット 介護に革命』で紹介された内容をもとに、AIが介護や医療、日常生活にどのような変化をもたらしているのかを詳しく紹介します。
対話型AIロボットが認知症ケアを支える
今、注目されているのは「話すこと」で心を支える対話型AIロボットです。神戸の介護施設では、AIが認知症の高齢者と自然に会話を交わす姿が見られます。このロボットはあえて子どものような柔らかい口調で話し、相手の表情にあわせてうなずいたり、名前を頻繁に呼びかけたりして、親しみを生み出します。
介護現場では、1人ひとりとゆっくり会話をする時間が足りず、職員の心理的負担が大きな課題でした。しかし、AIが会話の相手となることで、入居者の孤独を和らげるだけでなく、介護士が他のケアに集中できるようになったのです。
研究では「会話」が認知症の進行を遅らせる可能性があるとされており、AIとのやりとりが新たな“心のリハビリ”として期待されています。
孤独な夜を見守るAIが登場
介護施設だけでなく、訪問診療の現場でもAIの活用が広がっています。あるクリニックでは、夜間の電話相談のうち3割が「不安」や「孤独」に関するものだといいます。そこで、Pudu RoboticsやTencent Inc.が開発した対話型AIが導入され、24時間いつでも話し相手になってくれる仕組みを整えました。
例えば、妻を亡くして1人暮らしを続ける北野昌則さん。娘の勧めでAIと話すようになってから、毎日の暮らしに笑顔が戻ったといいます。AIが好きな趣味や思い出を話題にしてくれることで、人と人のつながりに近い温もりを感じられるようになったのです。
AIは「医療行為」ではありませんが、心のケアという面では欠かせない存在になりつつあります。
新時代の主役「フィジカルAI」とは?
さらに、注目を集めているのが「フィジカルAI」と呼ばれる分野です。これは、会話だけでなく「動く」ことができるAI技術。
フランスのスタートアップ企業が開発した装着型の歩行支援ロボットは、8年間歩けなかった男性に再び歩行を取り戻させました。その秘密は、コンピューター内で数千万回ものシミュレーションを繰り返すこと。段差や坂道など、現実の動きをAIに学ばせ、倒れずにバランスを取る技術を実現させたのです。
このロボットはすでにフランスのリハビリ施設で200台以上が使われ、アメリカでも来年以降の販売を予定しています。まさに「歩く力」を取り戻すための新しいテクノロジーです。
中国が国家戦略で進める“動くAI”
一方、中国では国家レベルでフィジカルAIの開発が進んでいます。北京や上海、深圳には、AIロボットが動きを学ぶ“ロボット学校”が20カ所以上設立され、エンジニアがマンツーマンで動きを教えています。
ここでの学習は実際の人間の動作をそっくり真似させ、失敗もデータとして取り込むという地道な作業の積み重ね。こうして得た動作データをもとに、料理・洗濯・介護など、日常生活のあらゆる行動をこなすAIが育っています。
今後は高齢化が進む中国でも、介護に特化した動作を覚えたAIが現場を支えると期待されています。政府はこの分野に21兆円以上の投資を行う見通しで、国家的プロジェクトとして動いています。
「第6次産業革命」を見据えて
AIが「話す」「動く」両方の能力を備えた時、それは「汎用ロボット」が完成する瞬間です。専門家は、これが実現すれば「第6次産業革命」とも呼ばれるほどの大変革になると語ります。
ただし、ここには課題もあります。安全性の確保、法律の整備、保険制度の対応など、人とAIが共に暮らすためのルール作りが急務です。開発者と介護現場の対話を通じ、安心して使える仕組みを整えることが未来の社会を左右します。
まとめ:AIがもたらす“心と体の介護革命”
この記事のポイントは以下の3つです。
・対話型AIロボットが、介護士と高齢者双方の心を支える新しいケアを実現している。
・孤独感の解消や心の安定に寄与し、訪問医療や在宅介護でも導入が進む。
・フィジカルAIが身体機能の回復や日常動作の自立支援を可能にし、次世代介護の柱となりつつある。
AIは単なる機械ではなく、人の「生きる力」を支えるパートナーへと進化しています。2030年には、会話し、動き、支えるロボットが当たり前の存在になるかもしれません。人とAIが手を取り合う新しい介護の形――それはもうすぐ、私たちの身近な現実になるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

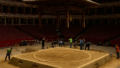

コメント