大相撲ロンドン公演、再び世界を魅了!土俵を運んだ職人たちの奮闘と力士たちの笑顔
相撲ファンの皆さん、「もしロンドンで本格的な大相撲が行われたら?」そんな夢のような出来事が、ついに現実になりました。2025年10月28日放送のNHK総合『午後LIVE ニュースーン』では、34年ぶりに開催された大相撲ロンドン公演の舞台裏が紹介されました。この記事では、伝統の技を海外で再現した土俵職人の苦労、現地ファンの熱狂、そして力士たちの素顔まで、余すことなく掘り下げていきます。
ロンドンの夜に響いた「どすこい!」の声
会場となったのは、ロイヤル・アルバート・ホール。ロンドンの中心に位置し、クラシックコンサートやバレエなど格式高いイベントが行われる歴史的ホールです。ここに本格的な土俵が築かれたのは実に34年ぶり。公演当日は、イギリス国内だけでなくヨーロッパ各地からもファンが集まり、会場の外には“SUMO”の文字が入ったTシャツを着た観客の姿もありました。
この日の放送でリポートを担当した相澤祐子キャスターは、かつてロンドンに在住していた経験を持つ人物。「日本の文化がこんなにも愛されているのを現地で感じるのは胸が熱くなります」と語り、感慨深い表情を見せていました。
土俵づくりの舞台裏 現地で再現された“日本の粘り”
驚くべきは、現地で一から土俵を組み上げた職人たちの努力です。公演2日前、作業は早朝から始まりました。コンテナ船で日本から運ばれてきたのは土俵の枠のみ。問題は「土」。日本の粘土質の土は植物検疫の制限で持ち込めず、ロンドンで調達した砂のような土を使うしかありませんでした。
このままでは締まりが悪く、力士が踏み込んだ瞬間に崩れてしまう危険があります。そこで職人たちは現地の土にセメントを混ぜ、独特の粘り気を人工的に再現しました。この発想と技術の柔軟さはまさに“日本の職人魂”。作業開始からおよそ10時間、ついに本格的な土俵が完成しました。
さらに、俵(たわら)にも工夫が。稲わらの持ち込みが禁止されていたため、化学繊維製の俵を使用。強度と質感を日本の本物に近づけるため、何度もテストが行われました。唯一、日本から持ち込めたのは俵を叩くビール瓶。叩く音と振動で締まり具合を確認する、日本ならではの技術がロンドンでも受け継がれていたのです。
熱狂するSUMOファン、2時間半の大興奮ステージ
いよいよ公演初日。開演4時間前の公式写真撮影会には、約100人のファンが列を作りました。イギリスだけでなく、フランス・ドイツ・スペインなどヨーロッパ各地からも観客が集結。力士のまわし姿を間近で見ようと、スマートフォンを手に笑顔があふれていました。
会場内に掲げられた取り組み表は、海外ファンにも分かりやすいように左から右へ読むスタイルに変更。細部にまで配慮された演出です。午後7時半の開演と同時に照明が落ち、場内に“どすこい!”の声と太鼓の音が響き渡ると、観客は総立ちに。約2時間半に及ぶ公演中、どの取り組みにも歓声と拍手が止みませんでした。
この模様はNHKワールド・プレミアムでも全世界に生中継され、SNSには「#SUMOLondon」のハッシュタグがトレンド入り。まさに“文化としての相撲”が世界へ広がった瞬間でした。
一番人気は豊昇龍!現地メディアも絶賛
今回の公演で最も注目を集めたのは、若手実力派の豊昇龍。取り組みのたびに歓声が沸き、現地メディアからは「SUMOの芸術的な動き」「静と爆発が交錯する舞踏のよう」と高評価を受けました。
大の里や安青錦、そして高安もそれぞれ熱戦を繰り広げ、観客の心をつかみました。特に高安関は取材の中で「観客のマナーが素晴らしかった。静かに見守り、拍手で称える姿に文化の深さを感じた」とコメント。相撲の精神である“礼節”が、言葉の壁を越えて伝わった瞬間でした。
力士たちのロンドン満喫エピソード
試合の合間には、力士たちもロンドン観光を楽しみました。ハリー・ポッターシリーズの大ファンとして知られる若元春は、大英博物館や“ハリー・ポッターの撮影地”を訪問。土俵上では真剣勝負の力士たちが、異国の文化に触れて笑顔を見せる姿が印象的でした。
また、千秋楽後にはロイヤル・アルバート・ホール内のバーで打ち上げが行われました。海外のスタッフと力士が同じテーブルを囲み、国境を超えた交流が生まれたのです。
まとめ:相撲は「世界共通の言葉」になった
今回のロンドン公演は、単なるイベントではなく、日本の“心”と“技”が世界へと伝わる文化交流の場でした。
この記事のポイントは以下の通りです。
・34年ぶりのロンドン公演は、伝統と革新が融合した歴史的瞬間だった
・現地で作られた土俵は、職人たちの技術と工夫の結晶だった
・豊昇龍・高安・若元春ら力士が異国の地でも観客を魅了した
ロンドンの夜に響いた「どすこい」の声。それは、日本の伝統文化が世界の人々に届いた証でした。次はどの国で、どんな土俵が築かれるのか。大相撲の“国際化”は、まだ始まったばかりです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


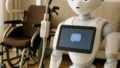
コメント