食の制限があっても一緒に楽しめる時代へ
「卵や牛乳が食べられない…」「動物性の食品を避けたい…」そんな悩みを抱える人が増えています。これまでなら、食事の場で「自分だけ別メニュー」ということも少なくありませんでしたが、今は違います。ビーガンから食物アレルギー対応まで、誰もが同じ食卓で楽しめる“食のバリアフリー”が全国に広がり始めているのです。2025年10月1日放送の『午後LIVE ニュースーン』では、その最新の取り組みと市場の広がりが紹介されました。
ビーガン食が広がる背景とシニア層の関心
番組では、ビーガンから食物アレルギーまでを含む「食のバリアフリー」の最前線が紹介されていました。最初に注目されたのは、植物由来の食材だけで作られるビーガン食です。
先月、東京都内の福祉団体が主催したビーガン食の体験イベントには、平日の昼間にもかかわらず50人以上が集まりました。参加者の中には、これまでビーガン料理に馴染みのなかった高齢者も多く、「ヘルシーで胃もたれしない」「野菜中心でも味がしっかりしている」といった声が上がりました。こうした反応を受け、主催団体は今後、地域の高齢者向け食堂や福祉施設でビーガン食メニューの提供を本格的に始めたいと考えています。
ビーガン食は動物性の食材を使わずに調理されるため、肉や魚、乳製品を避けたい人でも安心して食べられます。例えば、大豆ミートを使ったハンバーグや、豆乳ベースのクリームシチューなど、工夫次第で見た目も味も満足感のある料理に仕上げることができます。さらに、コレステロールが少なく消化にも優しいことから、健康を意識するシニア層にも注目されているのです。
背景には、生活習慣病予防や環境問題への関心の高まりがあります。肉の代わりに植物性の食材を選ぶことで、体への負担を減らすだけでなく、地球環境にも優しい食生活が実現できるとして、国内外で関心が広がっています。
急成長するビーガン市場とビジネスチャンス
ビーガンを含むベジタリアン人口は世界で約6億人にのぼるといわれています。これは、世界人口の1割近くにあたる大きな数字であり、年々その数は増加傾向にあります。特に欧米だけでなくアジアでも健康志向や環境意識の高まりから関心が強まっており、食のあり方に大きな変化をもたらしています。
観光庁のデータによると、このビーガン・ベジタリアン市場は2030年代には約17兆円規模に拡大すると予測されています。これは現在の約3倍にあたる規模で、外食産業や食品メーカーにとって無視できない巨大市場になりつつあります。観光地やホテルでも、海外から訪れるビーガン旅行者の受け入れ体制を整える動きが広がっています。
こうした潮流を背景に、東京ビッグサイトでは「ASIAN VEGAN CONNECT2025」が開催されました。アジア各地から多彩なビーガン食品が一堂に集まり、来場者は最新の商品や調理法を体験しました。日本国内だけでなく海外の企業も出展し、植物由来の代替肉、乳製品不使用のスイーツ、新しい発酵食品などが紹介されました。企業にとっては集客の場であると同時に、海外展開を視野に入れたビジネスチャンスの舞台ともなっています。
中でも注目されたのが、大阪の老舗かつお節会社が開発した「100%植物性のビーガンだし」です。長年培ってきた出汁文化の技術を生かし、かつお節を一切使わずに香りや旨味を再現することに成功しました。すでに大阪・福島区の和食店で導入されており、その結果、ビーガンの利用客が増え、店の新しい常連層を獲得する効果が出ているといいます。日本の伝統的な和食とビーガンの発想が融合することで、国内外の消費者にとって新しい食体験が生まれているのです。
さらに、植物性の出汁はアレルギーを持つ人にも安心して使える可能性があり、ビーガン向けだけでなく幅広いニーズに応える食品として期待されています。こうした商品開発の積み重ねが、今後の食の選択肢を豊かに広げていくことにつながっています。
食物アレルギー対応の進化
一方で、食物アレルギーに対応する取り組みも全国で大きな広がりを見せています。消費者庁のデータによると、日本では全人口の約1〜2%が何らかのアレルギーを持ち、さらに乳児では約10%にのぼるとされています。特に卵・牛乳・小麦はアレルギー症状を引き起こしやすい食品で、重度の場合はアナフィラキシーショックと呼ばれる危険な症状につながることもあります。そのため、安心して食べられる食品の選択肢が求められています。
北海道札幌市内のスイーツ店では、経営者自身が小麦アレルギーを持つ経験から、同じように制限を抱える人でも楽しめるお菓子作りに取り組んでいます。店で提供されるスイーツは、乳製品・卵・小麦・大豆といった主要なアレルゲンを使用せずに作られています。スポンジケーキには米粉を使用し、生クリームの代わりには豆乳ホイップやココナッツクリームを使うなど、代替素材を工夫することでふんわりとした食感や濃厚な味わいを実現しています。
来店するのはアレルギーを持つ子どもやその家族が多く、「みんなと同じケーキを食べられる」という体験が大きな喜びになっています。誕生日ケーキを注文する家庭も多く、見た目も華やかで写真映えするデザインにこだわっているため、イベントごとの特別な思い出づくりにも役立っています。
さらに、この店を経営する柴田愛里沙さんは、自身が食の制限で疎外感を抱いてきた経験を原点に、見た目も味も妥協しない「アレルギー対応スイーツ」を追求しています。代替素材を使っても食べる楽しさを損なわないよう工夫されており、アレルギーを持つ人とそうでない人が一緒に食べても満足できる仕上がりになっています。
こうした取り組みは、アレルギーを持つ人々の生活を支えるだけでなく、社会全体に「誰もが安心して食べられる場」を広げる大切な一歩となっています。
食のバリアフリーがもたらす未来
番組は最後に、食の制限がある人もない人も一緒に食卓を囲める社会が重要であると伝えていました。ただし、アレルギー対応スイーツもすべての28品目に完全対応しているわけではないため、購入時には必ずラベルを確認する必要があることも強調されました。ビーガンやアレルギー対応食の取り組みは、健康志向や観光産業にも結びつく新たな可能性を秘めています。まさに、誰もが安心して「おいしい」を共有できる時代へと向かっていることを実感させる特集でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

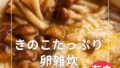

コメント