開業から半世紀、東京・埼玉・千葉をつなぐ71.8kmの移り変わり|2025年4月3日放送
2025年4月3日午前2時51分から放送されたNHK総合の番組『運転席からの風景 JR武蔵野線』では、1973年に開業したJR武蔵野線の全長71.8kmを、運転席からの視点でたどる鉄道旅が紹介されました。東京都府中市の府中本町駅から、埼玉県南部、そして千葉県船橋市の西船橋駅までを結ぶ武蔵野線は、首都圏の交通を支える大動脈です。沿線のベッドタウンの広がりや、貨物輸送の拠点としての役割、さらに地域の文化や歴史までを含めて描かれた内容は、鉄道に詳しくない方でも楽しめる構成となっていました。
武蔵野線の出発点・府中本町からの車窓旅
番組は府中本町駅を出発し、まずは西国分寺駅までの様子が映し出されました。この区間では、沿線の住宅街や雑木林が交互に広がり、郊外ならではの落ち着いた風景が印象的です。北府中駅では駅構内の複雑な線路構造も紹介され、武蔵野線が貨物線としても設計されたことを感じさせる場面でした。西国分寺駅に近づくと、中央線との接続が見えてきて、多くの乗客が行き交う様子が伝わってきます。
丸型ポストの残る街・新小平と、最長トンネルを抜けて新秋津へ
次に登場したのは新小平駅。ここには今では珍しくなった丸型ポストが設置されており、小平市ではこのようなポストが今も多く残っています。中には高さ2.8メートルの巨大な丸ポストもあるそうです。新小平から新秋津にかけては、全長4380メートルの武蔵野線最長トンネルを通過します。長いトンネルに入ると車窓は一気に暗くなり、静けさの中を走る列車の音だけが響きます。
開業当時の様子と拡張の歩み
武蔵野線は1973年4月1日、府中本町から新松戸までの区間で開業しました。当時は珍しかった自動改札機が12駅に導入されたことで話題となりました。都市近郊にありながら、先進的な設備を取り入れた新しい路線として注目を集めたのです。さらに1978年には西船橋駅まで延伸され、現在の路線が完成。沿線の都市化を支える大きな役割を果たしてきました。
貨物輸送の要、新座貨物ターミナルの存在
番組中盤では、新座貨物ターミナル駅が紹介されました。ここは武蔵野線の貨物輸送の中心的存在です。そもそも武蔵野線は都心の貨物線の混雑を緩和する目的で計画された路線であり、今でも旅客列車と貨物列車が同じ線路を共用していることは珍しくありません。大型の貨物列車が静かにすれ違う映像は、普段あまり見ることのできない貴重な場面でした。
新座から武蔵浦和、荒川を越えて
新座駅から武蔵浦和駅にかけての車窓では、広々とした住宅地や団地、そして荒川の鉄橋が見どころです。川の上を渡る場面では、橋を渡る風と鉄橋の音が響き、都市と自然の交わる場所を感じさせてくれます。周囲の景色も徐々に開け、武蔵浦和に近づくにつれ高層マンションが増えていく様子が確認できました。
鉄道ファンに人気の東浦和と、海を越えた205系
東浦和駅近くには有名な撮影スポットがあり、鉄道ファンに愛された205系車両の話題が紹介されました。この形式は2020年に武蔵野線から引退しましたが、インドネシアに300両以上が譲渡され、現地の都市鉄道で今も走り続けています。武蔵野線で活躍した車両が海を越えて新たな命を得ていることに、多くの視聴者が感動したことでしょう。
南越谷駅と阿波踊り、にぎやかな街の顔
南越谷駅周辺では、1985年から続く「南越谷阿波踊り」が紹介されました。毎年8月には60万人以上が訪れる大イベントで、地域を代表する夏の風物詩です。番組では踊りの様子も映され、鉄道と地域文化が密接につながっていることがよく分かる場面でした。また、駅のすぐそばには越谷貨物ターミナル駅もあり、貨物の輸送拠点としての側面も強調されました。
越谷レイクタウンと買い物の街
2008年に開業した越谷レイクタウン駅では、駅に隣接する日本最大級のショッピングモールが登場。東京ドーム約7個分の広さを誇り、休日には多くの買い物客が訪れます。鉄道が街づくりに果たしてきた役割を体感できるエリアのひとつです。
吉川美南・新三郷、操車場の記憶
吉川駅から吉川美南、新三郷駅にかけての沿線では、かつて存在した武蔵野操車場の跡地が再開発され、住宅地や商業施設へと変わった様子が紹介されました。武蔵野線の整備にあわせて開発されたこの地域は、鉄道が地域の未来を大きく変えていく力を持っていることを示しています。
三郷~南流山、江戸川の向こうへ
三郷から南流山までの区間では、江戸川を渡る鉄橋が印象的です。河川敷には公園やサイクリングロードが整備され、朝晩の時間帯には市民の姿も。車窓から見える水辺の風景は、都市生活の中の癒やしを感じさせてくれます。
新松戸で交差する路線、新たな接続点
新松戸駅では常磐線と交差しており、武蔵野線が放射状に延びる路線と接続する重要な拠点となっています。地域を横につなぐ役割を担っていることが、運行の様子からも伝わってきました。
市川大野から船橋法典、中山競馬場の玄関口
市川大野〜船橋法典間では、中山競馬場の最寄り駅である船橋法典駅が紹介されました。週末になると競馬ファンでにぎわう様子や、臨時列車の運行体制なども説明され、鉄道とイベントのつながりがよくわかる構成でした。
終点・西船橋、複数路線が交差するターミナル駅
最後に紹介されたのは西船橋駅。ここではJR総武線や東京メトロ東西線が乗り入れ、多くの乗客が乗り換えに利用しています。また、船橋市の特産「小松菜」にちなんだ「小松菜ハイボール」などのユニークなご当地グルメも紹介され、地域とのつながりが再び強調されていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

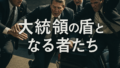

コメント