宮古島の暮らしの秘密
沖縄県の人気リゾート地・宮古島を舞台に、タモリさんが“島の暮らしの秘密”に迫った今回の『ブラタモリ』。自然の恵みと地質の特徴が、人々の生活と深く結びついていることが明らかになりました。サンゴでできた島ならではの特殊な環境が、住宅地や農業の工夫を生み、独自の文化を育ててきた様子が紹介されました。
【ブラタモリ】奇跡の岬と宮古馬に感動!サンゴが作った宮古島を地質探訪|2025年5月17日
サンゴでできた島には川がない?生活を支えた「イザガー」
番組は沖縄県宮古島の中心地である平良(ひらら)地区から始まりました。東京からおよそ3時間半の距離にあるこの地は、美しい海と豊かな自然に囲まれた観光地として知られていますが、番組では観光では見えない“暮らしの秘密”に迫っていきます。案内役を務めたのは、宮古島市教育委員会の久貝さん。地元の地形や歴史に詳しく、以前タモリさんが訪れた際にも注目された断層の存在が、実は今の生活に深く関係していると紹介されました。
島の住宅街を歩くと、ところどころに「イザガー」と呼ばれる洞窟が見られます。このイザガーは、島全体がサンゴ石灰岩でできていることによって生まれた地形です。長い時間をかけて雨水や風の浸食によって削られた岩の中に自然と空間が生まれ、そこに地下水がたまる仕組みになっています。洞窟の底には水を通さない泥岩層があるため、雨水が地下へ染み込んでもそこに留まってくれるのです。
こうした環境のため、宮古島には本州のような地上を流れる川や湖が存在しません。雨が降ってもすぐに地中へと浸透してしまうため、住民たちは水を地上でためることができず、地下水への依存が大きかったのです。
特に昭和30年代ごろまでは、イザガーの水が生活用水としてとても重要な役割を果たしていました。現在のように水道が整備される以前は、住民が日常的に利用する貴重な水源であり、毎日の暮らしに欠かせない存在だったのです。
イザガーの特徴や使われ方は、以下のように整理できます。
-
自然にできた洞窟で、地中に水がたまる仕組み
-
底に泥岩層があることで、地下水がたまる構造
-
島全体がサンゴ石灰岩でできているため、地上に水が残らない
-
川や湖がないため、イザガーが生活用水の中心だった
-
昭和30年代ごろまで使用されていた、身近な水源
宮古島という特殊な地質を持つ島で、自然の力と地形の仕組みを利用した暮らしが息づいていたことが、番組を通して改めて明らかになりました。現代ではほとんど使われていないものの、イザガーは今も島の人々にとって大切な記憶と知恵の象徴として残されています。
コメが育たない土地で栄えた伝統産業「宮古上布」

宮古島ではサンゴでできた地質のため水をためることができず、水田を作ることができません。そのため、本土のようにお米を育てることが難しく、代わりに選ばれたのが「苧麻(ちょま)」という植物でした。この苧麻は、乾燥に強く、アルカリ性の土壌でも元気に育つ性質を持っており、宮古島のような土地にぴったりだったのです。
苧麻の茎の皮をはいで取り出す繊維は、古くから織物に使われてきました。なかでも有名なのが「宮古上布(みやこじょうふ)」という織物です。これは、苧麻から採れる繊維を細く細く裂いて糸にし、織機で丁寧に織り上げて作られます。糸はとても細く、光を通すほどの薄さで、出来上がった布は半透明で涼しげな風合いが特徴です。
この宮古上布は、見た目の美しさだけでなく、その製造工程も非常に手間がかかります。
-
一反を作るのに必要な糸の長さはおよそ30km
-
完成までには半年以上の時間を要する
-
すべての工程が手作業で行われる
-
染めや織りの工程で高度な技術と根気が必要
さらに、番組ではかつてこの織物が米の代わりに年貢として納められていたという歴史も紹介されました。つまり、お米が育たない土地だからこそ、人々は苧麻を育て、布を織り、それを財産や納税の手段として活用していたのです。
このようにして生まれた宮古上布は、ただの布ではなく、宮古島の人々の暮らしと工夫の結晶でもあります。水が不足する土地に適した植物を選び、知恵と技術を重ねて生まれた伝統工芸。それは現代に受け継がれ、沖縄の誇る織物文化のひとつとして今も高く評価されています。
農業を救った“見えないダム”地下ダムのすごさ
宮古島では、地質がサンゴでできた琉球石灰岩のため、水が地中にすぐ染み込み、地表に水がとどまりません。そのため、雨が降っても川や湖ができにくく、農業用水を確保するのがとても難しいという課題を長年抱えてきました。特に、サトウキビやマンゴーのように一定量の水が必要な作物の栽培には不利な環境でした。
このような問題を解決するために、1980年代に世界初の農業用地下ダムが宮古島で造られました。これは、地表ではなく地中に水をためるという発想から生まれた画期的な仕組みです。具体的には、次のような構造になっています。
-
地下に「止水壁(しすいへき)」を設置し、地下水の流れをせき止める
-
壁の内側には水を通しにくい泥岩層があり、底や側面からの水漏れを防止
-
地上の地形を変えずに済むため、自然環境や土地利用に与える影響が少ない
この地下ダムの完成により、農業に使える水の量が大きく増加し、特にサトウキビの生産量は約1.5倍にまで向上しました。これは、単なる農業技術の進歩にとどまらず、島の経済や雇用にも好影響を与える重要な転換点となりました。
番組では実際に地下ダムの現場を訪れ、道路の下に張り巡らされた巨大な止水壁の存在や、その壁の奥にたまった地下水の様子などを紹介。さらに、この地下水はポンプで汲み上げられ、貯水槽にいったん蓄えられてから、ホースやパイプを通して畑へと運ばれていくという流れも明らかになりました。
この水の供給システムにより、これまで難しかったマンゴー栽培も可能になり、宮古島産マンゴーは現在、全国的にも高評価の特産品となっています。
現在では、既存の地下ダムに加えて新たに2つのダムが建設中であり、さらなる農地の拡大や作物の多様化が期待されています。地下に目を向けたこの発想と技術は、世界の水資源問題にも応用が可能なアイデアとして、今後ますます注目されることでしょう。
地下ダムで実現!宮古島産マンゴーの栽培

宮古島での地下ダムの活用には、農業の常識を変えるような工夫が詰まっています。なかでも特に注目されたのが、地下にたまった水を活用するための給水システムです。このシステムは、地下水をポンプでくみ上げ、いったん貯水槽にためてから畑ごとに配水するというもの。水を効率よく管理しながら、必要な量だけを届けることができるのが大きな特徴です。
この仕組みのおかげで、これまでの宮古島では不可能とされていた作物の栽培が現実のものとなりました。その代表例がマンゴーです。マンゴーは熱帯性の果樹である一方、水分が非常に必要な作物でもあるため、水源が安定しない地域では栽培が困難とされてきました。
しかし、地下ダムによる安定した水供給と、その水を農地へ計画的に配分できるインフラの整備により、宮古島ではマンゴー栽培が急速に広がっていきました。現在では、島内の多くの農家がこのシステムを活用し、高品質なマンゴーの生産を実現しています。
-
地下水はポンプでくみ上げてから貯水槽に一時保存
-
畑ごとに必要な分だけ配水することで無駄がない
-
年間を通じて水量の調整が可能なので、気候変動にも対応しやすい
-
地下ダムの恩恵により、宮古島産マンゴーは全国的に高い評価
このように、地質的なハンデを技術で克服した成果が、今の宮古島の農業を支えています。単に水をためるだけでなく、それをどう使うかまで考え抜かれたシステムは、マンゴーだけでなく、他の果樹や作物にも応用が可能であり、これからの島の農業の可能性を大きく広げるものです。
そして何より、こうした工夫の背景には、自然条件と向き合いながら暮らしてきた島の人々の知恵と努力があります。地下ダムは“見えない”存在でありながら、今の宮古島の暮らしと産業を支える“見えない主役”となっているのです。
地質と暮らしが結びつく島の知恵
今回の『ブラタモリ』は、単なる観光スポットでは見えない、地形と生活の関係に深く踏み込んだ内容でした。サンゴでできた土地だからこそ、地下水の利用や農作物の選定、織物文化など、宮古島独自の工夫や知恵が築かれてきたことがわかります。
番組の最後には、これらの地質や水に関する知識が未来の観光や農業、教育の財産になるというメッセージで締めくくられました。見えない地下の恵みと、それを活かす人々の知恵が詰まった“サンゴの島”宮古島の暮らしを、タモリさんの視点でじっくり味わえる30分でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

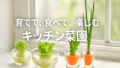

コメント