首の姿勢が崩れると何が起こるのか
特集は、50代のけいこさん(仮名)が「首のシワや姿勢の変化が気になる」と相談するところから始まりました。
整形外科医の高平尚伸さんによると、けいこさんは“カメ首”と呼ばれるような状態で、さらに巻き肩も加わって首が短く見えやすくなっているとのこと。
巻き肩で肩が前に巻くように入り込むと、本来まっすぐに伸びるはずの首が上に縮こまり、シワやたるみが目立つ原因に。
さらに問題の本質は『ファシア』と呼ばれる組織の硬さ。ファシアは筋肉・皮膚・内臓を含めて全身をつなぐネットワークのような存在で、ここがガチガチになると以下のような不調が起こりやすくなるそうです。
・肩こり
・頭痛
・めまい
・自律神経の乱れ
・全身のだるさ
姿勢のわずかな崩れが、首だけでなく全身の調子に影響することが分かります。
そんな自分の“首の硬さ”を知るためのチェック法も紹介されました。
・手のひらとひじを合わせたまま腕を上げ、ひじがあごより上に行くか
・背筋を伸ばして座り、痛くない範囲で頭を倒したときに地面と水平になるか
どちらも簡単で、自分の体の状態を知るきっかけになります。
すぐに効果が出やすい!首のファシアストレッチ
実際にけいこさんの首を整形外科医がチェックすると、首が45度ほどまでしか倒れない状態でした。そこで番組では、硬くなったファシアをほぐすためのストレッチを紹介。
まずは首の後ろ側をじっくり伸ばすストレッチ。
ポイントは「首の後ろの出っ張った骨を1つずつ倒していくイメージ」。アゴを軽く引き、首をゆっくり後ろへ倒して20秒キープ。これを2回行うだけで動きが変わる人も多いそうです。
次に、背中から腰にかけての後ろ側ファシアを伸ばす動き。
おしりを軽く引き上げるようにして全身の後ろを伸ばし、20秒キープします。
前側のファシアを伸ばす方法としては、手をまっすぐ前に伸ばし、肩甲骨を開いて20秒キープするストレッチも紹介されました。
これらはどれも短時間ででき、血流が良くなり全身のバランスが整うのが大きなメリットです。
さらに、専門医おすすめの“1分でできる全身の前側ファシアストレッチ”も登場。片ひざを90度に立てて両手を合わせ、そのまま天井に向かって反らすように伸ばす動きで、たった20秒でも胸からお腹まで伸びるのを感じられるストレッチです。
VTRのけいこさんは1か月間続けた結果、「長年悩んでいた肩こりが消えた」「襟元の肉がなくなった」と変化を実感したと話していました。毎日少しずつ続けることが一番の近道だと感じさせる内容でした。
今日から取り入れられる首の負担軽減ワザ
番組中盤では、クイズ形式で首まわりの負担を軽くする生活ワザが紹介されました。
・椅子には深く座って重心を安定させる
・タオルを引っ張って腕を上下に動かすと胸の筋肉とファシアが同時に動く
・料理中に片足を洗面器に乗せると自然に姿勢が整う
この“洗面器を台座にする方法”は、なんとスタジオのカメラマンも普段から実践しているとのことで、意外とポイントを心得ている人が多いのだと感じました。
また“ファシアをガチガチにしやすい趣味”として『ピアノ』と『ゴルフ』が紹介されました。
ピアノは長時間の前かがみ、ゴルフは左右非対称での動きが負担になるとのこと。視聴者からは「夫がピアノとゴルフをしているのでガチガチなのも納得」という声も寄せられていました。
理想の枕は玄関マット!?驚きの枕外来メソッド
続いて紹介されたのは、神奈川県相模原市にある整形外科クリニック。
枕外来を担当する睡眠研究歴25年の山田朱織さんが、“あなたに合う枕”の条件について語っていました。
山田さんによると理想の枕は『玄関マット』。
硬めのマットにタオルケットを蛇腹状に折って重ねることで、高さを2ミリ単位で調整できる優れものだそうです。
寝返りがスムーズにできることが首の負担を軽減し、肩こりや頭痛の予防につながるとの説明が印象的でした。
スタジオで実際に玄関マット枕の作り方が実演され、出演者たちも興味津々の様子でした。
美しい首を撮るためのちょっとしたテクニック
写真を撮るとき、首が太く見えたり短く見えたりして気になる…という悩み、誰もが一度は経験しますよね。
番組後半では、カメラマンのしろもんさんが“首を長く、美しく見せる撮影テクニック”を紹介していました。
・肩を軽く回して下げる
・胸鎖乳突筋のラインを出して縦の印象を強める
・「イィーネ!」のポーズで首のシワを自然に隠す
ゲストの横澤夏子さんと川村エミコさんも実際に挑戦して、楽しげに変化を確認していました。
いまオシ!LIVE・冬のごちそう“水ようかん”
福井県福井市からは、冬の定番『水ようかん』が登場しました。
水ようかんといえば夏のイメージがありますが、福井では冬にこそ食べられる伝統があります。水分量が多く夏は痛みやすいため、寒い季節にこそ味わいが深まるとのこと。
和菓子店では職人が40~50分間混ぜ続け、寒天とあんが分離しないよう丁寧に仕上げる姿が映し出されていました。
NHK【あさイチ】いまオシ!LIVE『水ようかん』福井・福井市 食べ比べ必見!丁稚ようかんの歴史と白い水ようかんの買える店まとめ|2025年11月26日
いまオシ!REPORT・鳴門のれんこんフルコース
徳島県鳴門市からは特産のれんこんを使ったユニークな料理が紹介されました。
れんこんカフェでは、なんと40種類ほどのれんこんメニューが並ぶそうで、ラインナップも圧巻です。
・蓮根ハンバーグ
・蓮根玉グラタン
・蓮根としらすの和風ピザ
・れんこんのからあげ
・蓮根入りガトーショコラ
さらに、れんこんを粉末にして練り込んだうどんを“わんこそば”のように食べるメニューも登場。地域の食材の魅力を存分に味わえる内容でした。
みんな!ゴハンだよ・豆腐カレーとさわやか和え物
料理コーナーでは、『豆乳ごまクリームの豆腐カレー』と『小松菜と柿のカレーあえ』の2品がスタジオに登場しました。
豆腐は紙タオルに包んで電子レンジにかけ、余分な水分を飛ばすひと手間を加えるのがポイント。玉ねぎを飴色になるまで炒めることで甘みが引き出され、トマトペーストやカレー粉との相性が深まります。
仕上げに無調整豆乳と豆腐を加えて優しい味わいのカレーに。
『小松菜と柿のカレーあえ』は、カレー粉を軽く炒ってレモン汁と塩で調味し、小松菜と柿を和えるシンプルで香りの良い一品。
試食した川村エミコさんは「黒ゴマの風味が広がって優しいカレーですね」とコメントしていました。
NHK【あさイチ】豆乳ごまクリームの豆腐カレー 作り方・レシピ|肉なしでもコクが出る“濃厚ヘルシー”の秘密|2025年11月26日
まとめ
今回の『あさイチ』は、首の姿勢を中心に全身を見直すヒントがつまった内容でした。
ストレッチ・姿勢改善・枕選び・生活の工夫・撮影術と幅広いテーマがつながり、体のケアと見た目の変化を同時に目指せる実践的な提案が盛りだくさん。
特に首まわりの不調や慢性的な肩こりに悩む方にとって、すぐに取り入れられるヒントがいくつも紹介されていました。
気になるところから少しずつ取り入れることで、首まわりが軽くなり、姿勢も気持ちもスッと整う1日が迎えられそうです。


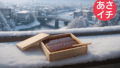
コメント