体重の新・健康リスク!“痩せ=健康”は思い込みだった!?
2025年4月17日放送の『あしたが変わるトリセツショー』(NHK総合)では、「体重」にまつわる新しい健康リスクについて徹底的に掘り下げました。これまでの「痩せていれば健康」「体重は少ないほどいい」という考え方が、現代の健康問題にどれほど危険をもたらしているかが明らかになりました。特に痩せ型女性に潜むリスクや、筋肉・骨との関係に注目した内容は、すべての世代にとって重要なメッセージとなっています。
「痩せていれば安心」はもう古い?見落とされがちな体のリスク

今回の番組では、痩せている人こそ健康に注意すべきという事実が明らかになりました。特に「低体重症候群」という言葉が取り上げられ、BMI18.5未満の女性の約5人に1人が該当しているというデータに驚きの声が上がりました。見た目はスリムで理想的に見えても、体の内側では栄養不足や筋肉量の減少が進んでいる可能性があるのです。
・「夜はスープだけ」「太ったと思ったら食べない」など、極端な食生活が当たり前になっている
・食事量が少ないと、必要な栄養が不足して代謝が落ちる
・結果として、肩こり・不眠・慢性的な疲労などを日常的に感じるようになる
特に印象的だったのは、こうした人たちの体調不良が「痩せているから大丈夫」という思い込みで見逃されていたことです。体が軽いのに、毎日がつらい。そんな“隠れ不健康”状態の女性が、実は少なくないことが分かりました。
また、コロナ禍をきっかけに、食べずにただ寝ているような生活習慣が増えたという点も指摘されました。動かないことで筋肉は急激に落ち、血流や代謝が悪化し、思わぬ病気につながる危険があるのです。
・「動かない・食べない」が続くと、糖を処理する力が落ちて糖尿病のリスクが上がる
・筋肉が減ると、血流が滞り脳卒中のリスクも高まる
・一見すると普通の生活でも、体の中では老化や病気の芽が進行している
こうした事実から、「痩せている人こそ健康に気を配るべき」というメッセージが強く伝えられました。体重が少ない=健康ではないという意識の切り替えが、これからの時代には必要です。見た目や体重の数字だけで判断するのではなく、体調や生活リズム、食事内容まで含めて“本当の健康”を考えることが大切だと、番組を通して改めて気づかされました。
体型の認識ズレが危険を招く?理想と現実のギャップに注目

番組では「日本人版ボディイメージスケール」を使い、参加者が自分の体型を客観的に見つめ直す取り組みが行われました。その結果、女性は実際の体型よりも太っていると感じやすく、男性は自分を実際よりも痩せていると思いがちという傾向が浮かび上がりました。このような“認識のズレ”が、無理なダイエットや栄養不足につながり、健康を損なう原因となっているのです。
・女性は「もっと痩せなければ」と思い込みがちで、必要な栄養まで削ってしまうことがある
・男性は自分を「痩せていてかっこいい」と認識しがちで、実際には筋力不足や内臓脂肪が多い場合も
・こうした勘違いが、健康的な体型づくりの妨げとなっている
また、正しい目安として紹介されたのが「BMI22」です。この数値は統計的に最も病気にかかりにくいとされる理想値であり、健康維持の基準となる体型として推奨されました。しかし、日本では痩せている人ほど「もっと痩せたい」と感じているケースが多く、実際の調査でもBMI22前後の人が「太っている」と答える例が多く見られました。
・BMI22は、健康的な食事と適度な運動をしていれば自然に到達しやすい数値
・見た目よりも「健康リスクが少ない数値」という観点で評価すべき
・高齢者の場合はBMIが22よりやや高い方が、骨折や病気リスクが低いことも分かっている
このように、自分の体型を客観的に把握することは、健康管理の第一歩です。理想の見た目を追い求めるのではなく、「健康で動ける体」を意識することで、極端なダイエットや偏った食生活から離れることができます。
大切なのは、体重や体型の数値にとらわれすぎず、筋肉や骨、内臓の働きなど“体の中身”を意識すること。番組が伝えたように、「細ければいい」という価値観から抜け出すことが、これからの健康づくりには欠かせません。
痩せすぎは骨にも悪影響!若い女性の骨密度に異変

番組では、痩せすぎが骨に与える深刻な影響についても詳しく取り上げられました。実際に骨密度を測定した結果、見た目は若くても、骨年齢が実年齢より10歳以上も上だった女性が多く見つかりました。これは体重が軽いため、骨に十分な負荷がかからず、骨を作る細胞が働きにくくなるからです。
・骨は刺激を受けて強くなるしくみがあるが、体重が軽いと刺激が足りず骨が弱くなる
・特に痩せた人は、歩く・走るなどの動作でも骨への圧力が少なく、骨芽細胞の働きが低下する
・骨密度が低くなると、将来の骨粗しょう症や骨折のリスクが高まる
さらに問題なのは、脂肪が少ないことによるホルモンバランスの崩れです。女性の体内では脂肪が十分にあると、エストロゲンという女性ホルモンが安定して分泌されますが、痩せすぎて脂肪が不足すると、このエストロゲンの分泌が減ってしまいます。
・エストロゲンには骨を壊す細胞(破骨細胞)を抑える働きがある
・ホルモンが減ると、骨が壊されやすくなり、新しい骨も作られにくくなる
・食事制限や無理なダイエットで生理が止まった経験がある人は、骨密度が急激に低下している可能性も
こうした骨の弱体化は、特に10代の若い世代で深刻です。この時期にどれだけ骨を強くしておけるかが、将来の健康を大きく左右します。調査では、痩せ型の中高生ほど骨密度が低く、骨にヒビが入ったり、捻挫から骨折に至ったりするケースも見られました。
・成長期に栄養が足りないと、骨の材料そのものが不足してしまう
・運動不足が重なると、骨に力が加わらず骨量が増えない
・この時期に弱い骨のまま成長すると、大人になってから取り戻すのは難しい
つまり、「痩せている=美しい」と思い込んで過ごしてしまうことで、将来の健康の土台となる“骨”が静かに弱っていくのです。栄養バランスの良い食事と、日常的な運動、そして適正な体重を維持することが、骨の健康を守るうえでとても大切です。今しかできない“骨貯金”を怠らないよう、若いうちから意識して生活を整えることが求められます。
筋肉量と糖代謝の関係が明らかに

番組では、見た目では分かりにくい「筋肉の量」が、健康にどれほど大切かが具体的に紹介されました。糖を体に取り込んでエネルギーとして使う働きを担っているのは、実は“筋肉”です。そのため、筋肉が減ると糖が血液中に残りやすくなり、血糖値が高くなってしまいます。これが、痩せていても糖尿病になる人がいる理由のひとつです。
・筋肉は“糖の受け皿”ともいえる存在で、筋肉量が多いほど血糖の処理がスムーズになる
・逆に筋肉が少ないと、糖が体に取り込まれず、血糖値が高いままになりやすい
・糖尿病は太っている人だけでなく、筋肉不足の痩せ型にも多いという新しい常識
握力測定の結果も衝撃的でした。参加した女性5人全員が、75歳以上の平均よりも低い握力という結果で、普段から運動や筋トレの習慣がないことが、体の機能にも表れていました。握力は筋力全体のバロメーターともいわれ、糖代謝力や生活機能とも関係があることが分かっています。
・握力が低いと、日常の動作にも支障が出やすく、活動量の低下が進む
・活動量が減ると、筋肉はさらに減り、代謝もどんどん悪化
・この悪循環が、見えないうちに糖尿病などの病気を進行させてしまう
さらに番組では、バーミンガム大学の研究も紹介されました。平均72歳の男女がたった2週間、1日1500歩以下の生活を送っただけで、ステーキ2枚分の筋肉が失われたという驚くべき結果です。この研究では、若い人でも活動量が減れば同様の筋肉減少が起こると警告されています。
・運動しない生活は、年齢に関係なく筋肉の減少を引き起こす
・筋肉が減ると、糖を処理する能力もすぐに落ちる
・たとえ見た目に変化がなくても、体の内側では代謝力がどんどん低下している
つまり、筋肉は「動くため」だけでなく、血糖値をコントロールするためにも欠かせない“代謝の要”です。見た目が痩せていても、筋肉が足りなければ健康ではありません。しっかり食べて、体を動かすことが、糖代謝の正常化と病気の予防につながるということが、番組を通して明確になりました。筋肉は年齢を問わず育て直せるため、今すぐできる習慣の見直しこそが、未来の健康を守るカギになります。
筋肉と骨を増やすための1か月チャレンジ
参加女性たちは、筋肉と骨の改善を目指して1日3食しっかり食べ、週3回の筋トレ、1日8000歩歩くという1か月チャレンジに挑戦。その結果、全員が太ももの筋肉量を増やすことに成功しました。体重は増えた人もいれば減った人もいましたが、共通して「体重を前向きに受け止められるようになった」という心の変化が印象的でした。
適正な食事、筋肉量の確保、そして体重を数字だけで判断しない価値観が、これからの健康の基準となることを番組は教えてくれました。
体重はただの数値ではなく、筋肉・骨・ホルモン・代謝など全身の健康を支える重要なサインです。「痩せ=美しさ=健康」という思い込みから抜け出し、バランスの取れた体型こそが本当の健康だということを、今日から意識してみてはいかがでしょうか。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


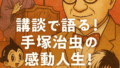
コメント