「寺や神社が大売り出し中!?」宗教法人をめぐる驚きの実態と“掛け持ち宮司”の元旦密着レポート|2025年4月5日放送
2025年4月5日放送のNHK総合「所さん!事件ですよ」では、全国の寺や神社が今“売り出し中”という衝撃の実態を追いました。水面下で広がる宗教法人の売買、制度のスキを突く悪質な脱税、そして神社を守るために元旦に8社を駆け巡る宮司の姿。今回の放送では、日本の宗教と信仰の現場が直面する現実が明らかになりました。
宗教法人に届いた1通のFAXが示す異変
北海道にある十三仏霊場のひとつ、金胎山 真言院。そこに突然送られてきた1枚のFAXが、今の宗教界に起きている異変を物語っていました。FAXの内容は、「宗教法人の法人格を売ってほしい」という驚くべき提案。送信者は、宗教法人の売買を専門にしているブローカー業者でした。
FAXには、売却のメリットや取引の実例が記されており、価格はどれも1億円以上。それはもはや宗教施設ではなく、「高額物件」として取り扱われている実態を示しています。ブローカーの言葉には「今売れば高額報酬が期待できる」といった文言もあり、信仰の場が商品として扱われている現実に衝撃が走ります。
-
物件価格は軒並み1億円を超えており、商業物件と変わらない扱い
-
宗教法人格という“箱”が価値を持つため、建物の状態や信仰の有無に関係なく買い手がつく
-
ブローカーは宗教施設を“資産”として売り込んでいる
背景にあるのは、宗教施設の深刻な経営難と後継者不足です。文化庁が発表した統計によれば、全国にある約7500の単立宗教法人(本山などに属さない寺院)のうち、11%が無収入、35%が年収100万円未満という厳しい現状が明らかになっています。
-
無収入や年収100万円未満の寺社は、日々の維持費すらまかなえない
-
住職や宮司が高齢化し、跡継ぎがいないまま放置されている寺も多数
-
屋根の修理や祭事の費用すら捻出できないという声が各地から上がっている
そうした中で、ブローカーのような業者が現れ、「高く売れる」「今がチャンス」といった甘い言葉を投げかけます。施設を手放す側は、経営や修繕の苦しみから解放されるかもしれませんが、その代わりに、地域の信仰の場が消えていくことになります。
-
売却後、寺は納骨堂や観光施設、時には全く異なる用途に転用されることもある
-
地域住民の中には、突然の閉鎖に戸惑う声も出ている
-
一度失われた神仏の場は、二度と元に戻せない
このFAXは、単なる営業行為ではなく、日本の宗教文化と信仰の根幹が揺らいでいる証です。宗教法人が“買える”時代。その現実を前に、制度の見直しと、地域全体での信仰の再評価が求められています。
宗教法人の売買を可能にする制度の隙
宗教法人は、もともと信仰の場として守られる存在ですが、その制度には大きな落とし穴があります。売買そのものを禁じる明確な法律が存在しないため、「代表者の変更登記」だけで実質的に売却が成立してしまうのです。
とくに問題となっているのが、「単立宗教法人」です。これは本山などの包括宗派に属しておらず、内部の判断だけで代表者や役員の交代が可能な法人です。外部の人物が代表に就任しやすく、資産の処分や管理を自由に行えるため、ブローカーの標的になりやすいのが現実です。
-
宗教法人の代表変更は、役所に登記申請するだけで完了
-
包括宗派の審査を経る必要がないため、買収がしやすい構造
-
内部の規定次第で、会議を開いたという形式的な手続きで代表が交代できる
番組で取材された大阪の実業家は、この制度の隙を悪用した人物です。彼は複数の会社を経営する一方で、宗教法人を取得し、「宗教法人は税金がかからない」と公言しました。なんと、会社の収益を“寄付”という形で宗教法人に移し、課税を回避していたというのです。
さらにその宗教法人の拝殿には、神棚や異なる宗教の神々の絵まで掲げられていたとのこと。形だけ「信仰がある」ように見せるための装飾で、役所の職員が来た際には写真を撮らせるだけだったといいます。
-
神棚や絵を用意し、「宗教施設らしさ」を演出
-
“信者役”として数人を用意し、活動の証拠写真を撮影
-
実態のない形式的な活動で、行政の目をくぐり抜ける
このように、信仰の実態がなくても、外見を整えただけで「活動中の宗教法人」と見なされることが多く、解散や是正措置には至らないのが現状です。制度を守りながらも、その中で悪用される隙が多すぎるため、行政としても効果的な対応が難しくなっています。
-
実際に活動しているかどうかを判断する手段が少ない
-
確認作業は書類と写真が中心で、現地調査にも限界がある
-
形だけ整えれば、「形式上の宗教法人」として生き残れてしまう
このような事例は氷山の一角で、今後も同様の手口が全国で行われるおそれがあります。制度の根本的な見直しと、監視体制の強化が急務となっています。宗教法人が本来の役割から外れ、税制の抜け道として利用されている現実は、日本の信仰と法制度の危うさを物語っています。
税制優遇とマネーロンダリングの温床に
宗教法人が悪用されているのは、脱税だけにとどまりません。相続税対策やマネーロンダリング(資金洗浄)といった違法行為の温床になっている実態も明らかになっています。宗教法人は本来、信仰を目的とする法人であるため、活動内容が限定されていると思われがちですが、現実にはその枠組みが曖昧なまま放置されているのです。
文化庁はこの問題に対し、“実態のない宗教法人”を「不活動宗教法人」と位置づけ、全国の都道府県に対して調査を要請しています。番組では新潟県庁の取り組みに密着し、現場の実情が紹介されました。
-
新潟県では360件の不活動宗教法人が確認されている
-
解散命令を請求できたのはわずか5件にとどまる
-
代表役員が死亡していても、花が供えられていれば“活動中”と判断されるケースも
この背景には、調査に必要な証拠をそろえるハードルの高さがあります。解散命令を出すには、「礼拝施設が2年以上存在しない」「1年以上宗教活動がない」「代表役員や代務者が1年以上不在」といった条件をすべて満たす証拠を揃え、裁判所に請求しなければなりません。
-
写真や記録、住民からの聞き込みなど複数の証拠が必要
-
担当職員の人数が限られており、調査が進まない自治体も多い
-
予算不足で実地調査ができない場合もあり、行政の手が届きにくい現実がある
番組では、実際に宗教法人を買った大阪の男の証言も紹介されました。彼は、宗教活動を偽装するために大阪から5人の“信者”を現地に呼び、活動している様子を写真に撮らせたと話しました。その写真を見た役所の職員は、「宗教活動が行われている」として帰っていったといいます。
-
外観だけ整えれば「活動中」と認定されてしまうケースがある
-
神棚や祭具を飾っているだけで形式上の信仰と見なされることも
-
「形式の整備」で行政の目をかいくぐる手法が既に広まっている
こうした“擬装活動”によって、本来は解散対象となるべき宗教法人が生き残り続けてしまうのが現状です。しかもそれらが、相続税対策や海外資金の隠し場所として使われるとなれば、問題は極めて深刻です。
宗教法人のあり方は、単に信仰の問題だけでなく、制度そのものの信頼性にも関わる社会的な課題になっています。文化庁による制度改革とあわせて、現場の監視体制や法律の見直しも急がれています。宗教の名を借りた金の流れが放置されていれば、日本の宗教文化自体の信頼も失われかねません。
解散を逃れる巧妙な手口と限界ある監視体制
宗教法人は毎年、活動状況を都道府県に報告する義務があります。これは本来、法人がきちんと宗教活動を行っているかを確認するための制度ですが、現実にはそのチェックが機能していないケースが多く見られます。背景には、自治体の人手不足や予算の限界があります。
たとえば、報告書に写真が1枚添えられていれば、そこに数人の信者らしき人が写っているだけで「活動の証拠」とされることがあるのです。実際の活動があるかどうかを直接確認することは少なく、書類だけで判断されてしまうのが実情です。
-
宗教法人が提出する活動報告は基本的に自己申告制
-
書類の不備や虚偽があっても、確認のための現地調査が追いつかない
-
自治体の担当者が1人しかいない、専任職員が不在という地域も多い
番組では、偽装の手口も紹介されていました。宗教法人を買った大阪の実業家は、活動実態があるように見せかけるために信者役として5人を大阪から連れてきて写真を撮らせたと証言しています。写真には神棚や装飾も映され、形だけは「立派な宗教施設」に見えるように細工されていたといいます。
-
建物の外観をきれいに整え、内部に神具を飾る
-
訪問のタイミングに合わせて“信者”を用意し、信仰の場を演出
-
実際には活動していなくても、写真と報告書だけで形式上の活動と認定される
このように、解散すべき不活動宗教法人が巧妙な手口で制度の網をすり抜けているのが現実です。行政が気づいたときにはすでに法人格が悪用され、脱税や資金洗浄に使われてしまっている場合もあります。
文化庁はこうした状況を重く見て、全国に不活動宗教法人の整理を進めるよう働きかけているものの、現時点では本格的な法改正や抜本的な対策には至っていません。法人の登記や活動報告の透明性を高める制度づくりが急務とされています。
-
法人の実態調査に予算を充てられない自治体では、確認作業自体が進んでいない
-
裁判所に解散命令を出してもらうには、厳密な証拠と法的手続きが必要
-
偽装の難易度が低く、制度の抜け道がそのまま放置されている状態
宗教法人制度は、本来は信仰の自由と地域社会のために作られた仕組みです。しかし、この制度が今、信仰とはかけ離れた使われ方をされていることが深刻な問題になっています。信仰を守るためにも、制度を悪用から守る法整備が求められています。
神社を守る「掛け持ち宮司」の元旦密着
一方、信仰の場を守るために奮闘している人もいます。神奈川県藤沢市の白旗神社の宮司・鈴木大次さんは、なんと8つの神社の宮司を兼務しています。特に元旦は一年で最も忙しい日。番組では、午前0時からの1社目を皮切りに、朝6時から昼12時まで7か所を“はしご”する姿に密着しました。
-
各神社での祝詞奏上や祈願祭を分刻みでこなす
-
移動はすべて車。待っている地域住民のために時間通りに到着
-
1社につきわずか10~15分で儀式を終えるタイトなスケジュール
体力的にも精神的にも過酷な元旦ですが、地域の信仰を絶やさないため、宮司は全力で神事を続けています。今や全国には約8万の神社がありますが、宮司は約1万人しかいません。神職の不足は深刻化しており、こうした掛け持ちは今後さらに増える可能性があります。
今回の放送は、宗教法人制度が抱える抜け穴と、信仰の現場を支える人々の姿を対比的に描いていました。所ジョージさんは「いままでで一番、重いかもしれない」と語り、木村佳乃さんも「人の信じる心を悪用してお金を得るのは一番よくない」とコメントしていました。
このテーマは単なる制度問題ではなく、日本の信仰と文化、そして地域社会の在り方に深く関わる問題です。私たち一人ひとりが、宗教法人の現状と未来を考える必要があると感じさせられる内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

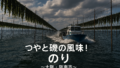

コメント