大阪・阪南市で育つ極上のりに密着!300手間の伝統養殖と磯の風味を味わい尽くすレシピまで|2025年4月3日放送回まとめ
2025年4月3日放送のNHK「うまいッ!」では、日本の食卓に欠かせない存在である「のり」を特集。今回の舞台は大阪・阪南市。ここで作られるのりは、ツヤのある見た目と磯の香り、しっかりとした味わいで評判です。番組では、のりの養殖から収穫、加工、そして家庭でも楽しめる料理まで、さまざまな角度からのりの魅力に迫りました。また、地元の子どもたちへの伝統継承の取り組みも紹介され、阪南市ののりが地域に根ざした存在であることが伝わってきました。
つやつやののりができるまでには「300手間」以上の作業がある
大阪・阪南市は、関西国際空港からほど近い場所にある港町で、昔からのりの養殖が盛んな地域です。ここで作られるのりは見た目の美しさだけでなく、食べたときに感じる香りや味の深さが魅力です。その背景には、「300手間」と言われるほど細かな工程が積み重ねられているという、手間ひまかけた伝統の技があります。
まずは「種付け」。白く細い網にのりの胞子をつける作業からすべてが始まります。この種付けをした網は、海の中に張り込み、ゆっくりと成長させていきますが、ここで欠かせないのが「干出(かんしゅつ)」と呼ばれる作業です。干出とは、日中の一定時間、網を海面から引き上げて、太陽にさらす作業のこと。自然の力を借りて、のりの葉を乾かすことで、雑菌の繁殖を防ぎ、健康でおいしいのりに育てることができます。
この干出作業は毎日行われ、約3週間続ける必要があります。天候や潮の満ち引きを見ながら、漁師たちはベストなタイミングを判断して、何度も海へ足を運びます。のりが1センチほどの大きさまで育ったら、一度マイナス25度の冷凍庫に保管し、成長のピークに合わせて「本張り」と呼ばれる本格的な養殖網への張り替えを行います。
豪快な専用船による収穫!阪南スタイルのダイナミックな方法
のりの収穫方法も、阪南市ならではの特徴があります。専用の漁船が養殖網の下に突入するように潜り込み、のりを一気に回収するという、非常にダイナミックな方法が取られています。海の中でたっぷりと育ったのりを、素早く、かつ傷つけずに収穫できるこの方法は、効率がよく、鮮度も落ちにくいため、阪南市ののりづくりには欠かせません。
この収穫のシーンは、言葉では伝えきれないほどの迫力があります。船が海面を割って網の下に突っ込み、機械が網を引き上げる動きは、まさに職人技と機械の融合。大量ののりが一度に収穫されていく様子は、見ているだけでも圧倒されます。
工場で丁寧に加工され、香り豊かな板のりへ
収穫されたのりは、その日のうちに加工場へ運ばれ、洗浄、裁断、成型、乾燥といった工程を経て、私たちが普段目にする「板のり」へと加工されます。阪南市の加工場では、温度や乾燥時間を微調整しながら、香りや色ツヤが最大限に引き出されるように丁寧に仕上げられています。
また、乾燥の過程でも、のりの状態に応じて細かい調整が必要です。湿度や空気の流れ、のりの厚みなどに合わせて作業を行うことで、破れにくく、しっかりとした食感のある上質なのりが完成します。こうして一枚一枚に手間と愛情が詰まったのりが出来上がっていくのです。
食べて実感!のりの佃煮でごはんがすすむ
スタジオでは、阪南市産ののりで作られた「のりの佃煮」が登場しました。炊きたての白ご飯にのせて味わうと、しっかりしたうまみと自然な甘み、そして磯の香りが口いっぱいに広がり、食欲をそそります。添加物や強い味付けに頼らず、素材の持つ力を活かして炊き上げたこの佃煮は、ごはんとの相性も抜群です。
ご家庭でも再現可能な佃煮は、調味料を控えめにしてのり本来の味を楽しむのがコツです。ごはんのお供にはもちろん、おにぎりや卵かけごはんにもぴったりの一品です。
子どもたちに伝えるのりづくりの心
のり養殖者である名倉さんは、地元の阪南市立西鳥取小学校を訪問し、のりの作り方や仕事の大切さを子どもたちに伝える活動も行っています。この取り組みは、地元の特産品を次の世代に伝えていくための食育の一環として、高く評価されています。
子どもたちは、実際にのりがどうやって育つのか、どんな工程があるのかを学びながら、地元で作られる食材に対する関心と誇りを持つようになります。こうした活動が、地域の未来を支える第一歩となるのです。
家庭でも楽しめる!のりを使った絶品料理を紹介
名倉さんの妻・やよいさんは、家庭で手軽に楽しめるのりレシピを紹介してくれました。まず紹介されたのは「のりのお好み焼き」。キャベツの代わりに板のりをたっぷり使い、通常より水分を控えめにして焼き上げることで、弾力のある食感と香ばしい香りが特徴のお好み焼きが完成します。
もう一品は「のりの炊き込みごはん」。土鍋に板のりを敷き、上にごぼうやにんじん、ねぎ、里芋、長芋、紅ショウガなどの具材を乗せて炊き上げると、磯の香りがふわっと広がる絶品ごはんになります。のりがごはんのうまみを引き出してくれるので、塩分控えめでも満足感のある味わいに仕上がります。
スタジオでは、これらの料理を試食。のりのお好み焼きは、ソースの濃い味に負けないほどの存在感があり、ふわふわではなくしっかりとした弾力がある新しいおいしさとして注目されていました。
まとめ:阪南市ののりには、自然と人の力が詰まっている
大阪・阪南市ののりづくりには、自然と共に生きる知恵、何世代にもわたる職人たちの経験、そして地域の人々の想いが詰まっています。300手間という言葉に象徴されるように、一枚ののりが食卓に届くまでには、数えきれないほどの手間と工夫が積み重ねられています。
今回の放送を通して、のりという身近な存在の背景にあるストーリーを知ることができ、これからの食卓でのりを味わうときの気持ちも、きっと変わるはずです。阪南市ののりは、味だけでなく、その背景にある人の力や地域の歴史までも感じさせてくれる、まさに“食べる文化財”です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


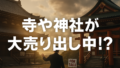
コメント